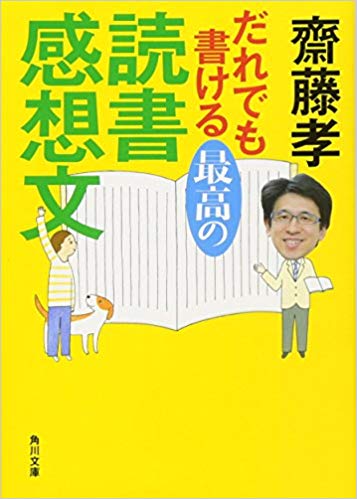- ブログでの本の紹介の書き方を知りたい
- 齋藤 孝 先生の『だれでも書ける最高の読書感想文』の感想が知りたい
- 読書感想文が書きたくなるおすすめの本を知りたい
この記事はそんな方へ向けて書いています。
この記事でわかること
- ブログでの本の紹介の書き方
- 『だれでも書ける最高の読書感想文』のグッときたところベスト3、口コミ6つ
- 齋藤孝先生おすすめの読書感想文が書きたくなる本36選
本記事の信頼性
- ブログ歴:2019年1月にブログ開設
- ブログ実績:過去最高は月62,000PV、月54,000円(確定)
- 180冊以上の読書感想文・書評を公開
読書感想文が苦手です。
読書感想をブログに書いても、なかなか「うまく書けた」と思えることがないからです。
苦手意識もあり、書く前は少し気が重くなります。
書き方で悩んでいるのです。
そんな自分を救いたくて「だれでも書ける最高の読書感想文」を手に取りました。
本記事では、著者・齋藤 孝 先生から学んだ「ブログで本の紹介の書き方」を解説します。
本書を読むと「読書感想文なんて楽勝。うまく書く必要なんてないんだ。気持ちでめげるな」と背中を押されます。
「読書感想文なんてカンタンだ」という気持ちが湧き上がってきます。
「考えたこと、思ったこと」を自由に書くのが、読書感想文です。
読書感想文が「楽しい」と思えてきます。
読書感想文の書き方で悩んだら読む本なのです。
記事最後では「ちきりんさん、村上春樹さん」の読書感想文の書き方を引用しました。
Contents
ブログで本の紹介の書き方【6つの手順でだれでも書ける】

ブログで本の紹介をする6つの手順
- リード文
- グッときたところベスト3
- どんな人におすすめなのか
- 著者のプロフィール
- 口コミ
- まとめ
1.リード文
- この記事でわかること
- 本記事の信頼性
- 何が書かれた記事なのか
- この記事を読むとどうなるのか
リード文の目的は、本文への誘導です。
2.グッときたところベスト3
- グッときたところベスト3の引用
- 引用した理由と体験談(思ったこと、感じたこと)
3.どんな人におすすめなのか
- おすすめな人を3名
- おすすめしない人を3名
4.目次、著者のプロフィール、本の詳細
- 目次
- 著者のプロフィール
- 詳細(出版社、ページ数、発売日など)
5.口コミ
- 良い口コミ
- 悪い口コミ
Amazonの口コミは誰もが見るので、Twitterから集めます。
6.まとめ
以下を書きます。
- グッときたところベスト3をつなげるとどうなるか
- 本を読んでどう変わったのか(ビフォーアフター)
- 具体的なアクションプラン
どれか1つ書けば十分です。
書くことに困ったらチェックするポイント
- 本を読むきっかけは
- なぜこの本を読もうと思ったのか
- 何を解決したかったのか、どんなことを知りたかったのか、期待したことは
- 読み始めて初めてわかったことは
- 最初の数ページで印象に残った文章は
- 本を読んで考えたことは
- 本の中の人と、自分の共通点、相違点は
- 本を読んでない人へ伝えたいことは
本を読んで何を考えたのかが、オリジナルです。
よく読まれている読書感想文5本
どれも手放せない本です。
【感想】『だれでも書ける最高の読書感想文』のグッときたところベスト3

グッときたところベスト3
- 1位:「グッときたところ」から、とくにいいと思ったところを3つにしぼりこむ
- 2位:「なぜこの本で感想文を書こうと思ったのか」から始める
- 3位:人は「違い」に目を向けると反応しやすい
1位:「グッときたところ」から、いいと思ったところを3つにしぼる
変化するきっかけになった文章なのです。
読書感想文に「グッときたところベスト3」を書くようになったからです。
以前は気に入った文章を引用していました。
漫然と選んでいたので、メリハリのない文章になりがちです。
しかし本書のベスト3方式を取り入れてから、文章に締まりが出てきました。
読書感想文が書きやすくなったのもメリットです。
読書のインプットの質も上がりました。
「グッときたところ」を探しながら読むからです。
アウトプットを前提とした読み方なのです。
ベスト3という数字も、多すぎず、少なすぎずで丁度良いです。
引用する数を決めないとキリがありません。
読み手にも、書き手にもベスト3がしっくりくるのです。
本書には他にも感想文のメソッドが満載で、色々と試したくなります。
2位:「なぜこの本で感想文を書こうと思ったのか」から始める
読書感想文で「本の概要を紹介しよう」と思っていました。
しかし「なぜ」から書き始めることもありです。
書きやすいからです。
たとえば「なぜ本書を読もうと思ったのか」の理由は下記です。
- 読書感想文がうまくなりたいから
- 読書感想文をこれからも書いていくつもりだから
- 早めに方法論を読めば、試行錯誤の回数を増やせるから
本書を読むことは当然なのです。
「なぜ本書を買おうと思ったのか」に答えるのも、読書感想文が書きやすくする秘訣ですね。
3位:人は「違い」に目を向けると反応しやすい
「読む前、読んだ後」の違いを比較して文章にします。
ビフォーアフターに注目するのです。
「本書のターニングポイントはどこか」を書こうと思いましたが、たくさんありすぎて迷います。
強いていうなら、やはり「グッとくるいい言葉をさがす」がターニングポイント。
小説の読書感想文を書くときも役立ちます。
»【小説の感想まとめ】読んできた12冊+これから読みたい10冊
本は自分だけの言葉を探すために読むのです。
『だれでも書ける最高の読書感想文』は、本の紹介の仕方に悩んでいる人におすすめの本

おすすめの人、おすすめしない人
こんな方におすすめ
- 文章作法と表現を知りたい人
- 面白そうな本を知りたい人
- 読書感想文の書き方、本の紹介の仕方に悩んでいる人
決めたことが1つあります。
「他人の読書感想文を盗まない」です。
盗用すると自分の頭で考えなくなります。
齋藤先生も「盗用するなら、書くな」といいます。
自分のアタマでウンウン唸りながら、考えて書くことで成長できるのです。
「書評の書き方」を知りたい人にはおすすめしません。
あくまで感想を書く読書感想文に最適です。
5つの章
第1章.きみにも「最高の読書感想文」が書ける!
第2章.もう悩まない!スラスラ書けるようになる方法
第3章.押さえておきたい文章作法と表現のツボ
第4章.キラリと光る感想文の書き方
第5章.読書感想文を書くための、失敗しない本選びのコツ
書籍情報
| 書名 | 「だれでも書ける最高の読書感想文」 |
|---|---|
| 著者 | 齋藤 孝(公式サイト) |
| 単行本 | 254ページ |
| 出版社 | KADOKAWA/角川書店 |
| 発売日 | 2012/6/22 |
『だれでも書ける最高の読書感想文』の口コミ6つ

「Twitter」から口コミを6つ集めました。
- 読書感想文に正解はない
- 読書感想文のコツがわかる
- もっと早く出会いたかった
- AKBの読書感想文に触発
- 読書感想文のヒントがたくさん
- 本の選び方から書き方のコツまで
Twitterで読書感想を書くコツ
- 読む前の状況
- 気づき、抽象性
- 具体的アクション
140字にまとめるにはこれだけで十分です。
【齋藤 孝 先生おすすめ】読書感想文が書きたくなる本36選
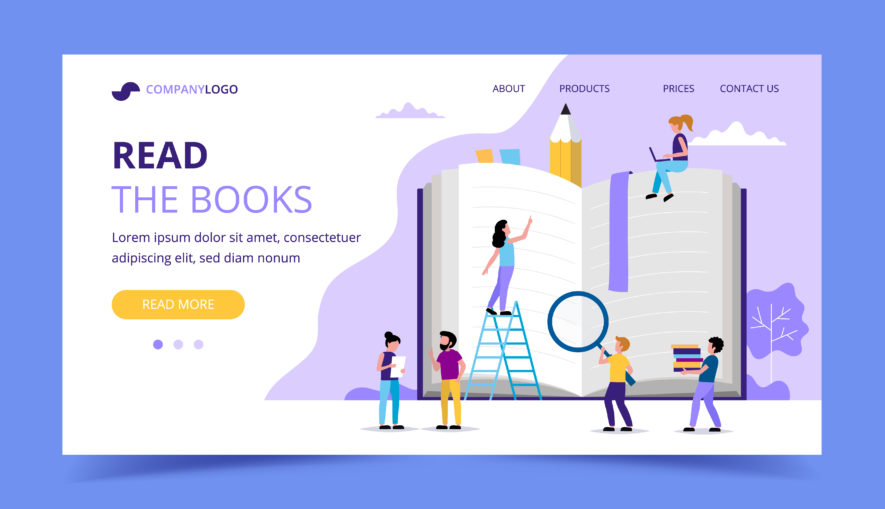
最後に齋藤孝先生のおすすめ本を11ジャンル、36冊を紹介します。
1.スポーツをテーマにした青春小説
2.音楽家の本
3.SFもの、冒険もの
4.読書案内
5.短編の名作
6.海外の著名作家の短編
7.名作の読みがえり版
8.まるごと読まなくていいもの
9.新書
10.科学好きな人に
11.ガツンと胸に刺さる言葉がほしいなら
まとめ:ブログやTwitter、読書感想文の宿題などで試してみるのもあり

まとめ:ブログで本の紹介をする6つの手順
- リード文
- グッときたところベスト3
- どんな人におすすめなのか
- 著者のプロフィール
- 口コミ
- まとめ
まとめ:グッときたところベスト3
- 1位:「グッときたところ」から、とくにいいと思ったところを3つにしぼりこむ
- 2位:「なぜこの本で感想文を書こうと思ったのか」から始める
- 3位:人は「違い」に目を向けると反応しやすい
読書感想文の座右の書です。
紹介した書き方の他にも「書き方のヒント」があります。
書き方に迷ったり悩んだりしたときは、助けになります。
最後にちきりんさん、村上春樹さんの読書感想文の書き方を紹介します。
- ちきりんさん:本を読んで、自分のアタマで考えたこと書く
- 村上春樹さん:途中でほとんど関係ない話を入れる(ちょっと内容と繋がっている)
読んで得られた発想や気づき、考えたことを書く。
途中で、連想したことを入れる。
以上です。
P.S. ブログやTwitter、読書感想文の宿題などで試してみるのもありですね。
関連記事アウトプットが苦手でも書評の書き方がわかる本【テンプレートあり】
関連記事低学年向けの作文の書き方がわかる本【調べたことを1つでも入れる】