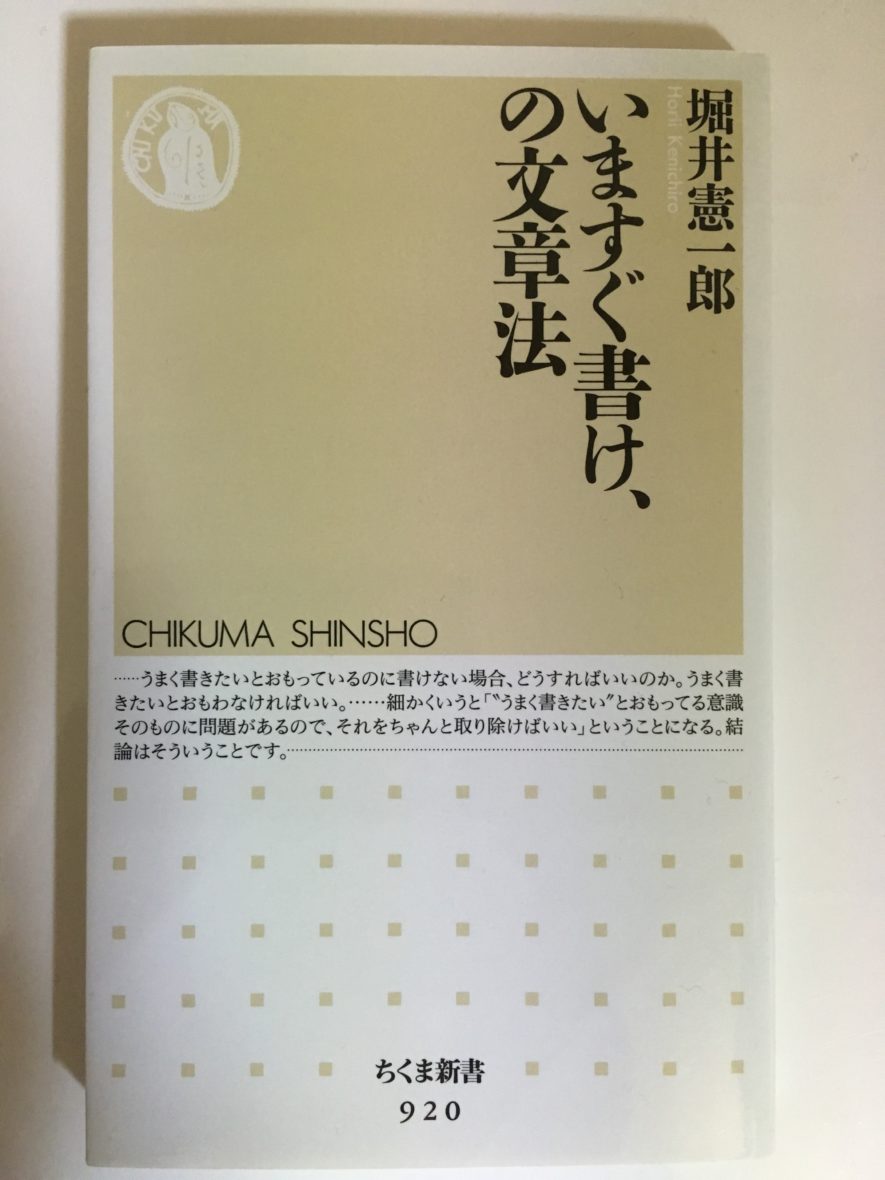「今すぐ書け、の文章法」を読んだ理由は3つです。
- 文章を書いてみたいけれど、うまくいかない
- 書こうとしても、なかなかうまく書き出せない
- 少しだけ書いても、それ以上書き進めずに止まってしまう
本記事を書いている私は、2019年1月にブログ開設しました。
ブログ実績の過去最高は、月62,000PV、月54,000円(確定)です。
この記事でわかること
- 「今すぐ書け、の文章法」の書評【グッときたところベスト3】
- 読んで変わった3つのこと
- 口コミ10個、動画2本
結論
- 読んでいる人のことをいつも考えて書けばいい
- 文章を書くのは人を変えるため
読み終わってから、どこでもいいので本書のページを開いてみる。
たいていのページには線が引いてある。
2回に1回はページの角が折られている。
線が引いてある、ページが折られている周辺を読んでみる。
惹きつけられ、ぐいぐいと読み進めてしまう。
恐ろしいです。
読んできた文章指南の本で、いちばん影響を受けています。
この記事を読むことで「本書の恐ろしさ」がわかります。
文章はサービス業です。
著者は「お金をもらって文章を書く限り、サービス業である」といいます。
サービスとは「読んでいる人のことを、いつも考えること」です。
文章のすべてです。
いちばん押さえなくてはいけません。
細かい文章技術などは少し気にしておけばいい程度なのです。
本記事を書き終える前に、また1回、読み終えてしまいました。
Contents
【文章とはサービス業】本質は「読んでいる人のことをいつも考える」
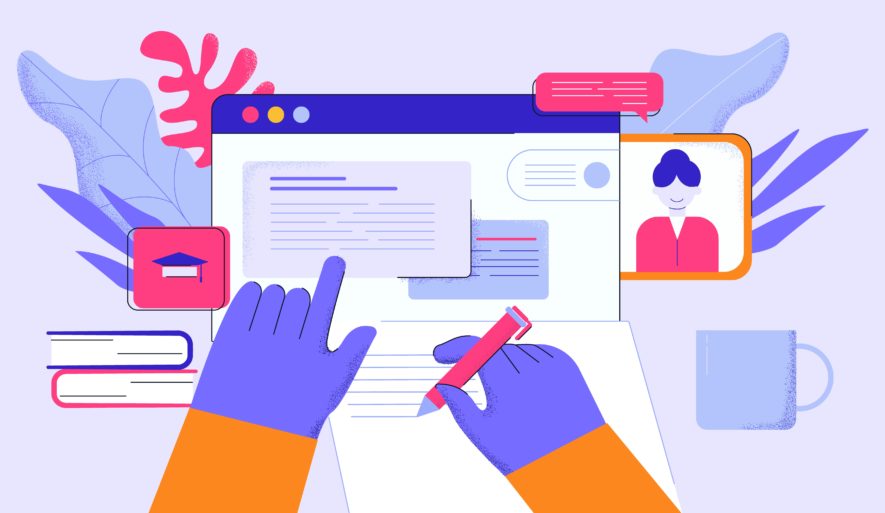
グッときたところベスト3
- 1位:文章は人を変えるために書け
- 2位:事前に考えたことしか書かれていない文章は失敗である
- 3位:頭は身体に勝てない
1位:文章は人を変えるために書け
文章を書くのは、人を変えるためである。
本書のタイトルになる言葉です。
人を変えるとは何か?
人を変えるとは、何かが動くことです。
- 読んだあと、行動したくなる
- 読んだあと、誰かに話したくなる
- 読んだあと、喜ぶ、悲しむなど感情が動く
「行動」と「感情」のどちらかを動かすのです。
なぜ、人を変えるために書くのか?
変わらないと「時間のムダ」だからです。
- 文章とはサービス業
- 読者を変えることが最大のサービス
- 読者を変えるには読者の立場で考え続ける
読む前と読んだ後では、変わっていないといけないのです。
人を変えるものを書くにはどうすればいいのか?
「いつも人を変えるものを意識して生きる」です。
「何かおもしろいことはないか」「新しい工夫はないか」といつも考えながら生きるのです。
ここまでで本書の2つの柱が出てきました。
- 読んでいる人のことをいつも考えて書けばいい
- 文章を書くのは人を変えるためである
本書は上記2つをさまざまな角度から解説しています。
2つが身につけば、本書の元は十分とったと言えます。
2つを意識してひたすら書けばいいのです。
ひたすら読めばいいのです。
文章を書くのはサービス業です。
2位:事前に考えたことしか書かれていない文章は失敗である
文章がどう変化するか、わかりません。
いつもわからない
たとえば、本記事も「まとめ」に何を書くか決まっていません。
考えてもわからないからです。
書いているうちに何かが思い浮かびます。
浮かんだ言葉を1文字1文字、書いていくだけ。
「文章を書くのは難しい」と思っています。
しかし文章が勝手に走り出すとラクなもの。
手綱だけと握っておけば、勝手にどこかへ運んでくれます。
野球の監督になった気持ちです。
ベンチに座って試合を見ているだけ。
投手の交代や代打などの指示はします。
試合に勝つためです。
試合に勝つとは「文章を完成させること」です。
読者を変える文章を完成させるために、指示を出します。
試合の結果を予想できても、試合の流れは予想できません。
どんな試合になるのかわからない
事前に試合の結果は、知りたくありません。
結末がわかってしまうと面白くないからです。
文章がおもしろいのは2つ
- 自分でも思ってもみなかったところに着地すること
- あとで読み返して、自分で「おもしろい」と思えること
むずかしい質問があります。
自分がおもしろいものが、読者におもしろいのか?
わかりません。
ただ自走した文章には力があります。
伝わる力です。
伝わったあと、読者がどう思うかは自由です。
誰にも止められません。
願わくばせめて1ミリでも動かしたいもの。
行動でも感情でもどちらでもいい。
たった1ミリを動かすために、パソコンに前に座り続け、文章を書き続けるだけなのです。
3位:頭は身体に勝てない
書く。
アタマでは考えずに書く。
アタマに負けないように身体で書く。
文章を書くのは、身体でするもの。
村上春樹さんが何かの書籍で「文章と身体の関係」を書いていたのを思い出しました。
身体性を大事にしているのが印象的だったのを覚えています。
以下のように汲み取りました。
- 文章を書くには体力が必要なので、ランニングを始めた
- 健康的で規則正しい生活が、文章では反対のものを生み出す
- 集中できる朝の数時間に原稿用紙10枚書いて、それ以上は書かない
- 午前中に大事な仕事を終わらせ、午後は読書や音楽などでリラックス
やはり文章には身体が関係しているのです。
会社員時代、慢性蕁麻疹になっても1年半ガマンしながら仕事を続けました。
結果、身体を壊しました。
身体の声を聞いていれば休職せずにすみました。
身体は壊しましたが、アタマは壊れていません。
壊れるのは身体からです。
身体はアタマでは制御不能なのです。
アタマより身体の声を聞くべき。
文章はアタマで書かない。
文章は身体で書くもの。
「アタマの役割はなんだろう?」という疑問が浮かぶかもしれません。
アタマの役割は「読む」ことです。
書いたものを冷めたアタマで読む。
書くのはカラダの役割。
読むのはアタマの役割。
それでいいのです。
「今すぐ書けの文章法」を読んで、変わった3つのこと

変わったこと3つ
- 文章を書くのが楽しくなった
- 村上春樹さんの文章を読むようになった
- 文章を書く前に本書を読むようになった
1.文章を書くのが楽しくなった
自由になれた気がするからです。
文章の型や決まり、ルールに囚われていました。
「文章はこう書かなければならない」というルールです。
しかし呪縛から抜け出せました。
正確には「文章の方や決まり、ルール以上に大事なことに気づいたから、気にならなくなった」です。
文章を書くのは楽しいかもしれません。
2.村上春樹さんの文章を読むようになった
いい文章を書くためにどうすればいいか?
本書の答えは「先人の書いたよい作品、よい文章をよめ」です。
村上春樹さんの文章を毎日読むようにしています。
歴史上の人物であり、大作家だからです。
よい文章を大量に読む。
村上春樹の文章なのです。
»【村上春樹の文章力】文章は何度も「読み直し、書き直し」でうまくなる
3.文章を書く前に本書を読むようになった
学んだことを忘れたくないからです。
線を引いた箇所、ページを折った箇所、パラパラと読み返してから書くようになりました。
なお「文章の細かい技術」は書かれていません。
細かい技術は、あとでどうとでもなります。
それより以前の問題について解説したのが本書です。
「今すぐ書けの文章法」の口コミ、動画
Twitterの口コミ10個
1.書くことで大切なものは勢い
書くことで一番大切なことは?どこかで喉に引っかかる🐟の小骨が、「今すぐ書け、の文章法」を読んで小骨がとれた。
書くことで一番大切なものは 勢い 。
勢いがあるから読み手が引きこまれる。そして勢いを増す方法は、1.立つて書く2.締め切りを決める。頭じゃなく身体で反応するスポーツと同じ。— ジョージ💖金森式+1日1食+筋トレ (@orpelas) June 1, 2020
2.書くとは肉体の鍛錬
「今すぐ書け、の文章法」読書感想のポイント:
・ちゃんとした文章を書こうとしない
・文章は人を変えるためだけに書け
・面白い企画は突然結論が浮かぶ
・自己弁護は不要根拠を示し断定する
・読むのは書くため読まないと書けない結局書くとは、肉体の鍛錬、考えても上達しない #ブログ書け !
— ジョージ💖金森式+1日1食+筋トレ (@orpelas) June 2, 2020
3.「何か変だな」をいくつストックしているか
『今すぐ書け、の文章法』堀井憲一郎 著
— 小林ひろかず (@D45316647) June 2, 2019
4.1人称は書かない
【アウトプット】誰やねん、私は〜って
今すぐ書け、の文章法 堀井憲一郎
文章の冒頭に一人称は書かない事が
読み手にとってわかりやすい文これを言われてハッとした。
顔も名前も知らない奴の一人称に
イメージが沸かずに意味がないから— ポチ (@pochitama0) June 4, 2020
5.「思う」は不要
『今すぐ書け、の文章法』
✅文章は言い切らないといけない
この中に出てくる
「言い切れないなら書くな」という言葉はすごく響きました。/
文末の"思う"は不要です。
\なぜなら【不安】を読み手が感じてしまうから🔰
書くことへの不安を押し切り
出していくのが"文章を書く"ということ‼️ pic.twitter.com/4y6gQqZs4B
— ぶちょー/ブログ×PPCアフィ (@Bucyosan_) November 2, 2019
6.改行を増やす
最近はブログでの改行を増やしたんだけど(今までは改行多い = ダサいと思っていた)、そうしたら文章がマジで書きやすくなった。
このノウハウはいますぐ書け、の文章法から学びました。圧倒的感謝!https://t.co/8mKaN0oImg— Manabu (@manabubannai) January 10, 2018
7.1人に向けて書く
今までどれだけ自分と意見の違う人と関わってきたか、もペルソナに対する想像力の違いを生みそう。「今すぐ書け、の文章法」で、万人向けに書くより1人の具体的な相手に向けて書く方が色んな人に刺さるって言っててなるほどと思った。 https://t.co/NFY7SAnSdJ
— ヒトミ⭐クバーナ🍉日本語教師たまにライター (@hitomicubana) December 10, 2016
8.グサグサくる本
今読んでる書籍は堀井憲一郎の「いますぐ書け、の文章法」です。ちょっとくせのある文体ですが、内容的にはグサグサ来るような良い本でした(^O^)
— koka (@koka_affi) June 12, 2015
9.新しい見方が増えた
半年ぐらい前に買って少しずつ読んでた堀井憲一郎さんの「今すぐ書け、の文章法」を読み終わった。クリティカルに図星を突かれたことも多いし、文章を書くということに対してだけでなく、新しい見方が増えた。
— GJCTC (@gjctc) April 25, 2013
10.まず自分が驚く
#読書メモ 『今すぐ書け、の文章法』
まず自分が驚け!
ある出来事もしくはある話によって、自分が驚き自分が変わったと感じ、それを人に伝えようとする。
その心持ちが根幹にあれば、ちゃんとした文章になる可能性がある。
— ろいど(さとうたかやす)|ブログ×WEBライターで副業 (@roido_blog) November 8, 2020
レビュー動画2本
1.結論:文章力を高める方法【ポイントは2つ/向き不向きはない】
動画内で『今すぐ書け、の文章法』がおすすめされています。
2.【10分で解説】いますぐ書け、の文章法
まとめ:文章が書けなくても、振りかぶらずに今すぐ書こう

まとめ:グッときたところベスト3
- 1位:文章は人を変えるために書け
- 2位:事前に考えたことしか書かれていない文章は失敗である
- 3位:頭は身体に勝てない
書く。
ウダウダ能書きをたれてないで書く。
まず書く。
勢いで書く。
書き続ける。
読者の立場を考え、読者を変えるために文章を書く。
カラダで書く。
アタマで読む。
よい文章を大量に読む。
暗唱できるまでカラダに刷り込む。
文章は人を変えるために書く。
以上です。
P.S. 振りかぶらずに、今すぐ書く。
関連記事ブログの文章力を鍛える本16選【書いて、読み直して、また書こう】
関連記事ブログ初心者向けおすすめ本36選まとめ【基礎18冊+応用18冊】