- 作文力をつけるには、どうしたらいいだろう?
- 『いますぐ書けちゃう作文力』の感想を知りたい
この記事はそんな方へ向けて書いています。
この記事でわかること
- 『いますぐ書けちゃう作文力』齋藤 孝【著】の感想
- グッときたところベスト3、口コミ5つ
- 齋藤孝先生おすすめの作文力をつける本23選
本記事の信頼性
- ブログ歴:2019年1月にブログ開設
- ブログ実績:過去最高は月62,000PV、月54,000円(確定)
筆者の「齋藤 孝 先生」は明治大学の教授です。
150冊以上の著書があり、ベストセラーは「声に出して読みたい日本語」です。
ジャンルは「読書論、コミュニケーション論、教育、勉強、言葉」など多数です。
本記事は、そんな齋藤孝先生の著作「いますぐ書けちゃう作文力」の読書感想です。
この記事を読むことで「作文力をつけるにはどうすればいいか」がわかります。
小学生向けですが、得るものがありました。
村上春樹さんから学んだ文章力を上げる方法は「【村上春樹の文章力】文章は何度も「読み直し、書き直し」でうまくなる」で解説しています。
Contents
低学年向けの作文の書き方がわかる本【グッときたところベスト3】

グッときたところベスト3
- 1位:調べたことを何かひとつでも入れる
- 2位:引用した理由と、体験談を書く
- 3位:自分なりのモノの見かたで書く
1位:調べたことを何かひとつでも入れる
- 調べたことを入れる
- 数字を入れる
たとえば、以下です。
- NG=『ちびまる子ちゃん』のコミックスはたくさん出ています
↓ - OK=調べたところ『ちびまる子ちゃん』のコミックスは全17巻
体験談は強いです。
調べたことは体験談になるのです。
体験談は数字とセットで強くなります。
2位:引用した理由、体験談を書く
「引用した理由と体験談」で作文は書けます。
本記事もグッときたところを引用しつつ、体験談を書いているからです。
引用した理由
「どんどん引用してもOK」と思えるようになったからです。
「引用はずるい」と思っていたのです。
引用した理由だけだと、すぐに文章が終ります。
感想より引用が長いのです。
どちらが主だかわからないです。
体験談で文章に厚みを出すことが大事なのです。
3位:自分なりのモノの見かたで書く
ブログはタイトルが重要です。
タイトルでクリック率が変わるからです。
たとえば、以下です。
- 記事のベネフィットがわかるタイトル
- 読者の利益を考えたタイトル
タイトルで煽らないことが大事です。
タイトルで読者の疑問に答えつつ、少し角度を変えてタイトルをつけるのです。
作文力をつけたい人におすすめの本

おすすめの人、おすすめしない人
こんな方におすすめ
- 作文力をつけたい人
- 文章力を上げたい人
- 文章を楽しく書きたい人
本書に期待したことは3つです。
- 読書感想文がうまくなる
- 文章力の向上につながる
- 齋藤孝先生の本の好奇心
同じ思いを持つ人には、おすすめできます。
下記3人にはおすすめできません。
- 文章の型を知りたい人
- 硬い文章本を読みたい人
- 小説の書き方を知りたい人
あくまで「作文力をつけるにはどうすればいいか」に特化した本です。
口コミまとめ
Twitterから口コミ5つ
- 起承転結の転から考える
- 本はつながりで読む
- 文章で人がわかる
- 量は質に変わる
- 夏休みの宿題の作文に使える
Amazonの口コミ5つ
- 入門として良い
- 読んでいて楽しくなる
- 本書が作文力の見本
- 実践的でおもしろそう
- 作文の好きな人用の作文術
齋藤 孝 先生おすすめの作文力をつける本23選
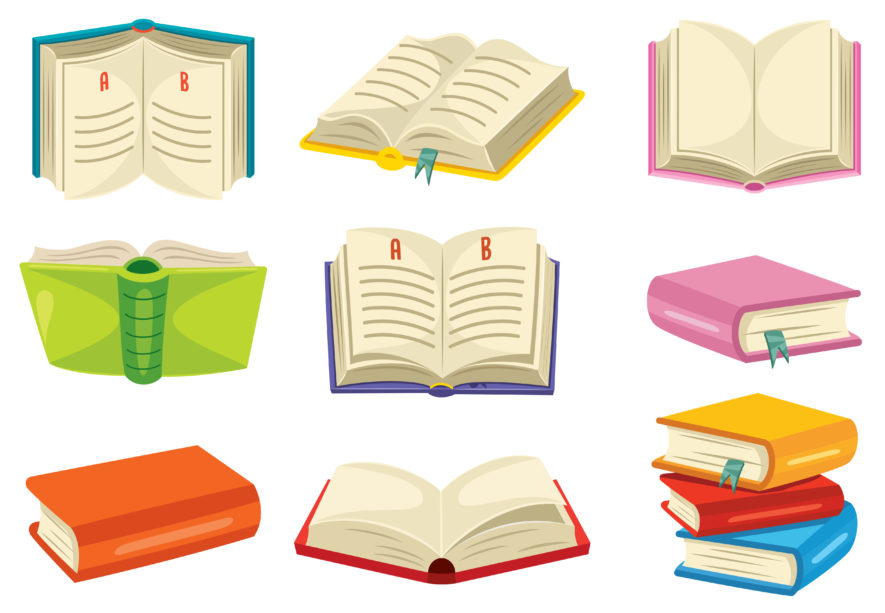
アマゾンのレビューで高評価な本ばかりです。
毎日、骨太の読書ライフが過ごせます。
まとめ:たくさん読み、たくさん書いて、作文力をつけよう

まとめ:グッときたところベスト3
- 1位:調べたことを何かひとつでも入れる
- 2位:引用した理由と、体験談を書く
- 3位:自分なりのモノの見かたで書く
上記は本書に書かれているメソッドの一部です。
作文力を上げる本質は2つです。
- たくさん読む
- たくさん書く
多くの文章に触れることが大切です。
文章術の本をたくさん読むのではなく、シンプルに「好きな小説家を見つけ、すべて読む」などです。
たくさん読み、たくさん書くこと。
文書を読み直して、書き直すこと。
以上です。
P.S.「たくさん読み、たくさん書いて」を繰り返します。
関連記事アウトプットが苦手でも書評の書き方がわかる本【テンプレートあり】
関連記事ブログで本の紹介の書き方がわかる本【6つの手順でだれでも書ける】

