- ブログの書評の書き方を知りたい
- 書評の書き方のテンプレートを知りたい
- インプットはしているが、なかなか身につかない
この記事はそんな方へ向けて書いています。
この記事でわかること
- 『黄金のアウトプット術』の書評の書き方【グッときたところベスト3】
- おすすめの人、おすすめしない人、目次、口コミ5つ
- レビュー動画3本
本記事の信頼性
- 書評の数:150本ブログに公開
- ブログ実績:過去最高は月62,000PV、収益54,000円(確定)
インプットばかりで「なかなかアウトプットできない」と悩む人は多いです。
なぜ悩むかというと、成長できていない感じがするからです。
私もそうでした。
インプット過多で人生が変わらないのです。
しかしアウトプット主体の書評を書き続けることで、少しずつ人生が好転してきました。
ブログでお金が稼げるようになってきたのです。
本記事では「黄金のアウトプット術」の書評の書き方を解説します。
この記事を読むことで「書評の書き方、話し方のコツ」などのアウトプット術がわかります。
インプットが好きで、アウトプットに興味がある方にはグイグイ読めます。
Contents
アウトプットが苦手でも書評の書き方がわかる本【グッときたところベスト3】
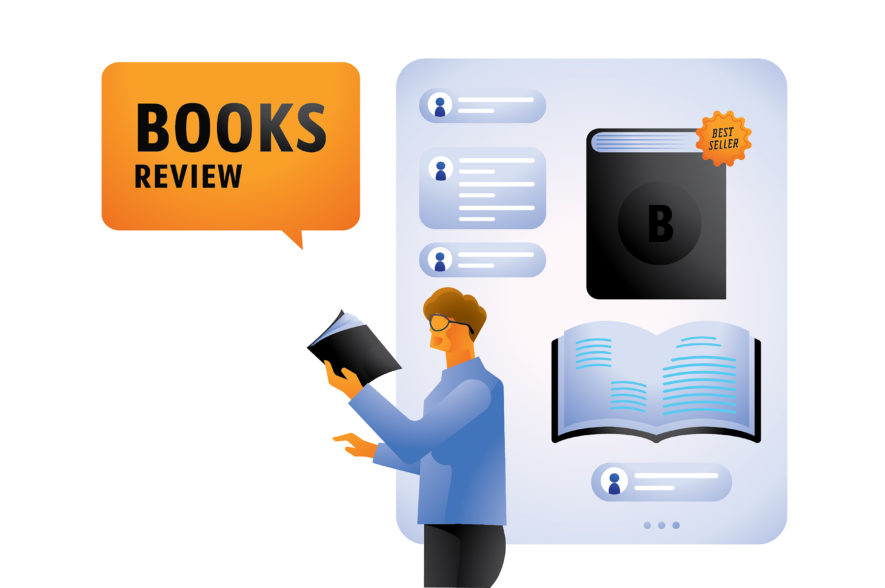
グッときたところベスト3
- 1位:書評の書き方(テンプレート)
- 2位:毛糸玉から毛糸をするする引き出すように、言葉を引き出す
- 3位:砂漠に暮らしながら、泳ぎを覚えるようなものだ
1位:書評の書き方(テンプレート)
1ブロック100文字×8ブロック=800字で書評を書く方法です。
- 第1ブロック:本の印象
- 第2ブロック:読者の想定
- 第3ブロック:中身の紹介
- 第4ブロック:概要の紹介
- 第5ブロック:具体的な中身の紹介(引用)
- 第6ブロック:具体的な中身の紹介(引用)
- 第7ブロック:著者の紹介
- 第8ブロック:読者の背中を押す
メリットです。
- ブロックごとの目的を意識できる
- 100文字は負担にならないので書きやすい
- 文字数が少ないので、ブロックの入れ替えも簡単
著者の紹介はあまり書いたことがなかったので、改善しました。
なお「ブログの読書感想文の書き方」は下記記事にまとめています。
» ブログで本の紹介の書き方がわかる本【6つの手順でだれでも書ける】
2位:人前で話す方法
話の要旨を毛糸玉にたとえて見失わないように、イメージしながら話す。
会社時代の朝礼では、いつもキーワードを暗記していました。
実際に話してみると、キーワードを忘れてしまうことも多かったです。
しかし引用文の方法であれば、キーワードの暗記不要です。
人前での挨拶は、アドバルーンを念頭に置くことで落ち着けます。
人前で話すこともアウトプットです。
アウトプットは、どれだけインプットしてもたいして上達しません。
アウトプットは、アウトプットでしか上達しないのです。
3位:アウトプットのスキルアップは必須
本の読みすぎで、消化不良になることはよくあること。
アウトプットよりインプットが多いからです。
体験談
英語の勉強をしていた時期があります。
英語の読書や添乗の英会話で役立つと思ったからです。
ただ実際に英語を使う機会は少ないです。
にもかかわらず、面白くない勉強に時間を使っていました。
今は英語学習は辞めています。
語学は必要に迫られたほうが身につきます。
インプットは必要に迫られてやるものです。
必要のないインプットはしなくていいのです。
アウトプットのないインプットは時間のムダなのです。
「このインプットはアウトプットできるだろうか」という視点が大事です。
書評の書き方を知りたい人におすすめの本
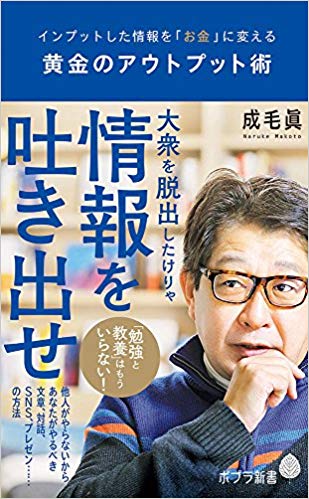
おすすめの人、おすすめしない人
こんな方におすすめ
- インプットばかりしている人
- 書評の書き方、話し方を知りたい人
- アウトプットの質を上げたい人
インプット過多の人に有益です。
価値観を変えてくれるからです。
たとえば、私は「インプットの量がすべて」という考えを持っていました。
量質転化の考えです。
本書を読むと「インプット量を増やす」という考えの危険性に気づけます。
危険性とは下記です。
- 自分で考えなくなる
- 新しいものが生み出せなくなる
- インプットしたことしかわからない
怖いことです。
大切なことは、インプットで引き出しを増やすことではありません。
より新しく、より良いものをアウトプットし続けること。
インプット過多の人が本書を読むと得るものがあります。
おすすめしない人
- アウトプット過多の人
- 自分のアタマで考えられる人
- 書評の書き方を知っている人
6つの章
書くアウトプットだけでなく、話す、見た目のアウトプットも解説されています。
第1章.アウトプット時代の到来
第2章.書くアウトプットがいちばんラク
第3章.やるほど上手くなる!話すアウトプット術
第4章.印象を操作する「見た目」のアウトプット術
第5章.インプットするなら「知識」ではなく「技法」
第6章.アウトプットを極上にする対話術
| 書名 | 「黄金のアウトプット術」 |
|---|---|
| 著者 | 成毛 眞 |
| 単行本 | 203ページ |
| 出版社 | ポプラ社 |
| 発売日 | 2018/4/10 |
成毛 眞さんの読書量は「本は10冊同時に読め」のとおりピカイチです。
難解なノンフィクションでも面白がって読める人です。
著者の「なんとか術とか、なんとか力という本を読むのはカッコ悪い」という言葉が印象的です。
Twitterの口コミ5つ
- SNS上でのアウトプットの方法を教えてくれている
- インプット過剰NG、アウトプット分割で敷居を下げる
- アウトプットが不足している人間は魅力がない
- アウトプットが足りないとアウトプット本を読もうとする
- アウトプットの上達はアウトプット
レビュー動画3本
まとめ:書評の書き方をインプットして、アウトプットで差別化

まとめ:グッときたところベスト3
- 1位:書評の書き方
- 2位:毛糸玉から毛糸をするする引き出すように、言葉を引き出す
- 3位:砂漠に暮らしながら、泳ぎを覚えるようなものだ
「情報過多の時代に、いかにアウトプット側にシフトしていくか」を痛感しました。
まず行動です。
「アウトプットで行動しながら、足りない部分、必要な部分をインプット」がスピード感があります。
じっくり計画している場合ではないのです。
「どうすれば早くなるか」という仕事で重要な考えがPDCAを破壊します。
まずは行動のDです。
インプットの質を高めるにはアウトプットが先なのです。
「アウトプットを先にしよう」という気持ちです。
- ブログ毎日更新する
- ツイートでアウトプットする
- 本や映画の感想をアウトプットする
いつもアウトプットのネタを考える必要があります。
インプットして、大量のアウトプットで成長できます。
アウトプットしているビジネスパーソンはあまりいません。
アウトプットするだけで、差別化できるのです。
以上です。
P.S. 書くこと、話すことのアウトプットで、自分を成長させたくなる本でした。
関連記事【文章とはサービス業】本質は「読んでいる人のことをいつも考える」
関連記事アウトプットが苦手な人へおすすめ本【1万時間にインプットは除く】


