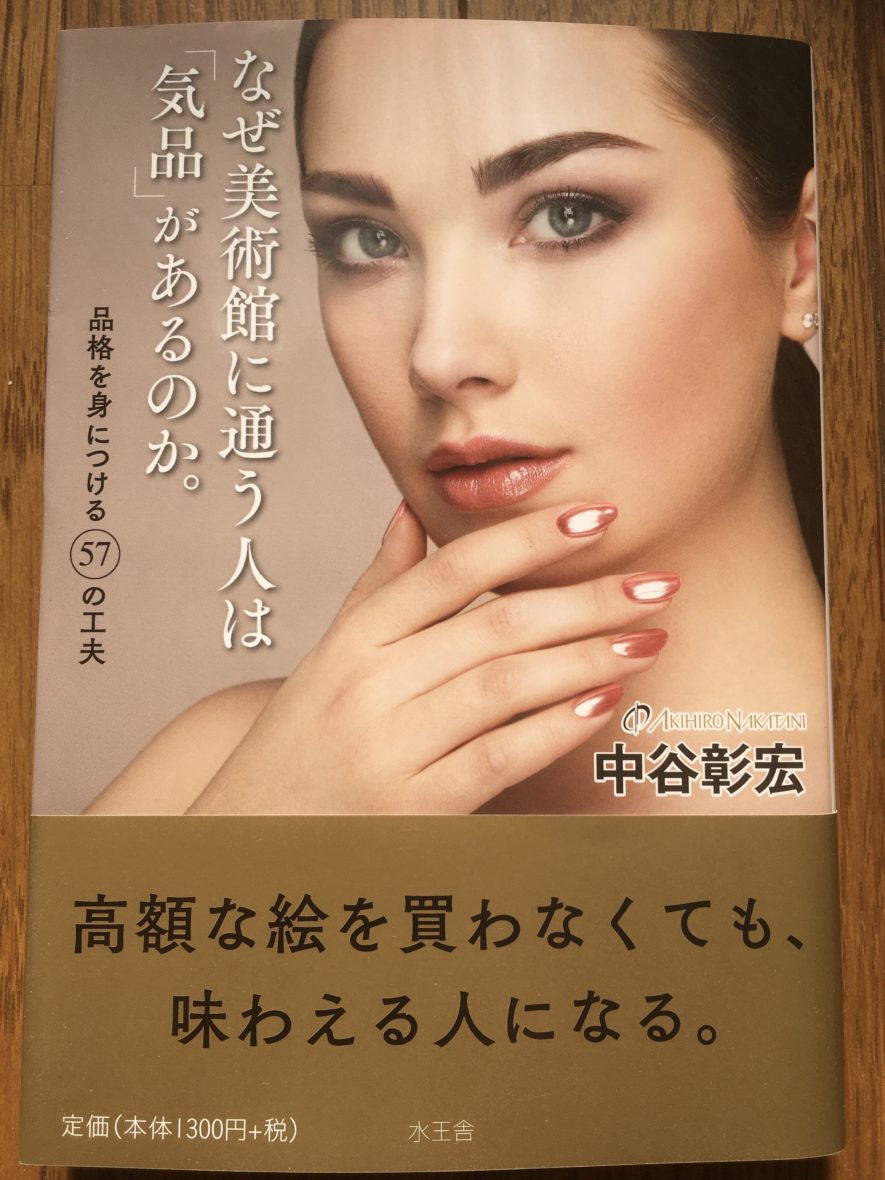- 美術館に興味がある
- 美術に関する本を読みたい
この記事はそんな方へ向けて「美術館へ行こう」と思える本を紹介します。
この記事でわかること
- 『なぜ美術館に通う人は「気品」があるのか』中谷彰宏【著】のグッときたところベスト3
- 概要、口コミ
本記事を書いている私は中谷彰宏歴27年11ヶ月で(1996年4月から)、著作はすべて読みました。
美術に興味はありませんが「中谷彰宏さんの本」という理由で本書を買いました。
» 中谷彰宏おすすめ本17選まとめ【文章4冊+成功5冊+ヒント8冊】
著者の中谷彰宏さんは月30件、年間で365件、美術展に行っています。
著者の学生時代の「1日映画3本、月間で100本のノルマ」を思い出します。
本記事は、『なぜ美術館に通う人は「気品」があるのか』の書評です。
美術館に行くことで「上には上がいる」がわかります。
美術に興味がなくても楽しめました。
Contents
【書評】『なぜ美術館に通う人は「気品」があるのか』のグッときたところベスト3

グッときたところベスト3
- 1位:自分の仕事よりも、もっと大変な仕事があることに気づける
- 2位:キャパが広がり、多様性に寛大になる
- 3位:明日古くなる情報より、一生使える知識を持つ
1位:自分の仕事より、もっと大変な仕事があることに気づけるのが気品
一流に触れることの大切さは、北野武さんも言っています。
北野武さんが女優の菅野美穂さんに「一流の美術館に行って、一流のものに触れたほうがいい」とアドバイスしました。
菅野美穂さんはすぐにパリのルーブル美術館へ行ったというエピソードがあります。
一流のものに触れる大切さを北野武さんは知っているのです。
本書からわかる美術館に行くメリット
- 一流に触れられる
- キャパが広がり多様性に寛大になる
- 美術館に行くことで姿勢が良くなる
- 芸術作品を通して、芸術家の生きざまを学べる
- 背伸びをして恥をかくことで、気品が身につく
- 美しいしぐさは美術館の美しいものを見ることで学べる
「美術館にメリットはない」と思っていましたが間違いでした。
すべては気品に通じます。
本書で下記の気持ちになりました。
- 美術館へ行こう
- 美術館へ行ってみようかな
- 少し美術を勉強してみようかな
- 美術館で器を広げてみようかな
きっかけがもらえたのです。
2位:キャパが広がり、多様性に寛大になる
美術館で思うのは「わけがわからない」です。
理解できません(知識不足もあります)。
過去に美術館へ行きました(下記)。
彫刻の森美術館
山の中にあるハイキングができそうな広い美術館。
1番奥にエリアにピカソ作品が展示されていますので、まずはピカソ作品を見学した後、戻りながら見学するのが効率的です。
屋外の所々に大きな彫刻作品が展示されています。
散歩しながら作品に触れられるため、天気の良い日にはうってつけの場所です。
「予習すると楽しめる」と感じました。
足立美術館
島根県の有名な美術館で、大きな庭園が印象的です。
旅行モデルコースに掲載の多い観光地のため、どうしても行ってみたかった美術館でした。
「底入れにかなりの手間をかけている」しか理解できなかったです。
他にも展示物は多数あり、軽く2時間は過ごせますが記憶に残っていません。
中谷彰宏さんは「そこに何かがないことに気づけるのが気品です」と言います。
深いです。
足立美術館には落ちているはずの落ち葉がないのです。
藤子・F・不二雄ミュージアム
プライベートで行ったミュージアム。
室内と室外の組み合わせです。
混んでいて、入るまでに30分並びました。
ドラえもん好きな方は楽しめます。
どの美術館も自分の意思というよりは「何かのきっかけで行った」という感じです。
「食わず嫌いせずに、行ってみる」が、キャパを広げます。
3位:明日古くなる情報より、一生使える知識を持つ
情報はいりません。
知識は有用です。
美術の知識は、一生使えます。
ブログと同じです。
できるだけ古くならないものを書く。
トレンド記事を書くよりは、資産になる記事を書く。
美術の知識も古典のように使える知識なのです。
ネットで得る知識は、誰にでも手に入る同じものです。
美術は体験や先生からの知識で、自分だけのオリジナルです。
知識があると楽しめるのが美術です。
『なぜ美術館に通う人は「気品」があるのか』で、美術館の楽しみ方を知る

美術館に行くことで得られるものがある
読み終わったときの感想です。
美術とはでしたが、美術館に行くときは再読します。
美術館の楽しみ方、作品の味わい方が書いてあるからです。
美術作品を見るのにも、予備知識がある・ないで楽しみ方が変わります。
- 知識がある
- 知識がない
美術作品を見るにもマナーがあります。
- マナーがある
- マナーがない
知識があって、マナーがある人が、美術館を1番楽しめます。
そんなことを気づかせてくれる本です。
「家族で美術館に行くのもあり」と感じました。
美術のある人生も良さそうです。
気品がある人は何が違うのか、知りたい人におすすめ
こんな方におすすめ
- 気品のある人は何が違うのか、知りたい人
- どうしたら気品を身につけられるか、知りたい人
- 芸術を日常生活に取り入れて、楽しみたい人
下記3人にはおすすめできません。
- 芸術が嫌いな人
- 気品を身につけたくない人
- おすすめ美術館情報を知りたい人
おすすめ美術館などの情報の載っていません。
5つの章
第1章.なぜ美術館に行く人は気品があるのか。
第2章.気品がある人は、イライラしない。
第3章.気品がある人は、暗闇を味わうことができる。
第4章.日常生活で、気品を磨く。
第5章.気品とは、学ぶ姿勢にある。
書籍情報
| 書名 | 「なぜ美術館に通う人は「気品」があるのか」 |
|---|---|
| 著者 | 中谷彰宏(公式サイト) |
| 単行本 | 182ページ |
| 出版社 | 水王舎 |
| 発売日 | 2020/3/2 |
『なぜ美術館に通う人は「気品」があるのか』の口コミ
Amazonの口コミ
要約します。
美術館へ行くとなぜ気品が?
- 絵を観ているときの姿勢が正しくなる
- 神社へ行った時の謙虚な気持ちになれる
- 静けさを味わうことで気品が出る
メモしておきたい言葉がたくさんあります。
まとめ:「なぜ人は美術館に行くのか」の答えは、美術で人生が広がるから
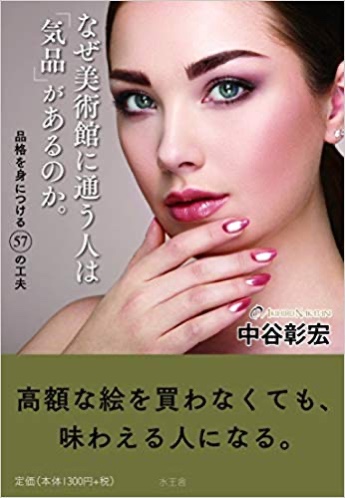
まとめ:グッときたところベスト3
- 1位:自分の仕事よりも、もっと大変な仕事があることに気づける
- 2位:キャパが広がり、多様性に寛大になる
- 3位:明日古くなる情報より、一生使える知識を持つ
どんなことからも学ぶ姿勢が、気品を生み出します。
人生に美術を取り入れるのもあり
本書を読むと「美術館へ行ってみようかな」と思えます。
人生に「美術」を取り入れるきっかけになる本です。
美術を取り入れることでキャパが広がります。
新しい視点を取り入れて、人生をもっと楽しみたい人へ本書を捧げます。
以上です。
P.S. 自分の人生を広げていくのが、美術なのですね。
関連記事【書評】メンタル不調のときに読む本『メンタルと体調のリセット術』
関連記事自己肯定感を自分で高める本『自己肯定感が一瞬で上がる63の方法』