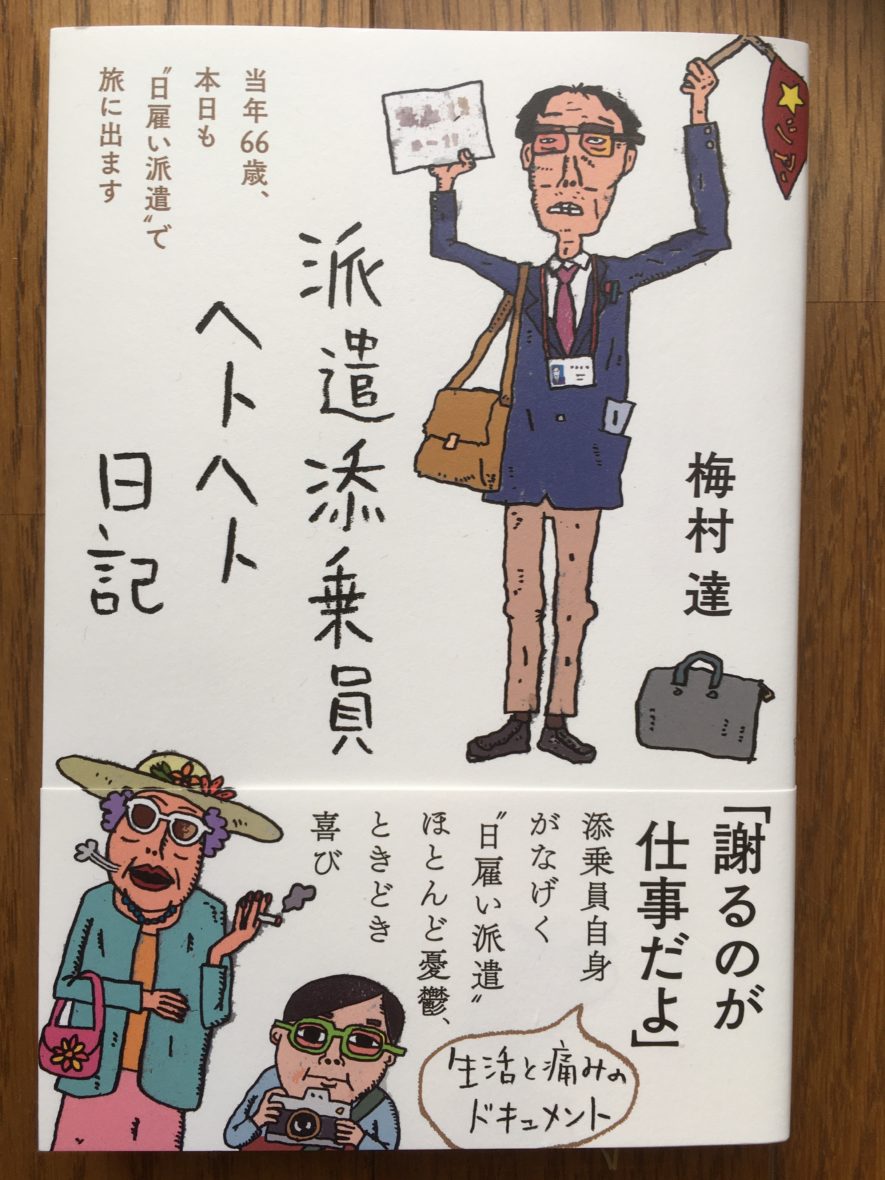- 『派遣添乗員ヘトヘト日記』の内容を知りたい
本書は「派遣添乗員の仕事内容を知りたい」という方に最適です。
本記事を書いている私は、旅行会社で19年8ヶ月勤務後、派遣添乗員になりました。
本書は添乗員として共感できる内容が多いです。
加えて、目頭が熱くなるところが2箇所あります。
本記事は「派遣添乗員ヘトヘト日記」のグッときたところ3つを解説した書評です。
この記事を読むことで、派遣添乗員の日常や仕事内容、クレームの辛さ、仕事の苦しさ・面白さなどがわかります。
添乗員は毎日が非日常です。
Contents
【書評】『派遣添乗員ヘトヘト日記』でわかる添乗員の苦しさ、面白さ

グッときたところベスト3
- 1位:リーダーは、学者、医者、易者、役者、芸者の心を持たなければいけない
- 2位:人の喜ぶ顔を見て、自分もまたうれしい心持となる
- 3位:自分のせいではない、などと思っていても仕方ないのだ
1位:リーダーは、学者、医者、易者、役者、芸者の心を持たなければいけない
駆け出しの添乗員のころ、お客さまを見ずに行程表ばかり見ていました。
お客さまに対峙すると面倒なことばかり言われるからです。
クレーマーは面倒なことを言ってきます。
相手にしたくなかったので「行程表ばかり見て」仕事のフリをしていました。
こんな姿勢は仕事はこなせても「役者、芸者」の域に達しません。
お客さまに喜ばれるのは「歩み寄っていく姿勢、寄り添う気持ち」です。
添乗員は究極のサービス業です。
肉体的にも精神的にもスーパーハードです。
どんな時も「お客さまを喜ばせ、楽しませ、満足させる」のです。
笑いをとることばかり考えていたツアー
肉体的にも精神的にも余裕のあるツアーでした。
バス車中ではいつも「どうやってお客さまを笑わせようか」と考えていました。
ツアーが終わり、お客さまから「めっちゃ楽しかったです」と言われたときは嬉しかったです。
喜ばせようとする気持ちが通じたのです。
余裕がないと、笑わせるのは難しいです。
段取りと体力で「余裕」を生み出すことが大事です。
2位:人の喜ぶ顔を見て、自分もまたうれしい心持となる
添乗の良いところは「お客さまの反応がダイレクトに返ってくる」です。
お客さまのためにした行動が、跳ね返ってくるのです。
ブログとは違います。
ブログは読者の反応を感じられません。
アナリティクスの数字では、アナログの反応はわからないのです。
あくまでデジタルな数字のみです。
無機質な「ページビューや滞在時間、収益」です。
ブログで高みを目指すのはありですが、気持ちは「これでいいのか」です。
引きこもって、パソコンをカタカタして、生身の人間との触れ合わずに完結してしまうからです。
本書から「ブログだけでいいの?」という言葉が聞こえてきます。
添乗のサービスがお客さまに手応えがなく「のれんに腕押し」もあります。
本書を読むと「派遣添乗員も捨てたもんじゃない」と思えます。
「これこそ人間味あふれる、人間臭い、感動物語じゃないのか」と著者は教えてくれます。
「素晴らしい職業についた」と感じたのです(苦しいこともありますが)。
» 旅行業界の内幕がわかる添乗員ブログ10選【旅行系インスタ10選】
3位:自分のせいではない、などと思っていても仕方ないのだ
著者が身につけた「クレームへの3つの法則」はすぐに試してみたいです。
- 1つ目:トラブルに際しては、落ち着いた態度を取る
- 2つ目:自分のせいではなくても不満を受け止め謝る
- 3つ目:起こった出来事に、迅速に対処する
「自分に非がなくても、不快感を与えたことには頭を下げるべき」という考えに賛成です。
「天気が悪くて申し訳ございません」とまでは言わなくていいですが「笑い」が取れそうならアリです。
なんでもかんでも謝ると、つけ込んでくるクレーマーもいますのでさじ加減が難しいです。
忘れられない言葉
- 気を使えるようになりなさい
- 決断できるようになりなさい
できないからこそ、刺さりました。
著者の「旅行会社のベテラン担当者に言われた言葉」もできないからこそ刺さったに違いありません。
できていないことや、図星は刺さります。
忘れられない言葉はヒントなのです。
『派遣添乗員ヘトヘト日記』はこんな人におすすめ
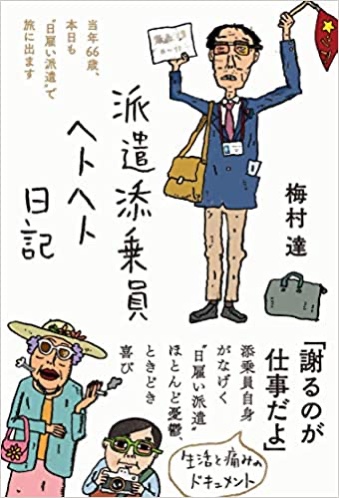
添乗に興味があり、泣きたい人へ
- 添乗員
- 添乗に興味のある人
- 募集型ツアーに興味のある人
本書には目頭が熱くなるエピソードもあります。
ちょっと泣きたい人にも向いてます。
文章が秀逸
まえがきを読んだ瞬間に、やられました。
文章がおもしろかったからです。
「派遣添乗員の体験談」も終始惹きつけられます。
しかしそれ以上に途中から「文章」に魅力を感じるようになりました。
「人と違う文章を書く」という姿勢が感じられます。
一語一語、一文一文、入念に言葉を選んでいる気迫が感じられるのです。
「文章」に魅力を感じたのは、村上春樹さんや奥田英郎さん以来です。
「まえがき」か、すでに他と違うのです。
»【村上春樹の文章力】文章は何度も「読み直し、書き直し」でうまくなる
募集型企画旅行の世界が見える
私の仕事は旅行会社の営業マンであり、ときどき添乗に行く添乗員です。
添乗に行くのは、いわゆる社員旅行や修学旅行などの「受注型企画旅行」と呼ばれるもの。
筆者が添乗に行くのは、新聞広告やメディアで参加者を集める「募集型企画旅行」と呼ばれるもの。
受注型と募集型では「添乗員の旅館の部屋や食事にも差がある」と初めて知りました。
添乗員の世界がわかる本です。
5つの章と著者プロフィール
第1章.団体ツアーって、どんな感じ?
第2章.ひとり参加の楽しみ方
第3章.団体ツアーの掟
第4章.旅は道連れ、世は情け
第5章.団体ツアーのお気に入り
| 書名 | 『派遣添乗員ヘトヘト日記』 |
|---|---|
| 著者 | 梅村 達 |
| 単行本 | 204ページ |
| 出版社 | フォレスト出版 |
| 発売日 | 2020/2/20 |
口コミ
Amazonの口コミの7割が5つ星です。
まとめ:派遣添乗員ヘトヘト日記は添乗員の日常がわかる本
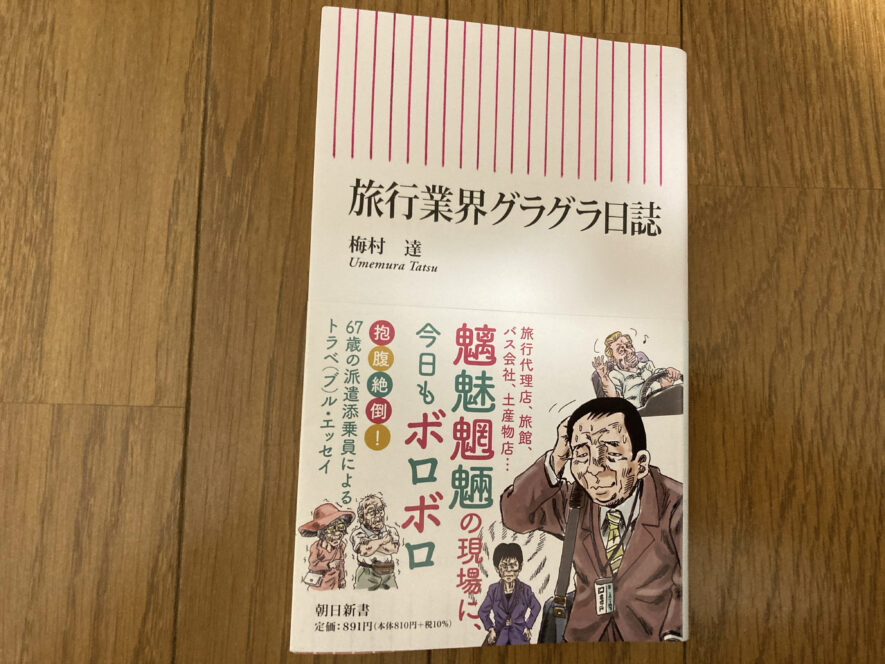
まとめ:グッときたところベスト3
- 1位:リーダーは、学者、医者、易者、役者、芸者の心を持たなければいけない
- 2位:人の喜ぶ顔を見て、自分もまたうれしい心持となる
- 3位:自分のせいではない、などと思っていても仕方ないのだ
添乗は誇りを持てる仕事
読んで良かったです。
「添乗」の仕事に誇りが生まれました。
「休職期間を終えたら、私も著者のように添乗員をやりつつ、ブログを書き続けたい」
そんな気持ちになれたのです。
人生の方向が、大まかに定まる本でした。
転機に『派遣添乗員ヘトヘト日記』に出会えたことに感謝します。
以上です。
P.S. 続編「旅行業界グラグラ日誌」をAmazonの中古本1円で買いました。
関連記事【添乗員のメリットとデメリット】派遣会社と旅行会社の軸で比較
関連記事添乗員になるには2つの方法【添乗員派遣会社に登録/旅行会社に入社】