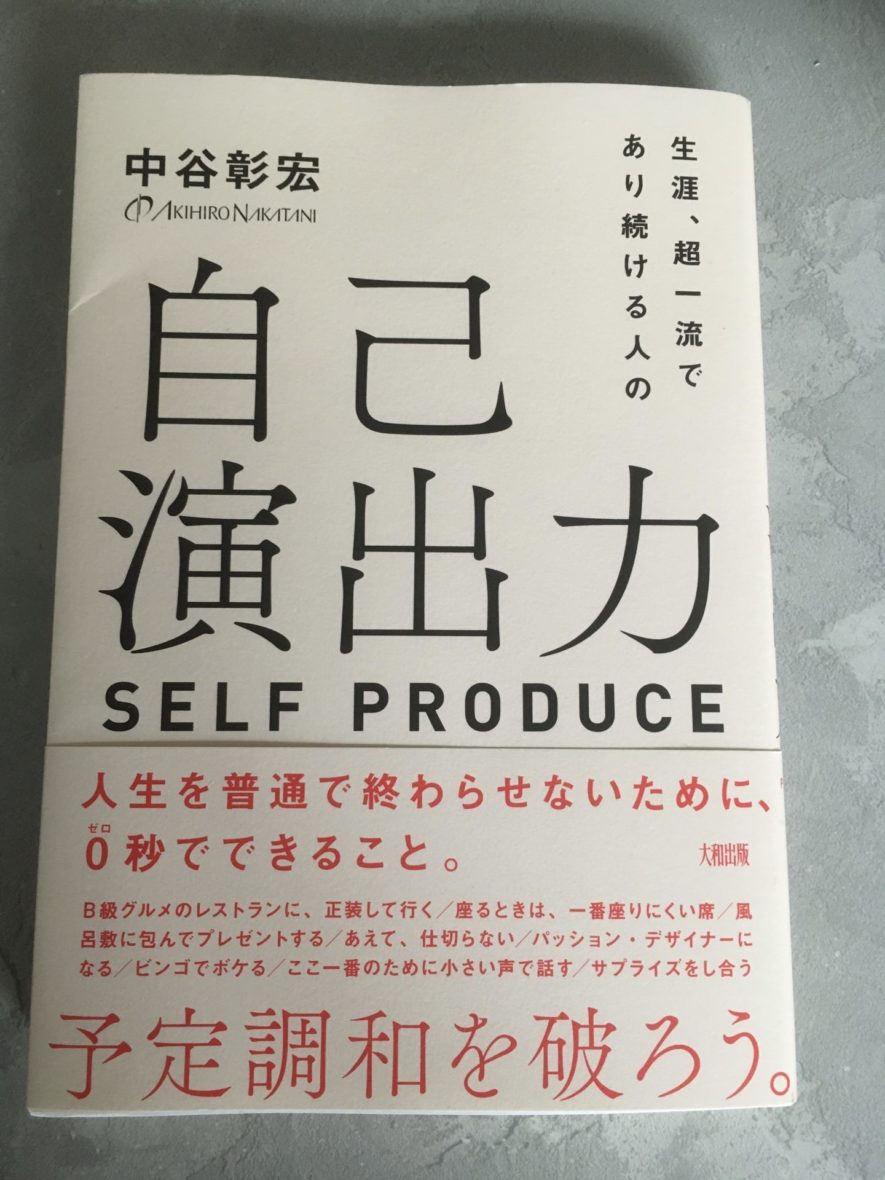- 自己演出とは何か?
- 自己演出の方法とは?
この記事はそんな方へ向けて書いています。
この記事でわかること
- 『自己演出力』のグッときたところベスト3
- 概要、目次
- 口コミ、動画
本記事を書いている私は、中谷彰宏 歴:22年8ヶ月です。
中谷彰宏さんの書籍はすべて読んでいます。
本記事は「自己演出力」の読書感想・書評です。
この記事を読むことで、自己演出の方法、自分の輝かせ方がわかります。
セルフプロデュースのヒントが得られます。
Contents
自己演出とは相手を輝かせる他者演出『自己演出力』グッときたところベスト3

グッときたところベスト3
- 1位:自分の欲より、友達を優先にする人が浮かび上がる
- 2位:目立つことをするより、共感力を持つ
- 3位:演出は準備が勝負
1位:自分の欲より、友達を優先にする人が浮かび上がる
重要なことは3つ
- 出しゃばらない
- ストイック
- 気配りする
① 出しゃばらない
つい出しゃばりたくなります。
認めて欲しいからです。
人間は誰しも承認欲求があります。
人から認められれば嬉しいのは当然。
嬉しくないはずがありません。
認めて欲しいがために、気づかないうちに自分を盛ったりしがちです。
そんな人は輝きません。
「自分が、自分が」と色を出すほど、色は出ないのです。
「自分の色を消す。なんの色もない状態」で初めて個性は出ることを知りました。
② ストイック
自分の欲望を抑えて、ストイックであること。
いかに下記の気持ちをを抑えるかが重要です。
- 自慢したい気持ち
- 見せびらかしたい気持ち
- 分かって欲しい気持ち
他人を立てることにつながります。
最初にやることは他人を輝かせること。
他人を輝かせられる人は、それだけ目立ちます。
誰もそんなことをやりたがらないからです。
自分の利益を先に取ろうとする人が大半です。
自分が損をしても、他人に利益を取らせることはなかなかできることではありません。
③ 気配りする
他者に気配りできることが「自己演出力」につながります。
気配りは自分の欲を抑えないとできないからです。
見習い添乗員のころ、先輩に「気を使えるようになりなさい」と言われました。
今でも心に残っている言葉です。
自分がどれだけできているか疑問です。
- 人を立てる
- 人を褒める
- 人が気持ち良くなるように行動する
ハッキリと言えることは「自分の色を消していこう」です。
2位:目立つことをするより、共感力を持つ
究極の演出は「何もしていないように見える」です。
ブログに応用できます
- 大げさな文章を削る
- 大げさなボタンを削る
大げさな文章を削る
- 非常に
- 大変
- 大至急
- 絶対
- 必ず
使ってしまいがちですが、なくても意味が変わらなければ消します。
大きなボタンを削る
トップページに使っていた「大きなボタン」もすべて消して、テキストリンクにしました。
上記2つを心がけることで、ブログがスッキリします。
自分ファーストより読者ファーストです。
自分を消し、読者の使いやすさの追求が自己演出力です。
むやみやたらに商品をおすすめしても成約しません。
読者を立たせることが最優先です。
3位:演出は準備が勝負
演出は「どれだけ準備をコツコツしているか」です。
添乗前に下見をしていました。
下見をしたことは、お客さまに言わないようにしていました。
聞かれたら言いました。
今振り返ると「聞かれても言わないほうが良かったかな」と感じます。
言った瞬間に「こんなに頑張っているんだ」と押し付けがましくなるからです。
「聞かれても言わないほうがいいこともある」ことを学びました。
下見に行ったことは、説得力を持たせるために「証拠として話す」のなら良いのです。
言った瞬間に自慢になることは言わない。
それだけで十分な自己演出になるのです。
自己演出の意味は、他人を輝かせること
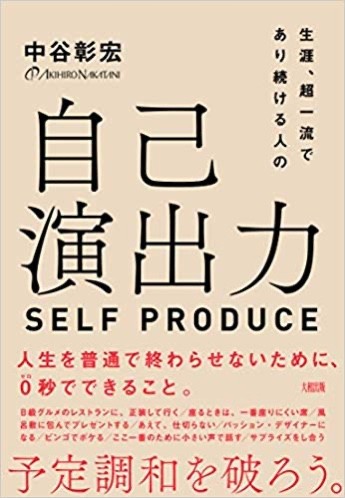
他人を良く見せることが、自己演出につながる
動機は不純です。
「自己演出=自分を良く見せる方法」と思っていたからです。
自分を少しでも良く見せたかったのです。
この考えでは自分を良く見せることができません。
自分ではなく、他人を良く見せることが、結果として自分に返ってくるからです。
作用・反作用の法則です。
覚えてもらえない人におすすめ
こんな方におすすめ
- 「盛ること」に、疲れた人
- 印象が薄く、覚えてもらえない人
- 自分の何を際立たせればいいか、わからない人
下記3人にはおすすめできません。
- 目立ちたい人
- 普通の人生でいい人
- 他人を蹴落として成功したい人
7つの章の目次、書籍情報
目次
第1章.”一瞬”で「感じがいい」と思われる。
第2章.大事な場面で、その場の”空気”を支配する。
第3章.”仕込み”を用意し、サプライズを仕掛ける。
第4章.誰とでも”共犯関係”を築いて、面白さをつくる。
第5章.写真1枚、挨拶ひと言で、”100すべて”を語る。
第6章.”どこか1か所”を崩して、非日常のリズムにする。
第7章.相手を楽しませる前に、”どう楽しむか”を工夫する。
| 書名 | 『自己演出力』 |
|---|---|
| 著者 | 中谷彰宏(» プロフィール:公式サイト) |
| 単行本 | 208ページ |
| 出版社 | 大和出版 |
| 発売日 | 2019/12/4 |
口コミ6個、動画3本
Amazonの口コミ3個
- 演出=プロデュースは自分のためではなく、人を幸せにするためにする。さまざまな思考や行動の目的が明確になりモヤモヤがなくなる
- 今回は「パンチ不足」という印象
- 相手意識ではなく、自分の内側に焦点を当てる本。読みやすいです
Twitterの口コミ3個
- 気配りができる事が、自己演出力
- 些細なことを気づき、工夫していくことが一流の道。今までは何とか一発逆転をしようと思ってた
- 演出は、自分のためではなく人を幸せにするサービス精神である
解説動画3本
まとめ:『自己演出力』とは、自分を消すことで相手が輝くこと

相手を輝かせることで、自分が輝きます。
本書のすべてです。
本書は自己演出のための「小さな工夫」が58の具体例で書かれています。
すべての具体例は「相手を輝かせる」ためのものです。
以上です。
P.S. 自分を消すことで相手が輝きます。
関連記事【書評】『1分で伝える力』伝わるコツはたった1%を丁寧に語ること
関連記事中谷彰宏おすすめ本17選まとめ【文章4冊+成功5冊+ヒント8冊】