もう3月なのに、まだ寒い…。
春らしい時候の挨拶って、どう書けばいいんだろう?
3月上旬にふさわしい時候の挨拶を知り、自然で好印象を与える表現を使いこなしたい。
この記事でわかること
- 3月上旬の気候や季節感の特徴
- 適切な時候の挨拶の選び方(ビジネス・フォーマル・カジュアル別)
- 避けるべき表現とその理由
- 相手に失礼のない表現のポイント
- 文章の締めくくりで印象を良くする方法
3月上旬は暦の上では春ですが、実際には寒暖差が大きく、地域によって気候も異なります。
「春爛漫」「桜満開」と書いてしまうと、まだ寒い地域の人には違和感を与えてしまうかもしれません。
かといって、冬の挨拶では春らしさが感じられず、何となく味気ない…。
ビジネスメールや手紙、カジュアルなメッセージでも、相手に合わせた適切な表現を選ぶことが大切です。
3月上旬ならではの時候の挨拶をマスターすれば、より自然で好印象なやり取りができます。
本記事では、3月上旬にぴったりの時候の挨拶をシーン別に紹介します。
3月上旬の時候の挨拶とは

「もう3月なのに、まだ寒い…」そんなふうに感じたことはありませんか?
3月上旬は、暦の上では春ですが、実際の気候はまだ冬の名残を感じることが多い時期です。
日本では、手紙やメールで季節の移り変わりを表現する文化が根付いています。
しかし、春らしさを強調しすぎると、寒さの厳しい地域では違和感を与えてしまうことも。
適切なフレーズを選び、相手に心地よく伝わる挨拶を考えましょう。
3月上旬の気候や季節感の特徴
「3月なのに、まだコートが手放せない…」
そんな日が続くのが、3月上旬の特徴です。
日中は暖かくなる日もありますが、朝晩は冷え込むため、寒暖差が大きい時期です。
梅の花が咲き始める地域もありますが、桜にはまだ早く、春本番とは言えません。
時候の挨拶では「春の訪れを感じさせる言葉」と「寒さに配慮した表現」をバランスよく使うことが大切です。
たとえば「日差しが春めいてきましたが、まだ肌寒い日が続きますね」などの表現が適しています。
春の訪れを感じるフレーズとは
3月上旬の挨拶では、冬から春へと移り変わる様子を表現すると自然な印象になります。
たとえば、次のフレーズが適しています。
- フォーマルな表現(ビジネス・かしこまった場面)
「余寒なお厳しき折ですが、いかがお過ごしでしょうか」
「春寒の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます」 - カジュアルな表現(親しい相手やカジュアルな手紙)
「日差しが少しずつ春めいてきましたね」
「梅の花が咲き始め、春の訪れを感じる季節になりました」
ビジネスでは「春寒」「余寒」などの堅めの表現を使うと失礼がなく、洗練された印象を与えます。
一方、親しい間柄では「春めいてきた」「梅の花が咲いた」という表現を入れると、温かみのある挨拶になります。
言葉選びのポイント
- ビジネス向け:「春寒」「余寒」など、堅めの表現が無難
- カジュアル向け:具体的な季節の変化を入れると親しみやすい
- 迷ったら:「春の訪れを感じる今日この頃」といったニュートラルな表現もOK
使うとNGな表現に注意
時候の挨拶で春らしさを強調しすぎると、違和感を与えることがあります。
たとえば、こんなフレーズには注意です。
避けるべき表現の例
- 「春爛漫の季節となりました」
- 「桜が満開となり、心躍る季節です」
- 「花冷えの日が続きますが、お元気ですか」
「春爛漫」は春本番を表す言葉で、3月上旬には早すぎます。
また「桜が満開」という表現も、地域によっては4月にならないと当てはまらない場合が多いため注意です。
さらに「花冷え」は桜が咲く時期に使う言葉なので、3月上旬では避けたほうがよいです。
適切な表現を選ぶコツ
- 地域差を考える:「桜が満開」は地域によって時期が異なるため、慎重に
- 気温の現実を意識する:「春爛漫」ではなく「春の気配を感じる」くらいが適切
- 迷ったときは?:「余寒」「春寒」といった無難な表現を選ぶ
たとえば、3月上旬の東京と札幌では、気温や景色が異なります。
全国の読者を意識するなら「春の訪れを感じる今日この頃」という表現を使うと無難です。
時候の挨拶は、相手への気遣いを示す大切な要素です。
適切な言葉を選び、自然な形で季節の移り変わりを伝えましょう。
3月上旬の時候の挨拶【文例集】

3月上旬、寒いと思ったら急に暖かくなったり、着るものに迷うことはありませんか?
この時期はまさに冬から春への変わり目。手紙やメールの挨拶でも、冬の余韻を残しながら春を感じさせる表現が求められます。
とはいえ「春爛漫」や「桜満開」といった言葉をうっかり使うと「3月上旬にそれは早いのでは?」と思われることも。
そこで今回は、ビジネスメールやフォーマルな手紙、カジュアルなメッセージで使える時候の挨拶を紹介します。
ビジネスメールで使える時候の挨拶
仕事のメールを書くとき、時候の挨拶に迷った経験はありませんか?
ビジネスメールでは、適切な季節感を保ちつつ、簡潔で礼儀正しい表現を選ぶことが大切です。
3月上旬はまだ寒さが続くため「余寒」や「春寒」といった言葉を使うのが無難です。
春の訪れを感じさせつつ、相手の健康を気遣う一文を添えると、より印象が良いです。
文例
- 一般的なビジネスメール
「余寒なお厳しい折、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます」
「春寒の候、貴社におかれましては益々ご清祥のことと存じます」 - 取引先や目上の方へのメール
「日差しが春めいてまいりましたが、まだ肌寒い日が続いております。貴社のみなさまにおかれましては、ご健勝のことと存じます」
「三寒四温の時節、貴社におかれましては、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます」 - お礼やお願いの際のメール
「春の訪れを感じる今日この頃、貴社ますますのご発展をお祈り申し上げます」
「寒さも和らぎつつありますが、まだ肌寒い日が続いております。どうぞご自愛くださいませ」
ポイント
- 季節の変わり目に合わせた表現を選ぶと、自然な印象になる
- 迷ったときは「余寒」「春寒」などの無難なフレーズを活用する
手紙や書面でのフォーマルな表現
フォーマルな手紙では、格式のある表現を使うことで、より礼儀正しい印象を与えます。
特に、公的な文書や目上の方への手紙では、文語調の表現を意識しましょう。
文例
- 一般的なフォーマルな挨拶
「余寒厳しき折、みなさまにはお変わりなくお過ごしのことと存じます」
「春寒の候、貴殿には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます」 - お祝いの手紙
「桃の節句も過ぎ、春の訪れを感じる頃となりました。みなさまにはお変わりなくお過ごしのことと存じます」
「早春の候、○○様におかれましてはますますご健勝のことと拝察いたします」 - 弔辞やお見舞いの手紙
「三寒四温の時節、寒暖差の激しい日が続いております。くれぐれもご自愛くださいますよう、お祈り申し上げます」
「春浅き折、体調を崩しやすい時期でもございます。どうかご自愛くださいませ」
ポイント
- 相手の立場に応じて、適切な敬語や表現を選ぶ
- 形式を意識しながらも、温かみのある言葉を添えると好印象
カジュアルな場面での使い方
「3月に入ったのに、まだ寒いね」そんな会話が増えるのがこの時期です。
友人や家族とのやりとりでは、かしこまりすぎず、季節の変化を感じさせる表現を取り入れるとよいです。
文例
- 親しい人への手紙やメッセージ
「梅の花が咲き始め、春の訪れを感じる頃ですね」
「日中は少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は冷えますね」 - メールやLINEで使えるフレーズ
「少しずつ春めいてきましたね。そろそろお花見の計画を立てようかな」
「三寒四温の季節だけれど、体調は崩していませんか?」 - 近況報告を兼ねたメッセージ
「日差しが春らしくなってきましたね。そろそろ春服を準備しようかなと思っています」
「3月に入ったけれど、まだ寒い日が続いてるね。暖かくなったら一緒に出かけよう!」
ポイント
- 具体的な話題を交えると、自然なコミュニケーションにつながる
- 季節の移り変わりを感じさせる表現を取り入れると、温かみが増す
3月上旬の時候の挨拶の書き方とポイント

3月に入ったのに、まだ寒いな…そんな日が続くのが3月上旬です。
日差しは少しずつ春らしくなってきますが、朝晩は冷え込むことが多く、地域によってはまだ冬のような気候のところもあります。
こんな時期に手紙やメールの時候の挨拶を書くとき「春の表現を入れたいけれど、まだ早い?」と迷うことはありませんか?
特にビジネスメールでは、相手の地域の気候を考えた適切な表現を選ぶことが大切です。
ここでは、3月上旬の時候の挨拶をスムーズに書くためのポイントや、失礼のない表現の選び方を紹介します。
相手に失礼のない表現を選ぶコツ
「春らしい挨拶をしたい」と思って書いた言葉が、実は相手には違和感のある表現だった…そんな経験はありませんか?
たとえば「暖かい日が続いていますね」と書いたものの、相手の地域ではまだ雪が降っていた、なんてこともありえます。
時候の挨拶の正しい使い分け
- 「余寒」と「春寒」の違い
余寒:立春(2月4日頃)を過ぎても残る冬の寒さを表す(例:「余寒なお厳しい折」)
春寒:春になった後も寒さが続くことを指す(例:「春寒の候」) - 避けたほうがよい表現と理由
「春爛漫」→ 春本番の表現なので3月上旬には早い
「桜満開」→ 桜の見頃は3月下旬から4月が多いため不自然
「暖かい日が続いていますね」→ 地域によってはまだ寒いため注意
適切な表現の選び方
- ビジネス・フォーマルな場合
「余寒なお厳しい折、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます」
「春寒の候、貴殿には益々ご清祥のことと存じます」 - カジュアルな場合
「日差しが少しずつ春めいてきましたね」
「梅の花が咲き始め、春の訪れを感じる季節になりました」
相手の地域の気候を考えた表現を選ぶことで、より自然な挨拶になります。
季節の移り変わりを自然に表現する方法
時候の挨拶では「春が来ました!」と一気に変化を表すより、冬の名残と春の兆しをバランスよく伝える方が自然です。
自然な季節感を表すフレーズ
- 冬の余韻を残す表現
「余寒厳しき折、みなさまにはお変わりなくお過ごしのことと存じます」
「まだ朝晩は冷え込みますが、いかがお過ごしでしょうか」 - 春の気配を感じる表現
「日差しが少しずつ春めいてまいりました」
「梅の花がほころび、春の訪れを感じる季節となりました」 - 寒暖差に配慮した表現
「三寒四温の季節、寒暖差が大きい日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか」
「寒さも和らぎつつありますが、まだ肌寒い日もありますので、ご自愛ください」
誤った使い方の例
- 「桜が満開の季節となりました」→ 3月上旬では時期が合わない
- 「春本番の暖かさですね」→ まだ寒さが続く地域もあるため適切でない
読者が実際に使いやすいように、具体的な言葉の使い分けを意識しましょう。
結びの言葉で印象を良くするテクニック
時候の挨拶の後に続く結びの言葉は、好印象を与える大切な要素です。
特にビジネスでは、丁寧な印象を残すことが重要になります。
結びの言葉の例
- ビジネス・フォーマルな場合
「季節の変わり目、どうかご自愛のほどお願い申し上げます」
「春の訪れを迎えつつある今日この頃、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます」 - 親しい相手への場合
「まだ肌寒い日が続きますので、お身体を大切にお過ごしください」
「暖かくなったら、一緒にお花見でもしましょう」
結びの言葉を選ぶコツ
- ビジネスでは丁寧な表現を使う:「ご自愛ください」などのフレーズが無
- 親しい相手には自然な言葉を選ぶ:次に会う予定などを交えると会話が広がる
相手に合わせた結びの言葉を選ぶことで、文章の印象がより良くなります。
3月上旬の時候の挨拶で、よくある質問

3月上旬の時候の挨拶、やわらかく伝えるには?
3月上旬の時候の挨拶、ちょっと迷いますよね。
やわらかい印象を与えたいなら「春の気配を感じる今日この頃ですね」や「梅の花がほころび始めました」などが使いやすいです。
親しい相手には「少しずつ春めいてきましたね」とすると、より温かみのある表現になります。
»【3月の時候の挨拶】やわらかい表現のコツ+シーン別の例文3選
3月の時候の挨拶、どんなフレーズを使えばいい?
「春寒の候」「三寒四温の時期ですね」などが3月らしい挨拶です。
ただし「桜満開の候」は3月上旬には時期が早すぎるため、避けたほうがよいです。
相手の地域によって寒暖差があるため「寒暖差が大きい日が続きますね」といった言葉を添えるのもおすすめです。
»【3月の手紙に迷ったら】すぐに使える時候の挨拶&結びの例文まとめ
卒業式の挨拶に3月上旬の時候の挨拶を使ってもいい?
使えます。
卒業式なら「春の訪れとともに、新たな門出を迎えられたことをお祝い申し上げます」や「寒さも和らぎ、卒業の季節となりました」などが適した表現です。
「未来へ向かう素晴らしい季節ですね」といった前向きな言葉を添えると、より印象的な挨拶になります。
»【3月の挨拶まとめ】時候・ビジネス・送別会ですぐに使える例文つき
学校向けに使いやすい3月の時候の挨拶は?
学校向けの時候の挨拶には「桜のつぼみが膨らみ始める季節となりました」「春の訪れとともに、新たな学びの季節が近づいています」などが適しています。
卒業や進級を意識した表現を取り入れると、より自然な印象になります。
3月の美しい季語にはどんなものがありますか?
3月の美しい季語には「桃の節句」「春霞」「梅の香」「三寒四温」などがあります。
「春霞」は、春の訪れをやわらかく表現するのに適した言葉で、手紙やスピーチの挨拶としても使いやすいです。
»【卒業・新生活】3月の挨拶に使いたい季語と例文【心に響く言葉】
まとめ:3月上旬の時候の挨拶を正しく使おう
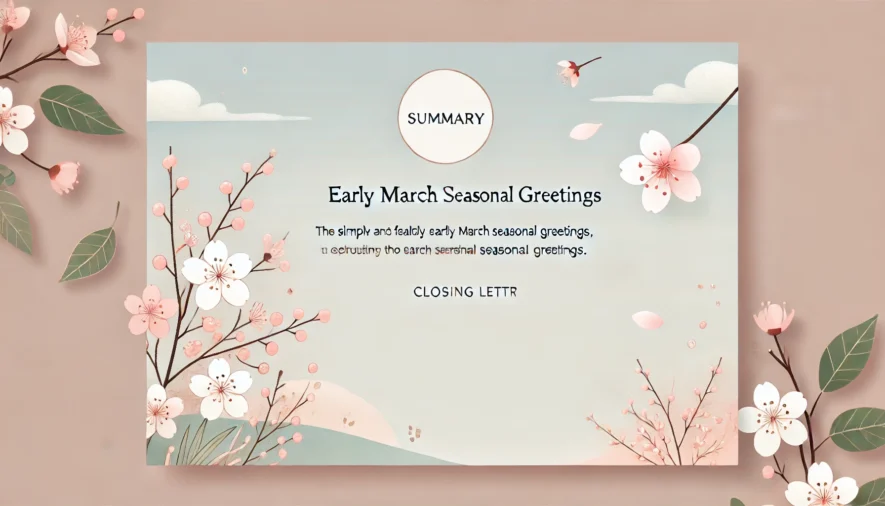
3月上旬の時候の挨拶は、春の訪れを感じさせつつ、寒さへの配慮も必要です。
適切なフレーズを選ぶことで、相手に心地よい印象を与えられます。
要点まとめ
- 3月上旬の気候の特徴:朝晩の冷え込みがあり、桜の見頃には早い時期
- 適切な挨拶の選び方:春の訪れを表しつつ、寒さへの気遣いを忘れない
- ビジネス・フォーマルな表現:「余寒」「春寒」を用いると自然な印象に
- カジュアルな挨拶:「日差しが春めいてきましたね」など温かみのある言葉を
- 避けるべき表現:「桜満開」「春爛漫」など、時期にそぐわない表現はNG
- 結びの言葉:相手の健康を気遣う一言を添えると、より印象が良くなる
季節の変わり目は、相手の状況に配慮した表現が重要です。
この記事を参考に、手紙やメールの時候の挨拶を見直してみてください。
以上です。
P.S.適切な言葉を選ぶことで、円滑なコミュニケーションにつながります。
関連記事【3月上旬の挨拶で差をつける】季節感を簡単に伝える方法+注意点
関連記事【3月の挨拶】カジュアルに使える例文3選+季節感を加えたフレーズ
