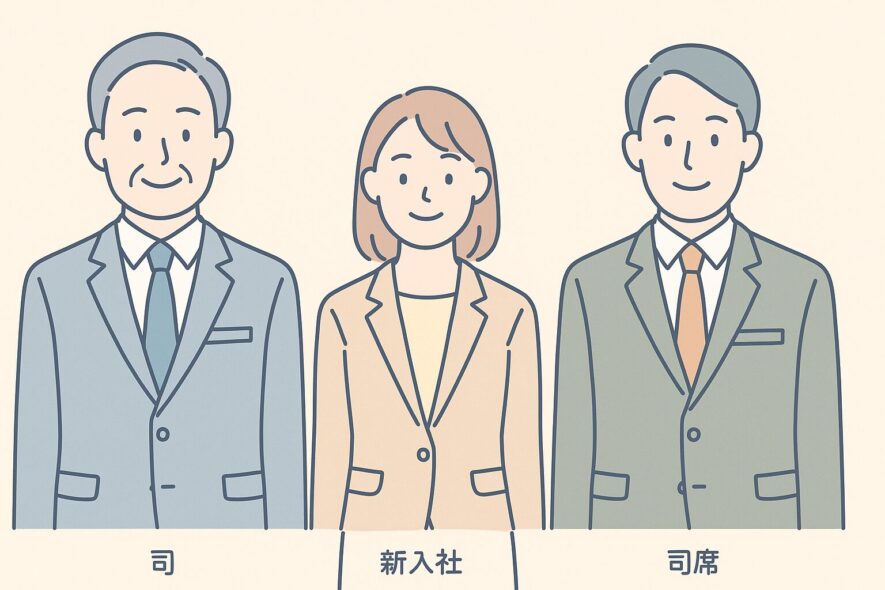- 「歓迎会の挨拶順番って誰から頼めばいいんだろう、間違えたら気まずいな」
- 「司会や幹事をまかされたけれど、ちゃんと進行できるか心配だ」
- 「失礼なく、みんなが安心できる流れにしたいけど、段取りがよくわからない」
この記事でわかること
- 歓迎会における挨拶の基本的な順番(司会→主催者→上司→新入社員→締め)
- 役割別(司会・幹事・上司・新入社員・主賓)の挨拶順番の実例と注意点
- 人数や会場規模による挨拶スタイルの違いと工夫
- 当日に失敗しないための進行のコツ
- 歓送迎会シーンごとの挨拶例文や、異動挨拶のタイミング
- 「歓迎会の異動挨拶」でよくある悩みと解決策
歓迎会の挨拶順番、誰から話すべきか迷っていませんか?
司会や幹事をまかされて、順番や進行に不安を感じる人も多いです。
たとえば、上司より先に新入社員が話してしまうと、場の空気が気まずくなってしまうこともあります。
この記事では、歓迎会の挨拶における基本の順番、役割別の流れ、当日に失敗しないコツまで丁寧にまとめました。
順番や段取りを押さえるだけで、進行に自信が持て、参加者全員が心地よく過ごせる会をつくれます。
Contents
歓迎会の挨拶は順番が命

歓迎会では、挨拶の順番が会の雰囲気を決める大きな要素になります。
たとえば、上司より先に新入社員が話してしまうと、会場の空気が一瞬ざわつくかもしれません。
誰にとっても心地よい場にするには、基本の流れを押さえることが大切です。
段取りに自信があれば、安心して進行をまかせられます。
この章では、歓迎会で失礼のない挨拶順をわかりやすく紹介します。
なぜ順番が重要なのか
挨拶の順番は、その場にいる人すべてへの配慮を形にするものです。
順番を守ることは単なるマナーではなく、職場の空気を穏やかに整える効果もあります。
たとえば、自分の前に上司の挨拶があると、話しやすくなると感じたことはないでしょうか。
話す順に気を配るだけで、その場にいる人たちの気持ちがほぐれ、信頼関係も育まれていきます。
基本の挨拶の流れとは
歓迎会の基本的な流れは「司会→主催者→上司→新入社員→締め挨拶」が基本です。
たとえば、司会が「本日はお集まりいただきありがとうございます」と会を始め、主催者が歓迎の言葉を述べます。
その後、上司からの激励、新入社員の自己紹介と続くことで、会の雰囲気が徐々に温まっていきます。
締めの挨拶では「これから一緒に頑張っていきましょう」と、会を気持ちよく締めくくるのが理想です。
立場別の一般的な順番ルール
誰がいつ話すかという順番には、自然と場の空気を整える力があります。
一般的には、役職の高い人から順に挨拶をすることで、場に一貫性が生まれます。
たとえば、部長→課長→新入社員という流れが定着しているのは、そのほうが聞く側も安心できるからです。
新入社員も、自分の順番が後だとわかっていれば、心の準備ができて落ち着いて話せます。
誰もが気持ちよく話せる順番があることで、会全体がスムーズに進行します。
役割別に見る挨拶の順番例
歓迎会では、誰がどのタイミングで話すかによって、場の印象が変わります。
たとえば、新入社員がいきなり挨拶を始めてしまうと「えっ、先に上司じゃなかった?」と場がざわつくこともあります。
役割ごとの順番を事前に知っておくだけで、安心して進行できます。
この章では、司会・幹事・上司・新入社員・主賓それぞれの立場で、よくある順番例を紹介します。
司会・幹事の段取り
会の雰囲気を左右するのが、司会と幹事です。
たとえば、開会の挨拶がぎこちないと、場の空気が固まってしまうこともあります。
司会は、進行役として会全体を見渡しながら、自然な流れをつくることが求められます。
幹事は、裏方としてマイクの準備や挨拶の順番確認、声かけなど細かな配慮が大切です。
ふたりで役割を分担し、アイコンタクトを取りながら動くと、安心感のある進行になります。
上司・新入社員・主賓の順番
順番を整えることで、挨拶に込めた気持ちがより伝わります。
上司の言葉が先にあることで、新入社員はその言葉を受けて話すことができ、安心感が生まれます。
主賓がいる場合は、あえて最後に挨拶をお願いすることで、会全体を締める役割を担ってもらうのが一般的です。
「最後にご挨拶を」と司会からお願いすれば、自然な流れで主賓の存在が引き立ちます。
こうした順番の工夫は、単なるルールではなく、会への気持ちを形にする大切な手段です。
人数や会場規模による違い
小さな会と大規模な会では、進行のスタイルも変わります。
たとえば、居酒屋の半個室で開く8人程度の会なら、座った順に挨拶するだけで自然な流れが生まれます。
一方で、30人を超える職場全体の歓迎会では、司会がタイムキーパーとなり、順番どおりに挨拶を進める必要があります。
「誰がいつ話すのか」が見えていることで、参加者も安心してその場に集中できます。
規模に合わせた工夫が、歓迎される側にとっても印象に残るひとときをつくります。
当日の進行で失敗しないコツ

歓迎会の当日は、思わぬアクシデントが起こることもあります。
たとえば、話す順番を忘れていたり、急に指名された人が慌てたり。
ちょっとした準備や工夫があれば安心です。
この章では「こうしておけばよかった」とならないための、進行のコツを紹介します。
声かけや指名のタイミング
「いきなりマイクを渡されて焦った」——そんな経験がある人も多いかもしれません。
挨拶をお願いする人には、開始前に「そろそろお願いしますね」とひと言添えておきましょう。
当日は、話す前のタイミングで軽くアイコンタクトやうなずきで合図を送るだけでも、相手は準備しやすくなります。
ちょっとした気づかいが、場の緊張を和らげ、進行をスムーズにしてくれます。
緊張をほぐす小ワザと配慮
挨拶の場は、話す人も聞く人も固くなりがちです。
たとえば「○○さん、あまり気負わず、一言だけでも大丈夫です」と司会が軽く声をかけると、相手も安心します。
話す前に「今日は天気がいいですね」といった一言を添えるだけでも、場がほぐれます。
また、聞き手のうなずきや笑顔も、話す側にとって大きな支えになります。
誰かのひと工夫が、会全体の空気をやさしく変えてくれます。
挨拶後の進行(乾杯・歓談など)
「えっと…次、何するんだっけ?」とならないように、挨拶のあとは流れを自然につなげましょう。
たとえば「乾杯のご発声を◯◯部長にお願いいたします」と続けるとスムーズです。
歓談タイムには、会話が途切れないように「お名前ビンゴ」などの軽い仕掛けを用意しても盛り上がります。
最後の締めは、司会が空気を見ながらタイミングよく声をかけると、自然に終わりに向かえます。
進行がうまくいくと「いい会だったね」と言われる満足感が残ります。
歓迎会の挨拶の順番で、よくある質問
歓送迎会の挨拶で順番が複数ある場合、どう決めればよいですか?
基本は立場の上の人から順に話すのが一般的です。
たとえば、送別者が複数いる場合は年次や役職順にし、同じ立場であれば所属部署ごとに順番を決めるとスムーズです。
事前に調整しておくと安心です。
歓送迎会の挨拶に使える例文はありますか?
あります。
たとえば「本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます」と始め、歓迎や感謝の気持ちを伝えると好印象です。
形式にとらわれず、素直な言葉で大丈夫です。
»【歓迎会の挨拶例文3選】失敗しない話し方のコツ+よくあるNG例
歓送迎会での課長の挨拶にふさわしい例文は?
課長としての挨拶は、簡潔かつ温かみのある言葉が理想です。
「これからの活躍を期待しています」「これまでの貢献に感謝します」といったフレーズがよく使われます。
部署全体を代表する気持ちで伝えることが大切です。
»【歓迎会の上司挨拶】短く心に残る例文3選+失敗しないコツまとめ
歓迎会の挨拶を面白くするにはどうすればよいですか?
無理に笑いを取ろうとせず、自分らしい話題を取り入れるのがコツです。
たとえば、趣味の話やちょっとした失敗談を交えると親しみやすくなります。
雰囲気を和ませたいときにおすすめです。
»【歓迎会の挨拶】シーン別の面白い例文3選【ムリに笑わせなくてOK】
異動の挨拶は歓送迎会でどのタイミングで話すべきですか?
異動の挨拶は送別者として、後半の落ち着いたタイミングに行うのが一般的です。
上司や代表者の挨拶のあとに、本人から感謝の気持ちを述べると自然な流れになります。
まとめ:安心して迎えるために

歓迎会の挨拶順番に悩んでいるなら、基本ルールと進行のコツを押さえるだけで解決できます。
誰にとっても心地よい場をつくるために、挨拶順やマナーを理解しておきましょう。
ポイント
- 歓迎会の基本的な挨拶順は「司会→主催者→上司→新入社員→締め」
- 役職別・役割別に自然な流れを意識することが大切
- 小規模・大規模によって挨拶スタイルを柔軟に変える
- 声かけやアイコンタクトで当日の進行をスムーズにする
- 緊張をほぐす配慮と、自然な歓談へのつなぎ方を意識する
歓迎会の挨拶は、単なる儀式ではなく、新たな関係づくりのきっかけになる大切な場面です。
順番や段取りに気を配るだけで、参加者全員が安心してその場を楽しめます。
事前の声かけや、当日の進行におけるちょっとした配慮が、会の流れをなめらかにし、印象も変わります。
また、場の空気を読む力や、参加者への敬意を形にすることも、挨拶の進行をまかされた人にとっては重要なスキルです。
基本の順番や進行のコツを押さえておけば、初めての司会でも安心です。
誰もが気持ちよくその場を共有できるよう、事前準備と丁寧な進行で、温かい歓迎会をつくっていきましょう。
以上です。
P.S. 段取りの確認だけで、当日の負担が減ります。
関連記事【転職後の歓迎会挨拶】中途入社で好かれる自己紹介の例文3選まとめ
関連記事歓迎会の挨拶に自信がない新入社員向け【不安が消える例文3選+コツ】