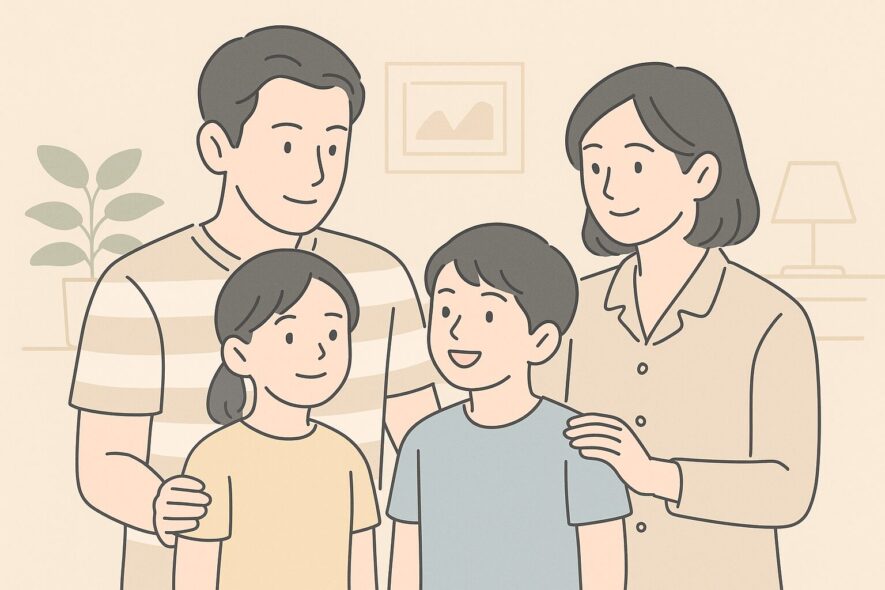- 家族にちゃんと気持ちが伝わる暑中見舞いを書きたい
- 親や親戚にどんな言葉を選べばいいのか、毎年迷ってしまう
- 形式だけじゃなく、自分の言葉で伝えたいけれど、例文がないと不安
この記事でわかること
- 暑中見舞いの正しい時期や文面の構成ルール
- 家族、親戚、子どもなど相手別文例と表現のコツ
- 避けるべき表現、はがき選び、手書きの一言などの実践マナー
- 気持ちが伝わる言葉の選び方と、自然な近況報告の組み込み方
- 投函前のチェックリストまでを含む、送る際の全体的な流れ
- よくある質問
暑中見舞いを家族に送るとき、マナーや形式にとらわれすぎて「気持ち」が伝わりにくくなることがあります。
大切なのは「相手を思う言葉」を「自分らしい文章」で届けることです。
本記事では、送る時期や構成の基本から、親・子ども・親戚など相手別の文例、避けたい表現、手書きの工夫までを解説します。
自分らしい言葉で感謝や思いやりを伝えることで、暑中見舞いが家族との距離を近づける「夏の手紙」に変わります。
丁寧すぎず、日常の延長線上にある自然な文章で心を届けましょう。
Contents
家族向け暑中見舞いの基本マナー

家族に暑中見舞いを送るときは、礼儀よりも気持ちを届けることが大切です。
基本的なマナーを知っておくと、丁寧な印象を与えられます。
暑さを気づかう言葉に、思いやりや安心を込めて届ける工夫が必要です。
送る時期や文面の構成、避けるべき表現などを具体的に紹介します。
暑中見舞いを送る正しい時期とは
暑中見舞いを送るのは、梅雨明けから立秋の前日までが目安です。
この時期は、例年7月15日頃から8月7日頃にあたります。
理由は、暑中見舞いが「暑さを気づかう挨拶」だからです。
たとえば関東では、梅雨が明けると本格的な夏が始まります。
この時期に届けば、季節の気遣いが伝わります。
文頭・文中・結びの基本構成
暑中見舞いは「あいさつ・近況・気遣い・結び」の順で構成すると書きやすくなります。
- 文頭に「暑中お見舞い申し上げます」と入れましょう
- そのあと「私たちは元気に過ごしています」など家族の様子を書きます
- 次に「暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛ください」といった気遣いの言葉を入れます
- 最後に「令和○年 盛夏」と記して締めくくると形式的にも整います
避けるべき表現・マナー注意点
暑中見舞いには、明るく前向きな雰囲気が求められます。
以下の表現は避けたほうが安心です。
- 「毎日ぐったり」「倒れそう」などネガティブな体調表現
- 病気や不幸に関する話題
- 家庭の詳細な事情や金銭面などの話
気を使わせないよう、心地よく読める文面を意識しましょう。
家族向け文例3選と書き方ポイント
暑中見舞いは、ふだん言えない気持ちを伝える機会です。
形式だけにとらわれず、家族の関係に合った表現を使うと、温かく伝わります。
一般的な文例に加えて、親や子どもなど相手別に使いやすい言葉を紹介します。
1.一般家族向けの文例
ふだん一緒に過ごす家族でも、少し気持ちを形にして伝えるだけで、関係が深まります。
暑中見舞いは、日々の感謝やいたわりの気持ちを自然に伝える機会です。
以下に、家族向けとして無理なく使える文例をまとめました。
- 暑中お見舞い申し上げます。
毎日暑い日が続いていますが、みなさんお元気でしょうか。 - こちらは変わらず元気に過ごしています。
家族みんなで、夏の思い出を作っています。 - まだまだ暑さが続きますので、どうか体に気をつけてお過ごしください。
季節感のある言葉を入れると、印象がやわらぎます。
2.親・親戚向けに使えるテンプレート
親や親戚に送る暑中見舞いでは、少し丁寧な言葉づかいが求められます。
あまり堅苦しくせず、温かみのある雰囲気を大切にしましょう。
下記の文例は、そのままでも使えます。
家庭の事情に合わせてアレンジできます。
- 暑中お見舞い申し上げます。
お変わりなくお過ごしのことと存じます。 - 私たちは家族そろって元気に過ごしております。
おかげさまで子どもたちも夏休みを満喫しています。 - 暑さの折、どうぞご自愛くださいませ。
丁寧さと親しさのバランスを意識すると、印象がやわらかくなります。
3.子ども・孫宛てに使う暖かい表現
子どもや孫に送る暑中見舞いでは、言葉のやわらかさや励ましが大切です。
目に浮かぶような語りかけの表現を使うと、距離が近づきます。
短くても気持ちがこもっていれば、記憶に残ります。
- 暑中お見舞い申し上げます。
夏休み、元気に楽しくすごしていますか。 - おじいちゃんとおばあちゃんは、ふたりとも元気です。
かき氷を食べながら、君の話をしています。 - また会えるのを楽しみにしています。
暑さに気をつけて、元気に過ごしてね。
やさしい言葉で、安心や楽しさを届けましょう。
»【子ども向けの暑中見舞い例文3選】夏の宿題に役立つ書き方ガイド
アレンジ自由、自分の家族らしい文章

定型文だけでは伝わらない温かさが、家族宛ての暑中見舞いには求められます。
ふだんの様子や感謝を自然に表すことで、距離を縮め、安心感を届けられます。
自分の家族らしさを大切にするための表現や工夫を紹介します。
近況報告を自然に組み込むコツ
近況を伝えるときは、話し言葉に近い自然な表現がポイントです。
相手の様子を気づかいながら、日常を短くまとめて伝えましょう。
たとえば「みんな元気にしています」「子どもたちは夏休みに入って毎日走り回っています」など、季節感や生活のリズムが伝わる表現が効果的です。
かしこまりすぎず、あいさつの一部としてさらりと書くと、押しつけがましさがなくなります。
「おかげさまで」「元気にしています」などの言い回しをうまく使いましょう。
感謝や思いやりを伝えるフレーズ集
日ごろ言葉にできない気持ちは、暑中見舞いに込めて伝えるチャンスです。
感謝や思いやりを伝えるフレーズは、少しだけ意識して選ぶことで、伝わり方が変わります。
以下の表現は、暑中見舞いにぴったりです。
- いつも気にかけてくださり、ありがとうございます。
- おかげさまで、心穏やかに過ごせています。
- この夏も元気でいてくださることを願っています。
- また顔を見られる日を楽しみにしています。
丁寧すぎず、やさしい語調を心がけると気持ちが伝わります。
手書きで一筆添える時の心がけ
印刷されたはがきでも、手書きでひと言添えるだけで印象が変わります。
文面の最後や空いたスペースに、短いメッセージを加えると温かみが生まれます。
長く書く必要はありませんが「また会いたいね」「お元気そうで安心しました」など、相手の顔を思い浮かべて言葉を選びましょう。
文字の上手さは気にせず、自分の言葉で素直に書くことが一番のコツです。
書き出しは「追伸」とすると、自然に始められます。
送り方・文面チェックリスト
暑中見舞いは、内容だけでなく届け方にも気を配ると、丁寧な印象を与えられます。
どんなはがきを使うか、日付や言葉の使い方は適切かなど、細部の工夫が心に届く要素になります。
はがき選びから投函前の確認まで、安心して送れるようポイントを整理します。
はがき選びのポイント
暑中見舞いは、私製はがき・官製はがきのどちらでも構いません。
ただし、家族や親しい人に送るなら、季節感のあるデザインを選ぶと印象が良いです。
たとえば、ひまわりや朝顔、風鈴など夏を感じるイラストは定番です。
落ち着いたトーンの和紙風はがきも人気があります。
写真入りや自作の絵を使うのも、個性が出て喜ばれるポイントです。
注意点として、郵送の際は定形サイズや料金にも気をつけましょう。
日付や「盛夏」の書き方
暑中見舞いでは、文末に季節を示す語句と日付を入れるのが一般的です。
多く使われるのが「令和〇年 盛夏」という書き方です。
「盛夏(せいか)」は、夏真っ盛りの時期という意味を持ち、季節の挨拶として好まれます。
正式な書き方を意識するなら「令和〇年7月」や「令和〇年盛夏」と漢数字で書くのが丁寧です。
ただし、親しい相手には西暦で書いても失礼になりません。
はがき全体の調和を考えて、書体や配置にも気を配ると整った印象です。
送る前の最終確認項目
暑中見舞いを送る前に、文面や宛名のチェックは欠かせません。
書き間違いや敬称の使い方など、細かな点にも気を配りましょう。
以下リストを参考に、投函前に確認してみてください。
- 宛名の漢字・敬称が正しいか
- 差出人の氏名・住所がはっきり読めるか
- 暑中見舞いの文中で時期や天候が適切か
- 日付や「盛夏」の記載があるか
- 手書きの一筆を添えているか
ひと手間かけることで、心のこもった暑中見舞いになります。
家族向けの暑中見舞い例文で、よくある質問7つ
1.暑中見舞いでおしゃれな文章はどう書けばよいですか?
おしゃれに見える暑中見舞い文例は、季節感のある言葉や絵柄を使い、簡潔にまとめるのがコツです。
ひまわりや風鈴などの情景を入れると、見た目にも涼やかな印象になります。
» 暑中見舞いをおしゃれに伝えるポイント【相手別の例文3選+書き方】
2.暑中見舞いの短い例文でおすすめは?
短い文例は「暑中お見舞い申し上げます。暑い日が続きますがご自愛ください」のようにまとめると丁寧に伝わります。
忙しい相手にも気軽に読んでもらえるのでおすすめです。
»【暑中見舞いの相手別の短い例文】3行でも丁寧に伝える書き方+マナー
3.寒中見舞いと暑中見舞いの違いは何ですか?
寒中見舞いは1月〜2月上旬に、寒さを気づかうために送る挨拶です。
一方、暑中見舞いは梅雨明け〜立秋前に送る夏の挨拶で、使用する季語や文面の内容が季節に応じて異なります。
4.友人向けの暑中見舞いにはどんな内容がいいですか?
友人への暑中見舞いでは、近況報告や思い出話、体調を気づかう一言を添えるのが自然です。
堅苦しくせず「また会いたいね」といったメッセージを入れると親しみが伝わります。
»【友人への暑中見舞い】堅すぎない気軽な例文3選【笑顔になるかも】
5.暑中見舞いでカジュアルな文面のポイントは?
カジュアルな暑中見舞いでは、口語調でまとめると親しみが出ます。
たとえば「暑いねー!元気にしてる?」のような書き出しに、夏の過ごし方や応援の言葉を加えると好印象です。
» 暑中見舞いで使えるカジュアル例文3選【友人宛に送る気軽な一言】
6.暑中見舞いのハガキはどんなデザインがよいですか?
季節感のあるイラストが入ったハガキがおすすめです。
ひまわり、海、風鈴などの夏らしいモチーフが定番で、家族向けなら写真入りや手書きの一言があると、より気持ちが伝わります。
7.暑中見舞いの時期はいつからいつまでですか?
暑中見舞いは、梅雨明けから立秋の前日までに送るのが一般的です。地域によりますが、例年7月15日頃〜8月7日頃が目安とされています。
立秋以降は残暑見舞いに切り替えましょう。
まとめ:心温まる暑中見舞いを送ろう

この記事では、文例や時期、書き方のコツなどを通して、やさしく丁寧な伝え方を解説しました。
家族向けに暑中見舞いを送るときは、マナーよりも「気持ち」を大切にします。
ポイント
- 暑中見舞いは梅雨明け~立秋前に送るのが基本
- 「暑中お見舞い申し上げます」から始め、近況→気遣い→結びの構成
- 「倒れそう」などネガティブな表現は避け、前向きな語調を意識する
- 家族との関係に合わせた文例や感謝のフレーズが効果的
- 印刷はがきにも一言手書きを添えると、印象がやわらぐ
- 送る前には宛名・敬称・文面チェックで失礼のない仕上がりに
暑中見舞いは、相手を思う気持ちを手紙で届ける日本らしい文化です。
難しく考えず、ふだんの言葉でやさしく語りかけるように書くだけで伝わります。
短い一通にも、自分らしい温かさを込めて送ってみてください。
家族との心の距離が近づくはずです。
以上です。
P.S. 小さな思いやりを伝えるチャンスです。
関連記事【先生宛ての暑中見舞い】子ども・学生・社会人向けの立場別例文3選
関連記事【暑中見舞い例文まとめ】友人・上司・取引先へ気持ちが伝わる書き方