- 9月下旬の時候の挨拶にどんな言葉を選べばよいか迷っている
- ビジネスでも私信でも失礼なく使える例文が欲しい
- 誤用せず、相手に信頼や温かさが伝わる文章を作りたい
この記事でわかること
- 白露・秋分を基準とした季語の正しい使い方
- ビジネス・私信・行事案内ごとの文体の使い分け方
- 書き出し例や結び文テンプレの具体例
- 季語のNG/OKの判断基準と誤用を防ぐ方法
- コピペして使える実用的な例文集
- よくある質問+回答
9月下旬の時候の挨拶は、二十四節気を目安に季語を選び、相手や場面に応じて文体を整えることで自然に仕上がります。
適切な語を用いることで誤用を避け、不安を与えない確かな文章となります。
さらに、書き出しや結びの定型を取り入れれば、短い文でも礼儀と温かみが伝わります。
本記事では、すぐに使える例文やコピペ可能なテンプレートを紹介し、実務でも私信でも安心して挨拶文を作成できるよう導きます。
Contents
9月下旬の基本:いつ・誰に・どう書く

まずは短く、正しく、丁寧に書きます。
二十四節気で季節語の方向を決め、相手像で文体を選び、当日の天候で語を仕上げます。
この三段を踏めば、数行でも印象は整います。
誤用は信頼を損ねるため、日付断定や天候と矛盾する表現は避けます。
- 方向=二十四節気。
- 文体=相手像。
- 語彙=当日の天候。
二十四節気の目安(白露・秋分)
二十四節気は「時期の手がかり」です。
9月は上旬に白露、下旬に秋分が巡るため、語の選択に迷いにくくなります。
白露では朝露や初秋の涼感、秋分では昼夜の均衡や空気の澄みを表す語が収まります。
年や地域で体感が異なるため、断定的な日付表現は控えます。
- 白露=朝露・初秋の涼感。
- 秋分=節目・澄んだ空気。
- 断定を避け、汎用表現を選ぶ。
文体の使い分け(漢語調/口語調)
文体は相手への配慮のかたちです。
改まる相手なら「秋分の候、貴社ますますご清栄のことと拝察いたします」
親しい相手なら「朝晩はひんやりしてきましたね。お体を大切にお過ごしください」
件名から結びまで語調をそろえ、読みやすさと敬意を両立させます。
- 漢語調=公式・目上・初連絡。
- 口語調=私信・近況・親しい間柄。
- 全体のトーンを統一する。
天候に合う語(秋晴/秋冷/野分)
語は天候と一致させます。
晴天続きに「秋晴」、冷え込みには「秋冷」、強風や荒天の余波には「野分」が合います。
判断が難しい日は「季節の変わり目」「朝夕はひんやり」などの汎用表現で外しません。
被災や荒天の地域には、安否を問う一文を先に置くと誠実です。
- 秋晴=晴天続き。
- 秋冷=冷え込み共有。
- 野分=強風・荒天の余波。
すぐ使える書き出し例(相手別)
9月下旬の挨拶は「型」を知っていれば迷いません。
相手別に決まった始め方を持つことで、状況語を差し替えるだけで完成します。
一文目に季節感、二文目に安否、本題は三文目から。
ら安心して使える流れです。
- 取引先や上司=端正に。
- 友人や家族=温かく。
- 地域行事=簡潔に。
取引先/上司/先生向け
改まる相手には漢語調の定型が万能です。
「秋分の候、貴社ますますご清栄のことと拝察いたします」
「秋冷の候、先生にはご健勝のことと存じます」
これらを冒頭に置けば、礼儀も敬意も伝わります。
- 取引先=「ご清栄」「ご発展」
- 上司=「ご健勝」「ご多幸」
- 先生=「ご壮健」「ご自愛」
友人/家族向け(口語調)
親しい相手は自然体が一番です。
「朝晩はひんやりしてきたね。体調は大丈夫?」
「雨が続いているけど元気に過ごしてる?」
挨拶の体裁を守りつつ距離が縮まります。
- 友人=会話調で共感。
- 家族=安心感を届ける。
- 柔らかい調子で温度感。
学校・地域行事/案内文
案内文は誰もが読みやすい型で始めます。
「秋冷の候、皆さまにおかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます」
「さて、このたび〜」と本題に移せば整います。
健康配慮と簡潔さが何よりも大切です。
- 全員向けに「皆さま」
- 二文以内で本題へ。
- 健康配慮+行事案内を基本形に。
»【9月の学校向けの時候挨拶】上中下旬の書き出しと保護者文例まとめ
9月下旬の結び文テンプレ
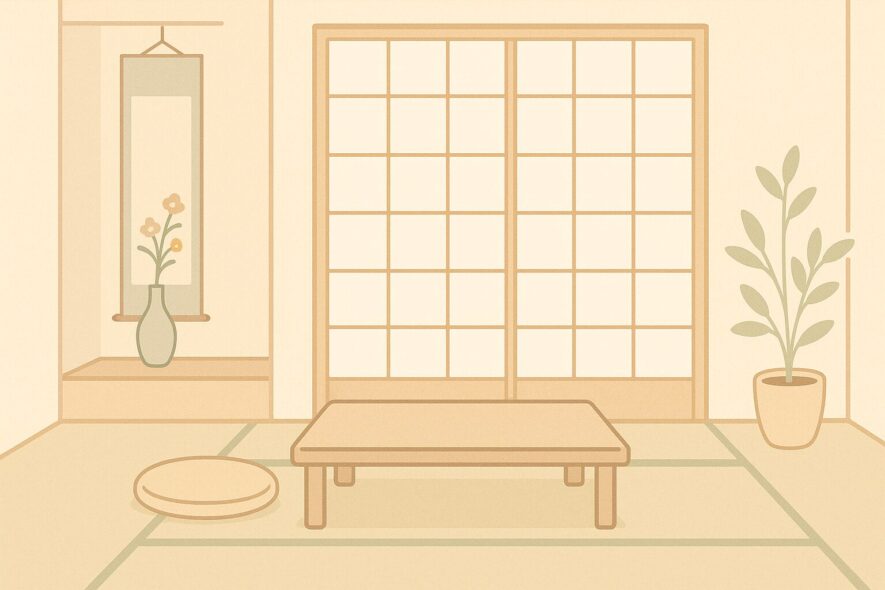
一文で伝わる結びを、目的別に用意しておけば迷いません。
本題の要約→配慮→丁寧な締めの順で、短く整えます。
- 目的別にストックし、差し替えて使う。
- 長くても二文までに抑える。
- 配慮の一言で余韻を整える。
繁栄・健康を祈る結び
- ビジネス汎用:「朝夕は冷え込む折、皆様のご健勝と一層のご発展をお祈り申し上げます」
- 取引先企業:「実り多き季節を迎え、貴社ますますのご清栄を心よりお祈りいたします」
- 私信・家族:「季節の変わり目ですね。どうぞお体を大切にお過ごしください」
継続取引/ご高配を願う結び
- 定期取引:「平素のご厚情に深謝申し上げます。今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます」
- 共同PJ進行中:「引き続きのお力添えを賜れましたら幸いです」
- 納品後フォロー:「末筆ながら、今後とも変わらぬお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます」
台風・残暑時の言い換え
- 荒天時汎用:「荒天が続く見込みと聞きます。何よりも安全を第一にお過ごしください」
- 影響懸念:「影響が最小であることを願っております。お困りの節は遠慮なくお知らせください」
- 残暑時汎用:「暑さの名残りが続きます。どうぞご自愛のうえ健やかにお過ごしください」
季語の早見表とNG/OKの注意
季語を正しく使うと、挨拶文の印象が大きく変わります。
仲秋・秋分・秋冷は使い分けで季節感が鮮明になり「秋晴」は条件を満たす場面でだけ映えます。
誤用防止は、時期・天候・地域の3点チェックで十分です。
仲秋/秋分/秋冷の使い所
- 仲秋=9月中旬〜下旬、月や涼感を表す。
- 秋分=9月22〜24日頃、昼夜均衡の節目。
- 秋冷=9月下旬〜10月、冷え込みを表す。
「秋晴」を避ける場面
- 雨天・曇天=不自然に映る。
- 台風・荒天時=無神経と受け取られる。
- 晴天続き=安心して使える。
誤用を避けるチェック
- 時期=二十四節気に照らす。
- 天候=実際の空模様と合わせる。
- 地域=相手の状況を想像する。
3点を守れば、誤用はほぼ防げます。
例文集(ビジネス/メール/私信)
例文は相手や媒体で切り替えるだけで完成します。
形式を整えれば信頼が生まれ、一筆で温かさを添えられます。
最後にチェックをすれば、安心して送信できます。
件名/宛名/差出人の整え方
- 件名=「ご挨拶」「近況のご報告」など簡潔。
- 宛名=組織は「御中」、個人は「様」
- 差出人=フルネーム。ビジネスは会社名・役職も。
一筆添えるフレーズ集
- ビジネス:「平素よりお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます」
- メール:「ご多用の折恐れ入りますが」
- 私信:「季節の変わり目ですのでご自愛ください」
送信前の最終チェック
- 誤字脱字・敬称に誤りがないか。
- 季語や表現が相手状況と合っているか。
- 添付・署名が抜けていないか。
9月下旬の時候挨拶で、よくある質問8つ
1.9月のビジネスの時候挨拶では、どんな表現が適切ですか?
ビジネスでは「秋分の候」「秋冷の候」など端正な漢語調が適切です。
体調を気遣う一文を添えると誠実さが伝わり、安心感を与えられるでしょう。
»【9月のビジネス向け時候の挨拶】上・中・下旬の例文+失敗しない結び
2.10月の時候挨拶の例文は、どんな内容が良い?
10月は「秋涼の候」「錦秋の候」など、深まる秋を感じさせる語が使えます。
具体的には「爽秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」が安心です。
3.10月の時候挨拶で避けたほうがよい表現はありますか?
10月に「残暑」や「初秋」といった語を使うと時期に合わず不自然です。
秋も深まる時期なので「紅葉」「秋涼」など季節感が進んだ言葉を選ぶと良いです。
4.時候挨拶の一覧はどう活用すればよい?
時候の挨拶 一覧は月ごとの季語がまとまっているため便利です。
時期や相手の立場に応じて言葉を選べば、迷わずに適切な挨拶文を作成できます。
5.風が涼しくなってきた頃のあいさつはどう書けばよいですか?
「朝夕の風に秋を感じる頃となりました」などが自然です。
体調への気遣いを添えると、寄り添う印象を与えられ、文章に温かみが生まれます。
6.6月の時候挨拶ではどんな表現が一般的ですか?
6月は梅雨の時期なので「入梅の候」「長雨のみぎり」が定番です。
相手の健康や雨の被害に配慮した文を添えると、礼儀正しい印象を持ってもらえるでしょう。
» 6月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
7.2月の時候挨拶にはどんな語が使われますか?
2月は立春を迎えるため「立春の候」「余寒の候」がよく使われます。
寒さが続く時期なので、相手の体調を気遣う言葉を加えると自然で丁寧な印象になります。
»【2月の挨拶文まとめ】好印象を残すビジネス&手紙の例文と書き方
8.涼しくなってきたときの挨拶でメールにはどんな文例がありますか?
「朝夕は涼しく過ごしやすくなりました。いかがお過ごしでしょうか」と始めると自然です。
短文でも丁寧さが伝わり、メールでのやり取りに活かせます。
»【9月の手紙挨拶】相手別に使える書き出しと言い回し+結びテンプレ
まとめとコピペ用ミニ一覧(終)

9月下旬の挨拶は「季語の選び方」「相手別の型」「最終チェック」の3点を押さえれば十分です。
最後にそのまま貼って使えるミニテンプレをまとめました。
コピペ用ミニ一覧
- ビジネス書き出し:「秋分の候、貴社ますますご清栄のことと拝察いたします」
- 私信用書き出し:「朝晩はひんやりしてきましたね。お元気にしていますか」
- 結び(繁栄祈念):「朝夕は冷え込む折、皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます」
- 結び(継続取引):「平素のご厚情に深謝申し上げます。今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます」
- 残暑対応:「暑さの名残りが続きます。どうぞご自愛のうえお過ごしください」
以上です。
関連記事9月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【9月の挨拶文まとめ】時期別のビジネス・カジュアル例文+安心マナー
