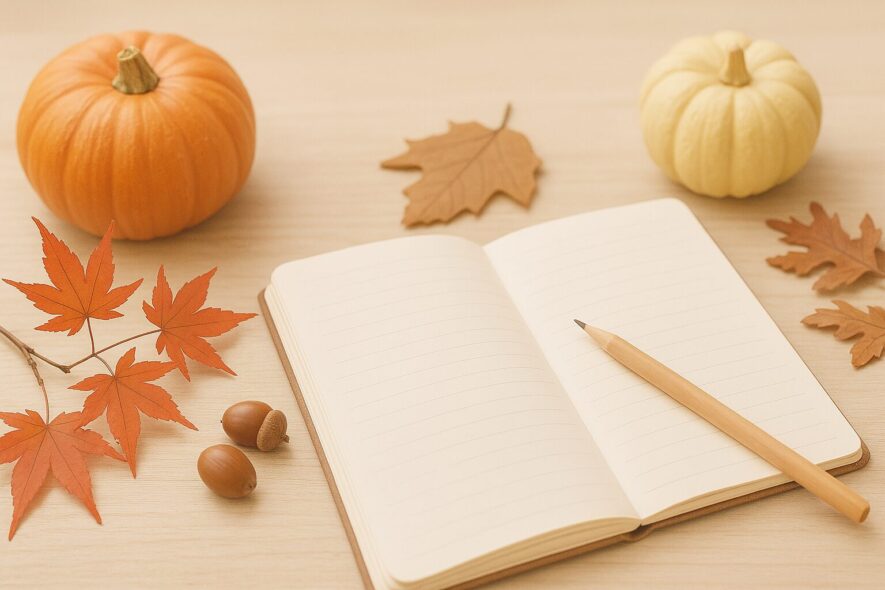- 11月のおたより、毎回書き出しに悩む…
- 季節感を出したいけれど、言葉が思いつかない…
- 忙しくて時間がなく、結局ワンパターンになってしまう…
この記事でわかること
- 11月らしい季節の言葉や行事(文化の日・七五三・勤労感謝の日)の入れ方
- クラスや活動内容に応じて使える書き出しテンプレートや短文例
- 保護者に安心感を与える言葉選びと、NG表現のやさしい言い換え方法
- 体調管理や安全面、保護者連携などをやわらかく伝えるコツ
- 季節語・比喩・つなぎ語の使い方で文章に深みと余韻を持たせる方法
- よくある質問+回答
本記事では、先生や保育士の方向けに「11月のおたよりの書き出し」で使える構成と例文をまとめました。
短くても心が伝わる3行テンプレートを使えば、紅葉や木枯らしなどの季節語を入れ替えるだけで、自然であたたかいおたよりが完成します。
文化の日や七五三、勤労感謝の日など行事に合わせた文例もあり、どのクラスでも使いやすい構成です。
保護者に安心感を届けながら、自分らしい言葉でおたよりを楽しめます。
今月の便りが「義務」ではなく「つながる時間」になるのです。
Contents
基本の考え方と3行テンプレ
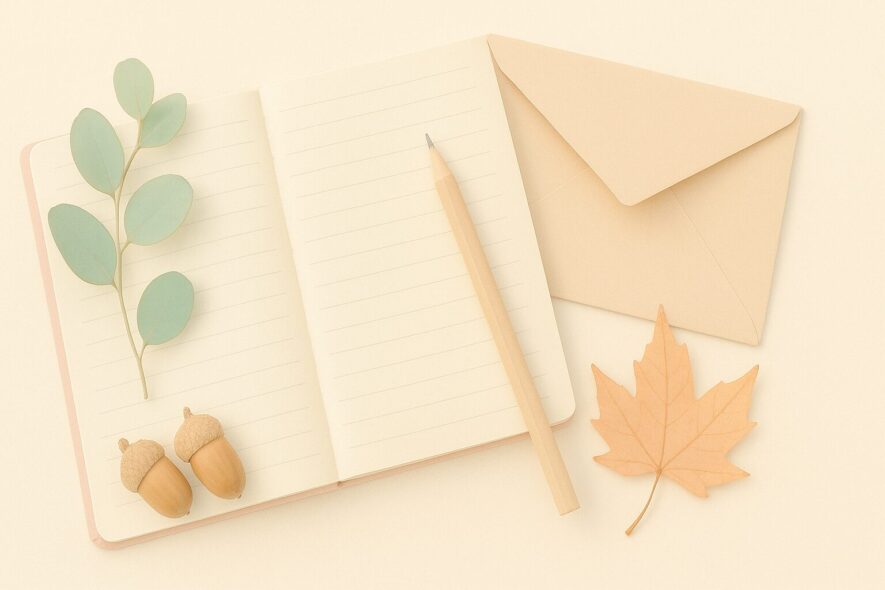
結論は、3行の雛形に置換スロットを用意すると、量産が容易になります。
季節語と活動と配慮を入れ替えるだけで、文の骨組みが保てるからです。
例として、行1「【季節語】が広がる朝です」、行2「【活動】が【進捗】です」、行3「【配慮】にご協力ください」を用意します。
各クラスで名詞を差し替えるだけで統一感が生まれます。
- 季節語:紅葉、木枯らし、初霜。
- 活動:落ち葉あそび、発表会れんしゅう。
- 配慮:上着の用意、手洗い、給水。
11月らしさの要素分解
結論は、小物の語彙を加えると差し替えが容易です。
写真や日々の記録と合わせやすく、事実の裏づけがとれるからです。
例として、「どんぐり袋」「銀杏の葉」「ベンチ」「木の実」を短語で入れます。
1語ずつを独立させると、装飾を足さずに雰囲気が伝わります。
- 小物:どんぐり袋、木の実、落ち葉の冠。
- 場所:園庭、並木道、公園の丘。
- 時間:朝、帰り道、夕ぐれ。
3行構成の型と配置ルール
各行を1センテンスで切り、改行で呼吸を作ります。
短い紙面でも視線が迷わず、連絡事項へ自然に進めるからです。
例として、行1「紅葉がすすむ朝です」、行2「発表会のれんしゅうが始まりました」、行3「上着の用意にご協力ください」とします。
語尾は平らに保ち、同語の反復を避けます。
- 行頭は名詞か体言で安定させる。
- 重複語は置きかえる。
- 改行で意味のまとまりを示す。
語尾・トーンの決め方
依頼語を2種で回し、単調さをへらします。
読み手が受け手の立場で読んだとき、音の変化が負担を軽くするからです。
例として、「お願いいたします」と「助かります」を交互に使います。
観察と配慮を前に置き、協力は短く端的に添えます。
- 観察→配慮→協力の順で固定。
- 依頼語は2種までにする。
- 評価は控えめに、事実を先に。
季節の言葉リストと使い方
季節の言葉は文章に息を吹き込む鍵です。
短い語が日常の風景をよみがえらせ、読む人の心を和ませるからです。
例として、「木枯らしが園庭の葉を運ぶ朝」「初霜が光る通園路」「紅葉が散る音に耳をすます午後」などが効果的です。
自然の描写は派手さよりも素朴さを意識すると、落ち着いた印象に仕上がります。
- 身近な光景を素材にする。
- 五感のうち2つを選んで重ねる。
- 1文を短く切って余韻を残す。
紅葉・木枯らし・初霜の例
季節語を子どもの瞬間と重ねると、温もりが生まれます。
自然の変化と成長の場面が響き合うからです。
例として、「紅葉を拾い集めて笑う」「木枯らしの音に負けず声を張る」「初霜の冷たさに小さく手をすぼめる」などです。
読む人が目で追えるように動作を入れると、印象が深まります。
- 紅葉:色と動きを描く。
- 木枯らし:風と音を結ぶ。
- 初霜:光と冷たさを並べる。
比喩と体感語の作り方
比喩は日常の感覚をすくい取る程度に抑えます。
共感できる表現のほうが、読者の記憶に残るからです。
例として、「風が笑うように吹く」「霜が絹のようにきらめく」「空気が透き通る」と書くと、静かな余韻が生まれます。
比喩と体感語をバランスよく置くことで、短文でも深い情景を描けます。
- 身近な自然をもとにする。
- 形容詞より動詞で表す。
- 重複を避け、音読で調整する。
つなぎ語のバリエーション
文の流れをつくるつなぎ語が、文章の呼吸を整えます。
句と句の関係を整理することで、読み手が自然に進めるからです。
例として、「〜につれて」「〜のころ」「〜とともに」「〜を感じながら」などを使います。
1文ごとに1種類のつなぎ語を意識するだけで、読みやすさが増します。
- 時間系:「〜のころ」「〜につれて」
- 感情系:「〜を感じながら」「〜とともに」
- 行動系:「〜を迎え」「〜に合わせて」
行事別の書き出しテンプレ

結論は、行事を描くときは“息づかいが伝わる言葉”を意識します。
感謝や喜びは大げさな言葉よりも、日常の中の一瞬に宿るからです。
例として、以下などです。
- 「文化の日を前に、紙の感触をたのしむ声が響きます」
- 「七五三のころを迎え、笑顔で手をつなぐ姿が見られます」
- 「勤労感謝の日に向けて、ありがとうの言葉を口ずさむ姿があります」
行事を通じて“日々のぬくもり”を伝える文章を目指します。
- 季節語と行事語を1文にまとめる。
- 行事名は1回のみ登場。
- 心の動きを小さく描く。
文化の日を入れる言い方
文化の日の書き出しは“つくる手と感じる心”を描きます。
作品を通して集中や発見が生まれる瞬間に、子どもの成長が見えるからです。
例として、「文化の日を前に、色と形をたのしむ時間が増えています」「文化の日に合わせて、園内に明るい作品が並びました」などです。
表現の楽しさを感じる文が、行事のあたたかさを伝えます。
- 活動の音(描く・貼る・並べる)を入れる。
- 色や形など具体的な語を添える。
- 結果より過程を強調する。
七五三を入れる言い方
七五三の文は“静かな喜び”を中心にします。
祝う行事を直接書かなくても、成長を感じる空気で伝わるからです。
例として、以下などです。
- 「七五三のころを迎え、登園の足どりに自信を感じます」
- 「お祝いの話をうれしそうに話す声が聞かれます」
やさしい気持ちで共感できる文を意識します。
- 成長・自立・笑顔など肯定的な語を使う。
- “祝う”ではなく“感じる”を軸に書く。
- 家庭と園の両方が想像できる文を意識。
»【七五三のおめでとうメッセージ】相手別文例とマナー完全ガイド
»【七五三お祝いメッセージ】そのまま使える相手別例文と好印象の書き方
勤労感謝の日の触れ方
勤労感謝の日の文では“ありがとうの音”を届けます。
声や絵など子どもたちの表現に、感謝の心が自然に表れるからです。
例として、以下などです。
- 「勤労感謝の日を前に、“ありがとうカード”をつくりました」
- 「お家の方への感謝を言葉にする姿が見られます」
文の最後をやさしい言葉で締めると、温かな余韻が残ります。
- 感謝の動作(言う・渡す・描く)を取り入れる。
- “ありがとう”は1文中に1回に限定。
- 最後の文は柔らかく終える。
クラス別の短文テンプレ
結論は、年齢ごとに“息づかいの違い”を感じられる文章が理想です。
日常の小さな瞬間に、その子の世界が詰まっているからです。
例として、「0–1歳はぬくもりの時間」「2–3歳は発見の時間」「4–5歳はつながりの時間」
発達の段階を言葉で描くことが、おたよりの深みを生みます。
- 短くても情景が浮かぶ文を意識。
- 動作と音の言葉を組み合わせる。
- 心情は語らず“伝わる”構成にする。
0–1歳クラス向け短文
毛布のぬくもりに包まれ、目を細めています。
風の音に耳を澄ませながら、秋の空を見上げています。
安心の中で、少しずつ世界が広がっています。
2–3歳クラス向け短文
木の実を拾って“なんの実かな?”と話しています。
友だちと落ち葉を踏みしめ、音をたのしんでいます。
発見のたびに、笑顔があふれています。
4–5歳クラス向け短文
友だちと相談しながら、作品を仕上げています。
年下の子に手を差しのべる姿が見られます。
優しさが日々の中に自然にあふれています。
活動別の差し替えフレーズ

結論は、活動の瞬間に漂う“音と香り”を描くことで、文章が生き生きとします。
体験を五感で伝えると、読む人の心に情景が残るからです。
例として、「風が頬をなでる」「土の香りが広がる」「葉が舞う音が聞こえる」
動きと余韻を行き来するリズムが、おたよりの温度を決めます。
- 動きと静けさを交互に入れる。
- 感情語を使わず情景で伝える。
- 読後に“やさしさ”が残る文を意識。
遠足・園外活動の書き出し
秋の風に背中を押されながら、笑顔でバスに乗り込みました。
窓の外を見つめるまなざしに、期待の光がゆらめきます。
山道の木々が色づき、子どもたちの声が風にとけていきます。
芋ほり・焼いも会の書き出し
土の香りに包まれながら、両手いっぱいのさつまいもを抱えています。
「とれたよ」と響く声が園庭にひろがり、焼いもの香ばしいにおいが重なります。
秋のぬくもりが、やさしく心に残ります。
落ち葉遊び・どんぐり拾い
落ち葉を集めて風にまかせると、空にひらひらと舞い上がります。
どんぐりを手にとって、「おそろいだね」と笑う声が聞こえます。
秋のひかりが、園庭いっぱいに広がっています。
体調管理と安全の表現集
11月は、朝晩の空気が冷たくなり、体調の変化を感じやすい季節です。
「気をつけて」という言葉より、「あたたかく過ごしています」という描写が心に残ります。
見る人が安心できる言葉、それがこの時期のおたよりの本質です。
感染症に配慮する言い方
手洗いやうがいの声が響く昼下がり。
笑顔で水をすくう姿に、安心の時間が流れています。
「予防」よりも「ていねいな日常」を描くことで、穏やかな印象になります。
防寒・乾燥への配慮表現
朝の冷たい風に、上着のボタンをとめる手が見られます。
指先をこすりながら、笑い合う声が響きます。
冬支度のひとこまを切り取ることで、季節のあたたかさを伝えられます。
過度に不安にさせない言い換え
「気をつけましょう」ではなく、「〜して過ごしています」と書く。
それだけで文章の空気が変わります。
行動を描くことで、安心と信頼が自然に伝わります。
保護者連携の丁寧な言い回し
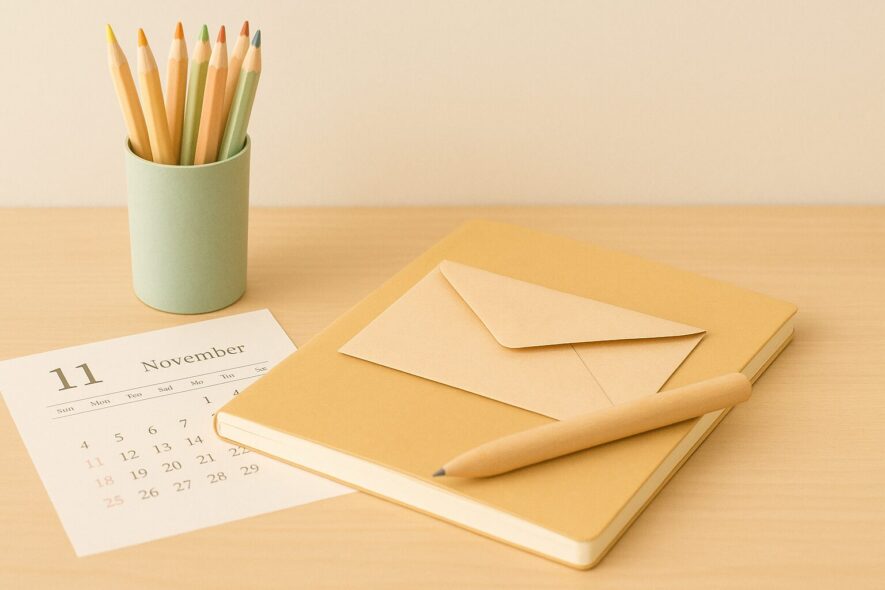
11月は行事が多く、お願いや報告の文が増える季節です。
そんなときこそ、言葉のやわらかさが信頼をつくります。
「ご協力ください」ではなく「助かります」の一言に、感謝が宿ります。
おたよりは、声の届かない場所での“会話”です。
持ち物・提出物の依頼文
必要な持ち物を伝えるときは、やさしい依頼文に変えるだけで印象が変わります。
「ご用意をお願いします」より「ご準備くださると助かります」
準備の理由を添えると、納得と協力が自然に生まれます。
日々の声かけと感謝の言葉
「いつもありがとうございます」だけでなく、「〇〇のおかげで助かっています」と添えると温度が伝わります。
具体的な出来事と一緒に感謝を伝えると、言葉が生きたものになります。
次号予告・締めの一言
締めくくりは、前向きな余韻を残す言葉で。
「次回は冬のあそびの様子をお伝えします」
小さな一言が、次を楽しみにしてもらえる合図になります。
NG表現と代替リスト
おたよりは、園と家庭をつなぐ言葉の橋です。
「気をつけて」「頑張りましょう」を少し言い換えるだけで、心の距離が変わります。
安心を届ける文章には、やわらかな余白があります。
不安を煽る表現の回避
否定ではなく、肯定で伝える。
それが安心の第一歩です。
「〜しないように」ではなく、「〜しています」
言葉を変えるだけで、読後の印象がまるくなります。
評価が強すぎる表現の調整
評価ではなく、観察を描く。
「上手」より「ていねい」、「頑張った」より「一歩ずつ」
小さな表現の違いが、子どもの姿をより正確に伝えます。
個別事情に配慮する言い方
誰かを基準にせず、「それぞれ」「みんなで」という言葉を軸にします。
違いを包み込むことで安心できます。
おたよりの目的は、比べることではなく、つなげることです。
コピペで使える例文40選
11月のおたよりでは、短くても心が伝わる文が喜ばれます。
1行、3行をうまく組み合わせるだけで、読みやすく温かいおたよりになります。
文体の切り替えや語彙のストックを意識しておくと、表現の幅が広がります。
1行・3行の即戦力テンプレ
「木々の色づきに季節の深まりを感じます」
「落ち葉を拾って秋を感じています」
1行で伝わる文を積み重ねることで、読む人の心に余韻を残します。
3行構成にするなら「季節→活動→気持ち」が基本です。
丁寧体と常体の切り替え例
「秋の陽ざしがやわらかくなりましたね(丁寧体)」
「秋の陽ざしがやわらかくなるころです(常体)」
この2文を並べて読むだけで、文章のトーンが整います。
丁寧体は親しみを、常体は余韻を生みます。
名詞・動詞スロット一覧
文を作るときの材料を増やしておくと、迷わず書けます。
「風」「木の葉」「陽ざし」「笑顔」を組み合わせ、「舞う」「包む」「広がる」などでつなぐだけで、温かい一文が生まれます。
- 名詞:木の葉・陽ざし・風・空気・ぬくもり。
- 動詞:包む・揺れる・舞う・見上げる。
- 形容詞:あたたかい・やわらかい・澄んだ。
»【11月のカジュアル挨拶】迷わず使える一言テンプレ+好印象の書き方
11月のおたより書き出しで、よくある質問7つ
1.11月の小学校おたより書き出しでは、どんな表現が喜ばれる?
小学校向けのおたよりでは、明るく前向きな書き出しが好印象です。
「朝晩の冷え込みに秋の深まりを感じます」「紅葉が色づき始めました」など、季節の変化を織り込みつつ子どもたちの成長を称える言葉を添えると温かく伝わります。
» 学校で使える11月の時候挨拶フレーズ【目的別の挨拶文テンプレート】
2.11月の保育園のおたより書き出しでは、どんな雰囲気が合う?
保育園では、子どもたちの体験や五感を通じた季節感を出すと共感されやすいです。
「木々の葉が色づき、園庭にも秋の訪れを感じます」など、園生活に重ねる表現が読みやすく、保護者の心にも温かく届きます。
»【11月の保育の挨拶文】季節と成長を自然に書けるコツまとめ
»【11月の挨拶文】上旬・中旬・下旬の書き出し+用途別テンプレ集
3.11月の園だよりのネタが思いつかないときはどうすればいい?
ネタ切れのときは、園での小さな変化を拾うのがコツです。
「風が冷たくなり外遊びの時間が短くなりました」や「子どもたちが落ち葉で遊ぶ姿に季節を感じます」など、日常の一場面を書くだけでも十分な季節感が出せます。
4.11月のおたより書き出しで、0歳児クラスではどんな内容が安心感を与える?
0歳児クラスでは、保護者への安心感を意識するのが大切です。
「朝晩の冷え込みが強くなってきましたが、子どもたちは笑顔で過ごしています」といった体調面への配慮や園での様子を入れると、読み手に信頼感を与えられます。
5.11月のおたよりのイラストにはどんなモチーフが合う?
11月のおたよりイラストは、落ち葉・どんぐり・焼きいも・紅葉などの自然素材が定番です。
色味はオレンジやブラウンなど温かみのあるトーンにすると、秋の深まりをやさしく表現できておすすめです。
6.11月のおたより書き出しで、学童ではどんな内容を入れると良い?
学童では、季節感と活動内容をバランスよく伝えるのがポイントです。
「夕暮れが早くなり、室内での工作活動が増えています」など、季節の変化を交えた書き出しにすることで、読んでいて情景が浮かびやすくなります。
7.10月のおたより書き出しから、11月にうまくつなげるコツは?
10月から11月への移行では、気温の変化や行事の流れをつなぐのがコツです。
「運動会を終え、ひとまわり成長した子どもたち」「木々の色づきとともに季節が進んでいます」など、過去と現在をつなぐ一文を入れると自然な流れになります。
まとめと活用のコツ、記事の要点
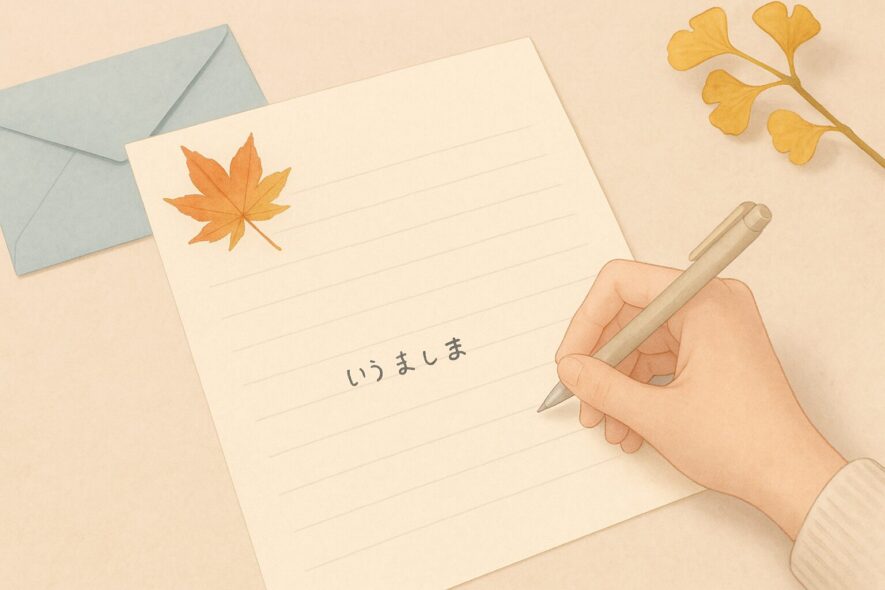
おたよりは、書いて終わりではなく“育てる”ツールです。
差し替えや更新を繰り返すことで、自分だけの文集ができます。
書き続けるほど、言葉の手ざわりがやわらかくなります。
差し替えで量産する手順
「季節語+子どもの様子+気持ち」
この3つを組み合わせるだけで、何通りものおたより文が生まれます。
「冷たい風の中でも元気に走っています」「冬の空を見上げて笑顔が広がります」
単語を変えるだけで、新しい季節が始まります。
年次更新のチェック項目
前年の文章を見直すときは、「日付」「行事」「語尾」「季節語」を確認します。
この4つを変えるだけで、古さが消えます。
子どもたちの今に寄り添った言葉を選ぶことで、読む人の心に新鮮さが残ります。
来月への布石の置き方
おたよりの締めくくりは、次への期待を込める場所です。
「寒さが増す12月も、子どもたちの笑顔があたたかな日々を運んでくれそうです」
そんな一文で終わるだけで、ページの余韻が残ります。
記事で学べる要点
11月のおたよりは“短くても心が伝わる言葉”を軸にすると、読む人に安心とあたたかさを届けられます。
構成・語彙・トーンを整理し、季節や子どもの成長を自然に描くことが大切です。
- 3行テンプレで構成を固定し、季節語や活動を差し替えて量産できる
- 季節の言葉や比喩を加えて、11月らしい雰囲気を出せる
- 行事(文化の日・七五三・勤労感謝の日)を自然に盛り込める
- 年齢や活動に合わせた短文テンプレで、すぐに使える
- 体調・安全・保護者連携などの表現も安心感を持って伝えられる
- NG表現の言い換えで、やわらかく誠実な印象を与えられる
この時期に書くおたよりは、保護者との信頼を深める機会です。
季節の移ろいと子どもの姿を結ぶ言葉を少し整えるだけで、11月の空気がそのまま届く「やさしいおたより」が完成します。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ