- 「5月のおたより、そろそろ書かないと…でも何を書けばいいの?」
- 「毎回同じような文章になってしまって、正直ネタが尽きてきた」
- 「保護者にちゃんと伝わってるか、いつも不安になる…」
この記事でわかること
- 5月に使える季語や表現例
- フォーマル・カジュアル・保護者目線での書き出し例文
- 行事や子どもの様子の伝え方・ネタの選び方
- 締めの挨拶文と協力依頼のコツ
- 配布タイミングやレイアウトの注意点
- おたよりを通して、心に残る表現や配慮方法
- よくある8つの質問+答え
5月のおたよりは、季節感と子どもの様子、感謝の気持ちを届けるチャンスです。
本記事では、5月らしい季語や例文、書き出し・締め・Q&Aまでを一つにまとめて紹介します。
そのまま使える文例とポイント解説つきで、読みやすく印象に残るおたよりがすぐに書けます。
少しの工夫で、園と家庭のつながりがもっとあたたかく、深くなります。
この記事の目次
5月のおたよりで押さえるべき季語と特徴

新緑の息吹が感じられる5月は、自然の変化を言葉で伝えやすい季節です。
季語をうまく取り入れることで、読み手の感性に訴えるおたよりになります。
行事や子どもの様子と組み合わせて表現すると、より印象的に伝わります。
ここでは、5月らしさを表す季語の例と、使い方のコツを紹介します。
5月ならではの季語一覧
「新緑」「若葉」「5月晴れ」「風薫る」「鯉のぼり」「端午の節句」などが代表的です。
これらは春から初夏へと向かう時季の爽やかさや、子どもにまつわる行事を象徴します。
たとえば「若葉が風にそよぐ頃」という表現は、風景の鮮やかさや季節の移ろいを印象づけます。
読み手の五感に届くような、やさしい表現を選ぶのがポイントです。
季語を使う際の注意点
季語をたくさん使いすぎると、かえって不自然になってしまいます。
文章全体との調和を意識し、1~2語を自然に取り入れる程度がちょうどよいです。
また、伝統的な季語と現代的な言い回しを組み合わせると、読みやすくなります。
丁寧に選んだ季語は、おたよりに奥行きとやわらかさを添えてくれます。
季語で演出する新緑のイメージ
「新緑」は、生命力や成長を象徴する言葉です。
特に子どもたちの成長と重ね合わせることで、読者の共感を得やすくなります。
「新緑の光が教室を包み、一人一人の瞳が輝く季節です」といった描写は、温かさと期待感を引き出します。
情景を映し出す言葉が、印象に残るおたよりにつながるでしょう。
書き出しに使える挨拶文例
5月のおたよりは、季節の変化を伝えながら心を引き込む書き出しが重要です。
最初の一文に季語や情景を入れることで、温かみのある印象を与えられます。。
フォーマルな場面から親しみやすいトーンまで、相手や目的に応じた表現を使い分けましょう。
ここでは、3つの視点からおすすめの書き出し例を紹介します。
フォーマル向け書き出し例文
新緑の候、保護者のみなさまにはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
書き出しは、丁寧な印象を与えるだけでなく、季節感も自然に取り入れられます。
行事のお知らせや園だよりなど、改まった文面に適しています。
カジュアル向け書き出し例文
風にそよぐ若葉がまぶしい季節となりました。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
少しくだけた口調で書くことで、読み手に親しみを感じてもらいやすくなります。
日々の連絡や学級通信など、日常的なおたよりにおすすめです。
»【5月のカジュアル挨拶文】堅苦しさゼロで伝わる一言3選+注意点
保護者目線で安心感を与える書き出し
新緑に包まれた教室で、お子さまの成長を感じる瞬間が増えています。
いつも温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
保護者が安心し、園や学校への信頼感を深められるようなトーンで始めると好印象です。
子どもの様子を自然に織り交ぜることで、心が伝わる文章になります。
本文に盛り込みたい具体例とネタ
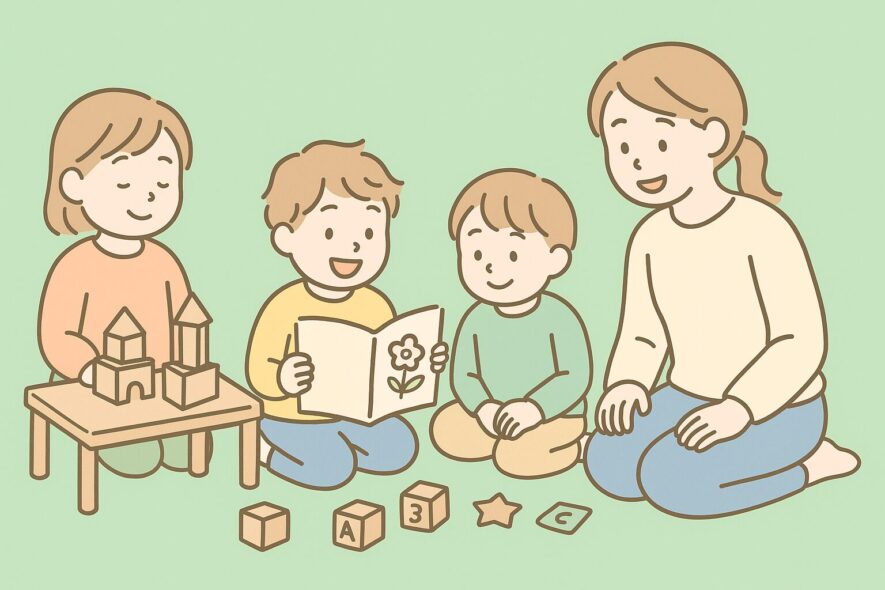
おたよりの本文には、行事や子どもの活動を具体的に書くことで、読み手の関心を引きつけられます。
様子が目に浮かぶような描写を意識すると、保護者にとって親しみやすい内容になります。
行事の紹介や日々の成長を伝えるための具体例とネタを紹介します。
行事やイベントの触れ方例
5月12日(日)に春の遠足を行います。
場所は近隣の○○公園で、自然に触れながら季節の変化を感じる活動を予定しています。
日付・場所・目的を明記することで、保護者の準備もスムーズになります。
内容が簡潔で明瞭だと、行事への理解と協力も得やすくなります。
子どもの様子を伝えるポイント
体育の時間、○○くんは初めて竹馬に挑戦しました。
転びそうになりながらも、最後まで笑顔で頑張る姿が印象的でした。
具体的な行動と感情を伝えることで、保護者が成長の瞬間を感じ取れます。
ひとりひとりの頑張りが伝わるよう心を込めて記しましょう。
園やクラスの取り組み紹介例
本クラスでは5月から朝の読み聞かせタイムを導入しました。
毎朝5分間、絵本を通じて子どもたちが言葉の世界に親しんでいます。
取り組みのねらいや期待する成長の方向性を明記すると、教育方針への理解も深まります。
保護者が園やクラスに信頼を持てるきっかけになります。
締めの挨拶文例とマナー
おたよりの締めくくりは、感謝と今後の協力を促す大切な部分です。
温かい余韻を残しつつ、丁寧な言葉で締めることで印象が良くなります。
読者に好印象を与える締めの文例や、伝わりやすい配布の工夫を紹介します。
感謝を伝える締めの一文
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。
配慮と丁寧さが伝わります。
保護者も「読んでよかった」と感じやすくなり、次回のおたよりにも自然と目を通してもらえます。
今後の協力をお願いする表現
今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。
協力のお願いを穏やかに伝えることで、負担感を与えずに参加意識を高められます。
信頼関係を育む一言として、締めには欠かせない要素です。
配布タイミングとレイアウトのコツ
行事のおたよりは、1週間前の配布が目安です。
余裕をもって渡すことで、予定調整や準備がしやすくなります。
レイアウトは見出しと本文の間にを挿入して、情報が探しやすくなるよう工夫しましょう。
保護者がストレスなく読めるおたよりに仕上がります。
5月挨拶文のおたよりで、よくある質問8つ

1.5月のおたよりで締めの言葉はどう書けばよいですか?
「ご理解とご協力をお願いいたします」や「最後までお読みいただきありがとうございます」など、感謝と協力を促す表現が基本です。
配慮が伝わる丁寧な締め方が好印象です。
»【5月の手紙挨拶】知らないと損する時候表現+3つのシーン別例文
2.5月のおたよりに子どもの様子をどう盛り込めばいいですか?
活動の様子を具体的なエピソードで紹介すると伝わりやすいです。
たとえば「竹馬に初挑戦し、笑顔で取り組んでいました」など、成長の瞬間が感じられる表現が効果的です。
3.学級通信の5月の書き出しには何を書けばいいですか?
「若葉がまぶしい季節となりました」「新緑の風が心地よい季節です」など、5月の季節感を意識した言葉から始めると柔らかく自然な印象を与えます。
季語の活用もおすすめです。
4.5月の挨拶を面白く書くにはどうすればいいですか?
読者のクスッと笑える共感ネタを入れると効果的です。
たとえば「衣替えをしてみたものの、まだ寒い朝に迷っています」など、身近な季節のギャップを取り上げると親しみが湧きます。
»【5月の面白い挨拶】笑顔が生まれる一言3選×2+失敗しないコツ
5.5月の園だよりにはどんな例文が適していますか?
「春の遠足では、自然に親しみながら元気に遊ぶ子どもたちの姿が見られました」など、行事と成長を絡めた例文が効果的です。
読み手の目に浮かぶような描写を意識しましょう。
6.5月のおたよりの例文で気をつけることはありますか?
例文は丁寧さと季節感を意識し、子どもたちの成長や園の活動内容が伝わる内容にしましょう。
長すぎず簡潔にまとめることで、負担を減らせます。
» 5月のおたよりに使える時候の挨拶3選【自然に気持ちが伝わる書き方】
7.5月の園だよりのネタが思いつきません。どうすれば?
園行事(遠足、こいのぼり制作)、季節の移り変わり、子どものつぶやきなどが定番ネタです。
昨年の園だよりを見返すとヒントが得られることも多いので、振り返りもおすすめです。
8.園長の5月の園だよりには何を書けばよいですか?
園長としては、年度初めの子どもたちの成長や職員の思いを丁寧に伝えるとよいです。
たとえば「新しい環境に慣れ、笑顔が増えてきました」といった温かい視点が読者の心に響きます。
まとめ:5月のおたより挨拶文で好印象を届ける
5月のおたよりは、新緑のまぶしさや行事の楽しさを伝えるタイミングです。
書き出しから締めまで、丁寧な言葉と具体的な内容を盛り込むことで寄り添えます。
ポイント
- 5月の季語は「新緑」「若葉」「風薫る」などが代表的
- 季語は多用せず、文章との調和を意識して取り入れる
- フォーマル・カジュアル・保護者目線など使い分けた書き出し例
- 本文には行事・活動・取り組みを具体的に書くと伝わりやすい
- 締めには「感謝+協力依頼」の言葉で温かな印象を残す
- 配布タイミングやレイアウトの工夫で読みやすさもアップ
おたよりは「形式よりも気持ち」が伝わることがいちばん大切です。
安心感と信頼が伝われば、園と家庭のやりとりは温かなものになります。
「若葉のように育つ子どもたちの姿が伝わるおたよりだった」と思ってもらえることが手応えです。
以上です。
P.S. 小さな表現の工夫が、子どもたちの日々をより豊かに感じさせるきっかけになります。
関連記事【5月の挨拶文】仕事・私用で使える例文3選+やさしく伝わる季語
関連記事【5月の時候挨拶】手紙・ビジネスにも使える例文+好印象な書き出し
