- 「5月の挨拶文、どんな書き出しが正解なんだろう」
- 「社内と取引先で文面を変えたほうがいいのかな?」
- 「季語って入れたほうがいいのはわかるけど、どれがビジネス向け?」
この記事でわかること
- 5月にふさわしい季語や時候の挨拶表現(例:「新緑の候」「薫風の候」など)
- 上旬・中旬・下旬での使い分け方と、背景にある季節感
- 社内・社外・初対面など、相手別に適した文例と使用シーン
- 避けるべきNG表現と正しい敬語の使い方
- メールや手紙に自然に季節感を織り込むコツ
- カジュアル・おたより向け・面白い挨拶の工夫
- よくある質問+答え(Q&A形式)
5月は季節の移り変わりが大きく、表現の幅が広い時期です。
だからこそ、挨拶文に“少しの工夫”を加えるだけで、相手に与える印象が変わります。
本記事では、5月のビジネスシーンで使える季語や時候の言葉、相手別の文例、NG表現と改善案まで解説します。
型に頼るのではなく「自分らしさ」と「信頼感」が自然に伝わる一文が、誰でも書けるようになります。
心にそっと届く5月の挨拶文を、今こそ見直してみませんか?
この記事の目次
5月の挨拶文に使える季語・時候の言葉

5月の挨拶文では「季語」や「時候の言葉」を添えるだけで、印象が豊かになります。
春のやわらかさと、初夏のすがすがしさが交差するこの時期は、言葉に込められた情景も魅力的です。
たとえば「新緑の候」「若葉の候」には、木々の芽吹きと前向きな空気が宿り「立夏の候」「薫風の候」は、初夏の風を肌で感じるような臨場感があります。
下旬の「初夏の候」「麦秋の候」は、麦畑の金色や穏やかな陽射しを連想させる語です。
形式のためではなく、言葉で季節を届ける——そんな丁寧さが、ビジネスの信頼を育てます。
上旬・中旬・下旬で使い分けるポイント
同じ「5月」でも、その前半・中盤・後半では、感じられる空気が少しずつ異なります。
上旬には「若葉」「新緑」といった、生命の始まりを感じる言葉が似合います。
朝の光に照らされる新緑の街路樹を思い浮かべると、言葉の背景にも深みが増します。
中旬には「立夏」「薫風」など、空気が変わり始める季節の入り口を表す語がしっくりきます。
下旬には「初夏」「麦秋」といった、落ち着きのある初夏の成熟感が伝わる表現がおすすめです。
小さな言葉の選び分けが、文章の表情を左右します。
ビジネスにふさわしい季語の選び方
ビジネスの場では、言葉遣いひとつがその人の印象を決めることもあります。
「新緑」や「立夏」など、季節を的確に伝えつつも、誰にでもわかりやすい表現が安心です。
たとえば「立夏の候」には、夏の訪れとともに新たなスタートを感じさせる力があります。
一方で「薄暑」「牡丹匂う」など、やや文学的で受け取りにくい言葉は避けた方が無難です。
大切なのは、相手が心地よく受け取れる言葉かどうか。
信頼関係は、小さな気配りの積み重ねから生まれます。
メール・手紙に自然に盛り込むコツ
季語を挨拶文にうまく馴染ませるには、相手の表情を思い浮かべながら言葉を紡ぐことが近道です。
「新緑がまぶしい季節となりました」のように、風景と気持ちを重ねて表現すると、文章に温度が加わります。
メールでは「心地よい風が吹いてきましたね」など、少しだけ会話調にすることで親しみやすくなります。
また、文末に「季節の変わり目ですのでご自愛ください」と添えることで、締めくくりにやさしさが宿ります。
相手の立場や関係性を意識して、言葉にひと工夫を加えることが、印象を左右するポイントになります。
»【5月の手紙挨拶】知らないと損する時候表現+3つのシーン別例文
【目的別】ビジネスで使える5月の挨拶文例3つ
5月は、新緑が目にまぶしく、風が心地よくなる季節です。
そんな季節の空気を言葉に乗せて届けることで、相手に印象づける挨拶文になります。
シーンごとに適した挨拶を使い分けることで、相手との距離感を自然に縮めることができるのです。
社内向け、取引先向け、初めての連絡など、目的に合ったフレーズを上手に活用してみましょう。
1.社内向け(上司・同僚)に使える例文
社内の挨拶文は、かしこまりすぎると距離を感じさせます。
逆に、砕けすぎると信頼感を損なうこともあるため、5月らしい爽やかさを感じさせつつ、品の良さを保つのがコツです。
忙しさの中でも「気にかけていますよ」という気持ちを込めた一文は、働く仲間の心を和らげます。
【例文】
「新緑がまぶしい季節となりました。お忙しい日々が続いておりますが、どうぞご自愛ください」
「立夏を迎え、日差しも少しずつ夏の気配を帯びてきました。くれぐれもご無理のないよう、お過ごしください」
2.取引先・顧客への丁寧な文例
取引先や顧客への挨拶には、“礼儀のなかに心を宿す”ことが求められます。
5月の季節感を活かしながら、相手の繁忙や気候の変化にも思いを馳せる言葉を添えると、印象がグッと上がります。
言葉は堅くても、気持ちはあたたかく——好感を呼ぶポイントです。
【例文】
「薫風の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます」
「初夏のさわやかな陽気となりました。日頃よりご厚情を賜り、心より御礼申し上げます」
3.状況別(初めての連絡/返信など)の使い分け
相手との関係が始まる「初めてのご連絡」と、すでに関係が続く「返信や継続的なやりとり」では、挨拶文のトーンを変えるのがベストです。
初対面では慎重に、でも堅苦しすぎず。
すでに関係がある相手には、少しだけラフにして信頼を深めるのが効果的です。
【初めての連絡】
「立夏の候、突然のご連絡失礼いたします。○○の件につきまして、以下の通りご案内申し上げます」
【返信・継続】
「新緑の候、いつもご丁寧なご連絡をありがとうございます。ご返信が遅くなり、申し訳ございません」
「この言葉で始めたら、伝わる」そんなひと工夫が、挨拶文を“気持ちの届け手”に変えてくれます。
挨拶文を書くときのマナーと注意点

「文章なんて誰でも書ける」と思われがちなビジネスの世界でも、挨拶文の“ひと言”で印象は変わります。
言葉の選び方や並べ方ひとつで、相手に与える信頼感や気遣いが伝わるからです。
ときには“テンプレートっぽさ”が出てしまいがちな挨拶文だからこそ、基本を押さえつつ、自分らしい気配りを加えることが大切です。
ここでは、実際に使えるルールと一緒に、ちょっとした工夫で印象を良くするコツを紹介します。
形式・文体・敬語の基本ルール
挨拶文は、最初に目に触れる“名刺代わりの言葉”とも言えます。
文体は「です・ます」調で統一し、主語と述語をきちんと対応させるだけで、文章に安心感が生まれます。
敬語も、正しい使い分け以上に「この人はちゃんとわかってるな」と思わせる“品”が問われます。
文末がぶれない、言い回しがすっきりしている、そんな基本的なポイントが意外と印象に残るのです。
丁寧で誠実な印象は、言葉のリズムと整え方から伝わります。
避けたいNG表現と改善例
丁寧な言葉が、実は相手に失礼になっていることもあります。
たとえば「ご苦労さまです」は、上司や取引先にはNG。
また「ご一緒させていただきます」は一見丁寧ですが、二重敬語として違和感を持たれることも。
こうした表現は、まさに“言葉は生き物”だと感じる瞬間です。
ほんの少し表現を変えるだけで、文章が引き締まり「この人は信頼できる」と感じてもらえるのが面白いです。
読みやすさを意識した書き方の工夫
“良い文章”は、読み終えたあとに「すっと入ってきたな」と感じるものです。
一文を短くしたり、段落を整えたりといった“読み手への思いやり”が欠かせません。
季節のひと言や相手へのねぎらいがさりげなく入っていると、一歩先の印象を与えられます。
決まり文句に頼りすぎず、自分の言葉で味つけを加える。
工夫が、堅苦しくない、でもきちんとした文章をつくるコツです。
5月の挨拶文(ビジネス)で、よくある質問7つ
1.5月の挨拶文の書き出しにおすすめの表現はありますか?
5月の書き出しでは「新緑がまぶしい季節となりました」や「立夏を迎え、さわやかな日が続いております」などが自然です。
季節感を出すことで、やわらかな印象を与えられます。
»【5月の時候挨拶】手紙・ビジネスにも使える例文+好印象な書き出し
2.やわらかい表現で5月の時候の挨拶を伝えるには?
「木々の緑がいっそう深まる季節となりました」や「さわやかな風が心地よく感じられる頃となりました」など、直接的な季語を避けたやわらかな表現がおすすめです。
寄り添う印象を与えられます。
»【5月時候挨拶】印象が変わるやわらかい表現3選+自然に伝わるコツ
3.5月上旬にふさわしい時候の挨拶はありますか?
5月上旬には「新緑の候」や「若葉の候」が適しています。
まだ春の名残を感じられるため、やわらかく清々しい印象の語を使うと、季節の雰囲気を上手に伝えられるでしょう。
»【5月上旬の時候挨拶】いますぐ使える例文3選+季語の選び方ガイド
4.5月の挨拶文をカジュアルにしたいときのコツは?
「気持ちのよい季節になりましたね」や「日差しが夏らしくなってきました」など、日常会話に近い表現を使うと、カジュアルな印象になります。
ビジネスでも社内向けなどに適しています。
»【迷わず使える】5月のカジュアルな挨拶例文3選【気持ちが伝わる】
5.園だよりなど5月のおたよりに使える挨拶文は?
園だよりでは「園庭の緑が日に日に色濃くなってきました」や「子どもたちも初夏の陽気に元気いっぱいです」など、活動や自然の様子と組み合わせた表現が親しみやすくおすすめです。
» 5月のおたよりに使える時候の挨拶3選【自然に気持ちが伝わる書き方】
6.ちょっと面白い5月の挨拶文を入れるには?
「衣替えを前に、クローゼットが悲鳴を上げています」など、季節あるあるや自虐ネタを軽く入れると親しみやすさが生まれます。
ただし、TPOに応じた控えめさも必要でしょう。
»【5月の面白い挨拶】笑顔が生まれる一言3選×2+失敗しないコツ
7.5月下旬に適した挨拶文は何ですか?
5月下旬は「初夏の候」「麦秋の候」がよく使われます。
梅雨前の穏やかで過ごしやすい季節を表す言葉を取り入れると、落ち着いた印象の挨拶文に仕上がります。
»【5月下旬の時候挨拶】ビジネス・カジュアル例文で季節感を伝える方法
まとめ:5月の挨拶文で信頼を築こう
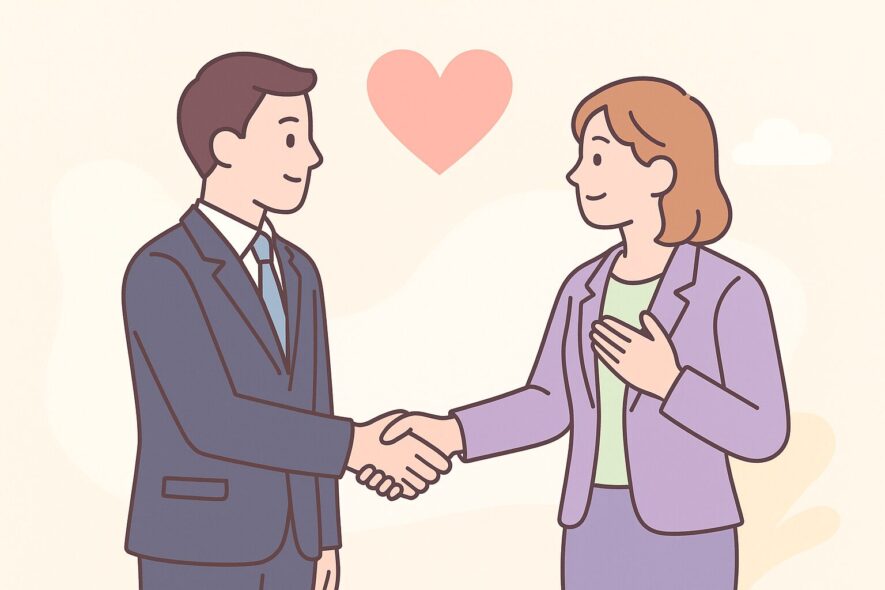
本記事では、ビジネスで信頼を得るための書き方や季語の選び方を紹介しました。
5月の挨拶文は、形式よりも「気持ちが伝わるか」が大切です。
やわらかく丁寧な言葉遣いは、相手との距離を自然に縮められます。
ポイント
- 5月は上旬・中旬・下旬で季語を使い分けるのがコツ
- 「新緑の候」「薫風の候」などは社外文にも使いやすい
- 社内向けは親しみやすさ、取引先向けは誠実さが大切
- 「ご苦労さま」などNG敬語には注意し、適切な言い換えを
- カジュアル表現やおたより向けの一文も使い分けが重要
5月の挨拶文は、単なる季節のやり取りではなく、人と人との関係をふわりとやさしくつなぐきっかけです。
- 「新緑がまぶしい季節ですね」
- 「立夏を迎え、風が心地よくなってきました」
一言が、受け手の気持ちをふっと緩めることもあるのです。
ビジネスの場であっても、そうした心配りは信頼や印象につながります。
社内向けには気遣いを、取引先には誠意を、初対面の相手には礼儀と温度感を。
マナーや敬語、文体の整い方も大切です。
それ以上に「この言葉で少しでも相手が心地よくなれば」という気持ちが伝わるかが本質です。
以上です。
P.S. たった数行の挨拶文に「自分らしさ」や「仕事への姿勢」がにじむことがあります。
関連記事【5月の季語挨拶】シーン別の例文3選【季節感を簡単に伝える方法】
関連記事5月中旬に使える時候挨拶の例文2種【自分らしい気持ちが伝わる表現】
