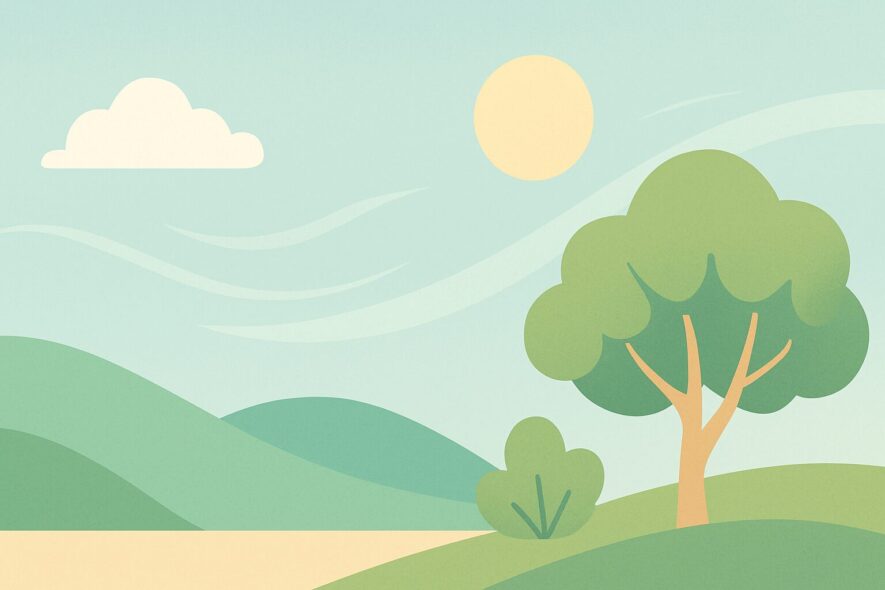- 「5月の挨拶文って、何を書けばいいのか毎回悩む…」
- 「丁寧に書きたいけど、かたすぎると逆に浮いてしまいそう」
- 「自分の言葉でやさしく季節感を伝えられたらいいのに」
この記事でわかること
- 5月の季節的特徴(春から初夏へのうつろい)と、表現にふさわしい季語・時候の言葉
- 挨拶文の使いどころ(ビジネス、おたより、家族や友人との手紙など)
- 書き出し・結びの書き方、避けたい表現
- 上旬・中旬・下旬で異なる季節感と、それに対応した言い回しの使い分け
- 場面別に使える例文と、例文に自分の言葉を加える工夫
- よくある質問+回答
5月は春から初夏へとうつろう、空気が一番やわらかな季節です。
5月の挨拶文は、形式よりも「季節感」と「相手への思いやり」を自然な言葉で届けることが大切です。
工夫で印象に残る文章になります。
本記事では、5月に使える季語や表現、書き出しや結びのコツ、用途別の例文まで、すぐに活かせる情報をまとめました。
形式にとらわれず、自分らしい挨拶が書けます。
やさしさを言葉にのせて、そっと届けられたら、何気ない挨拶文でも心に残ります。
Contents
5月の挨拶文とは?特徴と使う場面

5月の挨拶文は、春から初夏へのうつろいを感じさせる季節の便りです。
澄んだ青空、心地よい風、木々の緑が日ごとに色濃くなるこの時期は、心も自然と穏やかになります。
そんな気持ちを言葉に込めれば、相手とのやりとりにもやさしい空気が流れます。
形式としての挨拶文ではなく、相手との関係を結び直す“声かけ”として意識してみましょう。
5月にふさわしい時候の特徴
5月は、光と風がもっとも心地よく感じられる時期です。
街路樹の緑がいっせいに芽吹き、日差しがやわらかく差し込みます。
この穏やかさを伝えるには「新緑」「薫風」「風薫る」などの季語が効果的です。
こうした言葉は、ただの美辞麗句ではなく、目に浮かぶ情景や空気の温度まで想像させてくれます。
たとえば「風薫る」という表現には、初夏の訪れに気づく“音のない変化”のような美しさがあります。
どんな場面で使われるか
5月の挨拶文は、かしこまった場だけでなく、日常のやりとりにも活用できます。
「最近ご無沙汰しています」というひと言に、季節の言葉を添えるだけで、印象が変わります。
ビジネスでは、取引先との信頼関係を築くための小さな気づかいとして使われます。
プライベートでは、相手の生活リズムや心の動きに寄り添う役割を果たします。
忙しい毎日だからこそ、ふとした挨拶の中に季節が宿ると、心に余白が生まれます。
挨拶文に込めたい気持ちと印象
5月の挨拶文に込めるべきは、季節を楽しむ余裕と、相手を思いやる視線です。
年度の始まりを過ぎ、少し疲れが出やすい時期でもあります。
届く一通の手紙やメールが、相手にとっての“ひと息”になることもあります。
たとえば「若葉が陽に透けて、気持ちも明るくなる季節となりました」という書き出しには、やさしい明るさがあります。
挨拶文は文章力よりも、“あなたを気にかけています”という気持ちがにじむかどうかが大切です。
5月の挨拶文に使える季語・時候の言葉
風がやわらかくなり、陽射しに夏の気配が混じる5月。
空気を言葉で届けられたら、一通の文章に温度が宿ります。
春の終わりと初夏の始まりが折り重なる、季節の境目にあたります。
日付だけでは伝わらない「今の空気」を、季語や時候の挨拶でさりげなく表してみましょう。
上旬・中旬・下旬で異なる季節感
5月上旬、朝晩には春の涼しさが残り、風の中に名残惜しさを感じます。
この時期にふさわしいのが「晩春」「惜春」という表現です。
中旬を迎える頃には「立夏」の節気とともに、空気の輪郭がゆるやかに変わっていきます。
「新緑」「初夏」は、光と草木が躍るようなこの季節にぴったりです。
» 5月中旬に使える時候挨拶の例文2種【自分らしい気持ちが伝わる表現】
下旬になると、木漏れ日が濃くなり、風に香りが生まれます。
「薫風」「風薫る」は、その静かな変化を肌で伝えるような言葉です。
季語は単なる時期の指標ではなく、空気や気持ちまでも添える“音のない挨拶”です。
ビジネスでも使いやすい季語一覧
きちんとした印象を大切にする場面でも、5月の季語は活躍します。
形式的な文書のなかにひとこと入れるだけで、緊張がふっとゆるみます。
- 新緑の候
- 立夏の候
- 若葉の候
- 薫風の候
- 青葉の候
これらの言葉は、四季に慣れ親しんだ日本語ならではの“呼吸の余白”を作ってくれます。
伝えたいのは情報だけでなく、丁寧な姿勢や気づかいかもしれません。
日常会話や手紙で使えるやわらかい表現
少し気持ちが沈みがちな相手にも、そっと季節の話題を届けると、ふっと空が開けることがあります。
「風が気持ちよくなってきましたね」「緑が日に日に濃くなってきました」などの言葉は、何気ないけれど優しい響きを持ちます。
こうした表現は、手紙やLINE、会話の一言に自然となじみます。
難しいことを言わなくても「今、外はこんな季節だよ」と伝えるだけで、やさしいつながりが生まれます。
言葉の選び方ひとつで、気づかれないまま過ぎていく季節を心に残せます。
»【5月時候挨拶】印象が変わるやわらかい表現3選+自然に伝わるコツ
ビジネス・プライベートで使える5月の挨拶文例3選

ふだんは気に留めない“挨拶のひと言”が、意外と印象を左右することがあります。
とくに季節の変わり目には、言葉の選び方ひとつで空気がやわらぐことも。
5月の明るくやさしい季節感を、メールや手紙にそっと添えてみませんか。
ここでは、シーン別に使いやすい表現を紹介します。
1.社内向け:メールや社報の一文
忙しい朝、開いたメールに季節のひと言があるとち和みます。
堅苦しすぎず、それでいて信頼を感じさせる言葉選びがポイントです。
たとえばこんな一文はいかがでしょうか。
- 新緑がまぶしい季節となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。
- 風が心地よく、過ごしやすい日々が続いております。
- 5月に入り、業務も落ち着き始めた頃かと存じます。
たった一行でも、日々のやりとりが少し柔らかくなることを実感できるはずです。
2.社外向け:上司・取引先への手紙例文
大切な取引先や上司への手紙は、慎重になる場面だからこそ、温度のある文章が印象に残ります。
堅すぎない丁寧さと、気づかいのある季語表現が好印象をつくります。
以下の書き出しは、挨拶文に品と優しさを与えます。
- 若葉の緑が目に鮮やかな季節となりました。
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 - 立夏の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のことと拝察いたします。
- 薫風香る季節、みなさまにおかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。
「かしこまった文章は苦手」と感じる人ほど、最初の一文で空気をやわらげてみてください。
3.友人・家族向け:カジュアルな文例
ちょっとしたお礼や近況報告のついでに、季節の話題を添えると文章に温度が宿ります。
忙しい毎日のなかで「そういえば5月か」と気づく、そのきっかけにもなります。
以下はそのまま使えるやわらかい表現です。
- 新緑がまぶしくて、外を歩くのが気持ちいい季節になりましたね。
- 昼間は汗ばむくらいの日も増えてきたけれど、朝晩はまだ涼しいですね。
- 5月は気候もよくて、気持ちが少し軽くなる気がします。
書き慣れていない人こそ、自分の感じた季節のひと言を添えるだけで、言葉が生き生きと動き出します。
»【5月のビジネス挨拶文】信頼が伝わる例文3つ+時候の書き方ガイド
印象に残る書き出しと結びの工夫
メールや手紙を開いた瞬間、ふと目に留まる“季節のひと言”。
文章の空気が変わることがあります。
5月は、新緑と爽やかな風に満ちた、静かなエネルギーを感じる季節です。
やさしい空気を、文章の冒頭と締めくくりに映すことで、心に残る挨拶になります。
書き出しで季節感と配慮を伝えるコツ
書き出しは、言葉の印象が最も濃く残る場面です。
一行に、景色と気づかいを込められたら、心にすっと届きます。
たとえばこんな表現があります。
- 新緑が美しい季節となりましたが、みなさまお変わりなくお過ごしでしょうか。
- 爽やかな風が心地よい頃となりました。いかがお過ごしですか。
- 若葉がまぶしく、心も明るくなる季節を迎えました。
目に映る風景や肌に触れる風、その体感をそのまま言葉にするだけで、自然な温度が伝わります。
型にはめるより、“この季節らしさって何だろう”と想像して選ぶことが、文章の呼吸を生みます。
結びで心に残るひとことを添える方法
読み終えたあとの余韻こそが、挨拶文の“本当の伝わり方”を決める部分です。
一通の文章の締めくくりに、さりげない気づかいが添えられていたら——それはもう立派な手紙の贈り物です。
- 季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください。
- 気温差のある時期ですので、お体に気をつけてお過ごしください。
- 今後のご発展とご健康を心よりお祈り申し上げます。
丁寧であることと、やさしいことは、じつは少し違います。
その差を埋めるのが、この“ひと言”の力です。
避けたい表現・NG例
「丁寧に書こう」と思えば思うほど、言葉がよそよそしくなってしまうことがあります。
正しさや形式が強くなりすぎると、気持ちを遠ざけてしまうかもしれません。
たとえばこんな表現は、気をつけて使うのがよいです。
- ご健勝の段、慶賀の至りに存じます(かたさが前に出る)
- 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます(関係性によっては温度差を生む)
- 以上、よろしくお願い申し上げます(締めとして急に事務的)
一番伝えたいのは、あなたの“心づかい”です。
言い慣れた言葉ではなく、使いたい言葉を選んでみてください。
5月の挨拶文で、よくある質問
5月上旬の時候の挨拶に使いやすい言葉はありますか?
はい、5月上旬は春の名残と初夏の始まりが感じられる時期です。
「晩春の候」や「惜春の候」「風薫る頃」などが自然な表現として使いやすいです。
相手との関係性に応じて語調を調整すると、より印象が良くなります。
»【5月上旬の時候挨拶】いますぐ使える例文3選+季語の選び方ガイド
5月の挨拶で面白い言い回しを使っても大丈夫ですか?
カジュアルな場面では、少しユーモアを交えた表現も喜ばれることがあります。
ただし、ビジネスやフォーマルなやりとりでは、控えめにしておくと安心です。
相手との距離感や関係性を踏まえて判断するとよいです。
»【5月の面白い挨拶】笑顔が生まれる一言3選×2+失敗しないコツ
5月の挨拶文をカジュアルに書きたい場合、どんな表現が向いていますか?
「緑がきれいですね」「風が心地よい季節になりました」などの自然な一文がおすすめです。
丁寧すぎない言い回しにすることで、親しい関係でも違和感なく使えます。
LINEや手紙でも好印象を与えられます。
»【迷わず使える】5月のカジュアルな挨拶例文3選【気持ちが伝わる】
おたより用の5月の時候の挨拶にはどんな例がありますか?
保護者通信や園だよりには「新緑がまぶしい季節となりました」などが自然で親しみやすいです。
堅すぎず、園や学級の雰囲気に合った言葉を使うのがポイントです。
子どもの成長や気候の変化と合わせて季語を取り入れましょう。
» 5月のおたよりに使える時候の挨拶3選【自然に気持ちが伝わる書き方】
5月の挨拶文の書き出しにはどんな工夫が必要ですか?
書き出しには季節の情景をやわらかく表す言葉を使うと、印象がやさしくなります。
「新緑がまぶしい季節ですね」など、自然な導入が読みやすさにつながります。
相手への気づかいもそっと添えると効果的です。
»【5月の時候挨拶】手紙・ビジネスにも使える例文+好印象な書き出し
5月下旬にふさわしい挨拶文にはどんな言葉がありますか?
5月下旬は初夏の爽やかさが増す頃です。
「薫風の候」や「青葉の頃」など、軽やかで明るい印象の言葉が適しています。
気温や日差しの変化にも触れると、季節感がより自然に伝わります。
»【5月下旬の時候挨拶】ビジネス・カジュアル例文で季節感を伝える方法
5月の時候の挨拶はビジネス文書でも使えますか?
はい、ビジネスでも5月の時候の挨拶はよく使われます。
「新緑の候」「立夏の候」などが丁寧で違和感のない表現です。
手紙や案内状の冒頭に入れることで、印象を和らげる効果もあります。
»【5月の時候挨拶(ビジネス)】相手別に使える3つの好印象フレーズ
5月らしい季節の表現にはどんな言葉がありますか?
「新緑」「若葉」「薫風」「青葉」などが5月らしい季節の表現としてよく使われます。
いずれも自然の移り変わりや清々しさを感じさせる語です。
文章の雰囲気に合わせて取り入れてみると、季節感が豊かになります。
»【5月の季節挨拶】今すぐ使えるシーン別の文例+伝わる文章の工夫
まとめ:5月の挨拶文をうまく書くポイント

5月の挨拶文は、形式ではなく「相手を思う気持ち」を伝える手段です。
本記事では、5月にふさわしい季語や表現、場面ごとの使い方を丁寧に解説しました。
ポイント
- 5月の特徴は「春から初夏の移ろい」と「心地よい風や緑の深まり」
- 時候の挨拶は上旬・中旬・下旬で使い分けるとより自然になる
- ビジネス・おたより・私的な手紙では語調と季語を場面に応じて調整する
- 印象を決めるのは書き出しと結びのひと言に込める気づかい
- 例文は参考にしつつ、自分の感覚や体験を加えると温かみが増す
5月の空気を映した挨拶文は、やさしい風を届けてくれます。
コツは「文章を整える」より「声を届ける」気持ちで書くことです。
挨拶文に必要なのは、整った文型より、ひとつの“体温”です。
以上です。
P.S. 誰かの暮らしに寄り添うように、言葉で締めくくってみてください。
関連記事【5月の季語挨拶】シーン別の例文3選【季節感を簡単に伝える方法】
関連記事【5月のおたより挨拶文3選】好印象+安心感をそっと届けるひとこと