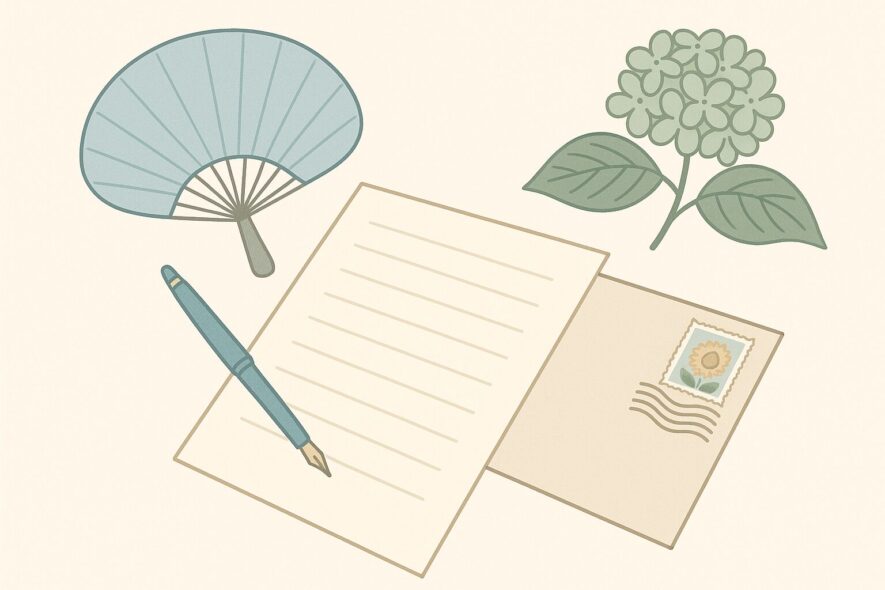- 「手紙 夏 挨拶」と検索したまま、言葉選びに迷っている
- 季節感は大事にしたいけれど、かたくなりすぎるのも避けたい
- 形式やマナーも気になるが、相手に失礼がないか不安が残る
この記事でわかること
- 時候の挨拶とは何か、その意味と役割
- 6月・7月・8月のそれぞれの「候」や季語の使い分け
- ビジネス・個人向けで異なる書き出しと結びの文例
- 挨拶文にふさわしいマナー(頭語・結語)の基本
- やわらかい印象の書き方、Q&Aでの疑問解決
夏の時候の挨拶は、相手や時期に合わせた表現で「思いやりと礼節」が伝わる洗練された手紙になります。
ビジネスでも個人宛でも「季節を大切にする日本文化」と「相手を気づかう気持ち」を言葉で表現できることがポイントです。
本記事では6〜8月の「夏の時候挨拶」について、ビジネス・個人別に「書き方と文例」を紹介します。
※ 夏のごあいさつを美しく
文面だけでなく、はがきの質感や色合いも印象を左右します。やさしい色調や余白を活かしたデザインなら、言葉がより映えます。気に入ったはがきは、暑中見舞いの時期前に用意しておくと安心です。
» 暑中見舞いはがきをAmazonで見る
夏の時候の挨拶とは何か

時候の挨拶は、日本独自の手紙文化のひとつで、四季を感じる言葉として重宝されています。
夏は気温や天候の変化が大きいため、時期に合った表現を選ぶ工夫が求められます。
「暑中お見舞い申し上げます」や「梅雨の候」といった挨拶文は、気遣いを自然に伝えられる手段です。
言葉の背景には、日本人が古くから育んできた季節感を大切にする心があります。
相手を思いやる気持ちを、季節の語句にのせて届けるのが時候の挨拶の魅力です。
「時候の挨拶」の意味と季語の役割
時候の挨拶は、単なる慣習ではなく、相手との関係性を築く大切な要素です。
日本では古来より、季節の移ろいを言葉に託し、礼節のひとつとして大切にしてきました。
たとえば「初夏の候」と書くだけで、蒸し暑さの中にも新緑の涼しさが感じられます。
含まれる季語は、短いながらも自然や情緒を読み手に伝える力があります。
季節とともに心を伝える、日本語ならではの魅力が詰まっています。
- 6月:「初夏」「梅雨の候」「向暑」
- 7月:「盛夏」「大暑」「炎暑」
- 8月:「残暑」「立秋」「晩夏」
»【7月の挨拶と季語一覧】季節感を伝える文例3選+表現のコツ
夏(6~8月)それぞれの候とは
夏の候は、単なる季節表現ではなく、気象の特徴や暮らしの変化を表す役割も持っています。
たとえば「炎暑の候」は、猛暑を表現すると同時に、体調への配慮も含む意味合いがあります。
昔の手紙では、こうした言葉を選ぶことで、相手の健康を気づかう気持ちを表しました。
また「立秋の候」は、暦の上で秋が始まる日を表し、8月上旬から使われるのが一般的です。
手紙を書くときは、季節の変化に敏感であることが丁寧な文章につながります。
- 6月:「向暑の候」「梅雨の候」「初夏の候」
- 7月:「盛夏の候」「炎暑の候」「大暑の候」
- 8月:「立秋の候」「残暑の候」「晩夏の候」
6月~8月別・時期別の書き出し文例
夏の手紙では、時期に合わせた挨拶文を選ぶことが大切です。
季節の移ろいを意識して表現を変えると、印象もやわらかくなります。
6月・7月・8月の中でも、特に時期を区切って使える表現を紹介します。
気候の特徴や暦の動きに合わせて、適切な「候」の語句を選びましょう。
6月上旬~中旬:「向暑の候」「梅雨明けの候」など
6月は春から夏への変わり目で、気温が徐々に高まり、湿気が増してきます。
この時期に適した挨拶語には、初夏の爽やかさと梅雨入りの気配を表すものがあります。
たとえば「向暑の候」は、暑さが近づいていることをやわらかく伝える表現です。
また「梅雨の候」や「入梅の候」も、湿度の高まりを表す語句として使われます。
- 向暑の候、いかがお過ごしでしょうか
- 梅雨の候、ご健勝のこととお喜び申し上げます
- 入梅の候、みなさまにはお変わりございませんか
挨拶語は「季節感と気遣い」をバランスよく伝えられます。
7月中旬:「盛夏の候」「大暑の候」など
7月中旬は、本格的な夏が始まる時期であり、日差しや気温も強まってきます。
この時期の挨拶には、暑さの厳しさを表しつつ、気づかう気持ちが込められています。
「盛夏の候」は、夏の真っただ中で使う定番表現で、力強く爽やかな印象を持たれます。
また「大暑の候」は、二十四節気の「大暑」付近に使える時期限定の表現です。
- 盛夏の候、皆様のご健康をお祈り申し上げます
- 大暑の候、暑さ厳しき折から、どうぞご自愛ください
暑中見舞いにも使える言い回しなので、季節の便りとしても活用しやすい時期です。
8月下旬:「立秋の候」「残暑の候」など
8月下旬は、暦の上では秋に入りながらも、実際には暑さが続く時期です。
「立秋の候」や「残暑の候」といった、季節の変わり目を意識した挨拶が使われます。
「立秋の候」は、二十四節気の「立秋」(8月7日頃)以降に使える表現です。
「残暑の候」は、残る暑さに配慮する意味があり、気遣いが伝わる挨拶文になります。
- 立秋の候、朝夕の風に秋を感じる頃となりました
- 残暑の候、まだまだ厳しい暑さが続いております
夏の終わりを感じさせる語句を使うことで、余韻のある表現になります。
ビジネス・個人向けの例文集

時候の挨拶は、相手との関係性によって使い分けることが大切です。
ビジネスでは格式や丁寧さが求められ、個人向けではやわらかく親しみある表現が好まれます。
ビジネスと個人、それぞれの目的に合った文例を紹介します。
使い分けのポイントを押さえることで、手紙の印象が良くなります。
ビジネス:貴社 ○○の候 ~ご健勝~
ビジネスでの時候の挨拶は、形式を重視し、適度な距離感と敬意を保つことが重要です。
特に書き出しには「貴社」や「貴店」など相手を敬う語を用いるのが基本です。
続く表現では「○○の候」として季節を示し「ますますご健勝のことと~」などと続けるのが一般的です。
- 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
- 貴社いよいよご発展のことと拝察いたします。
- 貴社ますますご繁栄の段、お慶び申し上げます。
相手企業への敬意を自然に伝えられるので、取引先や目上への書簡に適しています。
個人:暑中お見舞い申し上げます ~ご活躍~
個人宛ての手紙では、形式にとらわれすぎず、親しみやすく心のこもった表現が求められます。
「暑中お見舞い申し上げます」などの季節の挨拶に、相手の健康や近況を気づかう一文を添えるのが基本です。
暑さを労う気持ちや、会えない相手を思いやる内容が自然に含まれるようにすると好印象です。
- 暑中お見舞い申し上げます。お変わりなくお過ごしでしょうか。
- 暑い日が続きますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。
- 皆さまのご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
硬すぎず、礼儀は保たれた文面にすると、安心感を与えられます。
結びの言葉とマナーの使い分け
手紙の印象は、書き出しだけでなく「結びの言葉」でも決まります。
丁寧な挨拶で締めくくられることで「安心感や誠実さ」が伝わります。
季節や相手の立場に応じて、適切なフレーズやマナーを選ぶことが重要です。
よく使われる定型句と、頭語・結語の基本ルールについて解説します。
結びの定型句:「ご自愛ください」「ご清祥を祈る」
結びの言葉は、手紙全体の雰囲気を整え、配慮を伝えるために欠かせません。
夏の時期は、暑さへの気遣いを込めたフレーズが使われます。
よく使われる定型句は、以下です。
- ご自愛ください
- ご清祥をお祈り申し上げます
- ご健康とご多幸をお祈りいたします
「ご自愛ください」は体調を気づかう表現で、ビジネス・個人どちらにも使えます。
「ご清祥を祈る」は少しかしこまった印象があり、目上の方やフォーマルな場面で適しています。
相手との関係性に応じて、語調や丁寧さを調整することが大切です。
頭語と結語の基本ルール
手紙には「頭語」と「結語」というセットの表現があります。
正式な手紙において礼儀を整えるために必要な形式です。
たとえば、以下の組み合わせが基本です。
- 拝啓 → 敬具
- 謹啓 → 謹白
- 前略 → 草々
「拝啓」はもっとも一般的な頭語で、季節の挨拶と組み合わせやすい形式です。
「謹啓」は改まった相手に使い「前略」はやや略式な文面に使われます。
頭語を使った場合は、必ず対応する結語を文末に書くことがマナーです。
夏の手紙挨拶で、よくある質問8つ
1.時候の挨拶でやわらかい表現にするには?
やわらかい印象にしたいときは「〜の候」ではなく「暑さが続きますが…」など口語調の書き出しが効果的です。
敬語を保ちながらも、やわらかい言い回しを選ぶと読み手に親しみが伝わりやすくなります。
»【7月のカジュアルな挨拶】書き出しのおすすめフレーズ+メール短文例
2.夏終わりの時候挨拶で、2文字の表現はありますか?
「晩夏」や「残暑」など、夏の終わりを表す2文字の語が使えます。
たとえば「残暑の候」や「晩夏の候」は、8月下旬の手紙にふさわしい定型表現です。
3.夏の挨拶でビジネス向けの書き方を教えてください。
「貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」などが基本です。
「盛夏の候」や「大暑の候」といった漢語調の表現と組み合わせると、より丁寧な印象になります。
»【ビジネス向けの夏の挨拶】上司や取引先に好印象な例文とマナー集
4.7月の時候の挨拶で使える例文を教えてください。
「盛夏の候、皆様いかがお過ごしでしょうか」や「暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください」などが7月に適しています。
上旬は「小暑」、中旬以降は「大暑」「盛夏」などが一般的です。
» 7月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
5.手紙の書き出し例文にはどんなものがありますか?
「向暑の候、いかがお過ごしでしょうか」や「暑中お見舞い申し上げます」などが定番です。
形式に合わせて頭語(拝啓など)や季節の語を入れると、整った印象になります。
»【7月の季節の挨拶】書き出しと結びの使える例文集【ビジネス・私信】
6.時候の挨拶の一覧を確認したい場合はどうすればいい?
月別の「時候の挨拶 一覧」は、ビジネスマナー関連の書籍や信頼できるWebサイトで確認できます。
季節に合った漢語調や口語調の使い分けも学べるので便利です。
7.夏の時候の挨拶には、どんな表現がありますか?
「初夏の候」「盛夏の候」「残暑の候」などがあります。
6月〜8月の時期に応じて使い分けることで、季節感を伝えながら丁寧な印象を残せます。
»【7月時候の挨拶例文】ビジネス・私信で信頼と季節感を伝える言葉
8.夏の挨拶で締めの言葉には何を使えばよいですか?
「ご自愛ください」や「ご清祥をお祈り申し上げます」がよく使われます。
健康や無事を願う締め言葉は、どの相手にも失礼がなく安心感を与えられるため重宝されます。
まとめ

本記事では、6月〜8月の季節に合った言葉選びから、文例やマナーまで紹介しました。
手紙の印象は、書き出しと結びで決まるため、使う表現次第で好感度が変わります。
ビジネスと個人向けで、語調や丁寧さを調整することが信頼につながります。
ポイント
- 季節ごとに合った「候」の語句を正しく選ぶ
- ビジネスでは敬語や定型句を丁寧に使い分ける
- 個人宛には親しみやすく、心のこもった表現を添える
- 結びの言葉で相手への気遣いや配慮を伝える
- 「拝啓・敬具」など、頭語と結語の正しい組み合わせを守る
夏の手紙では、季節感を大切にした言葉選びが印象に残ります。
時候の挨拶や結びの一文は、手紙全体の雰囲気を整える要素です。
6月から8月にかけては気候の変化が大きいため、時期に応じた語句を使い分けることが重要です。
以上です。
P.S. 相手や目的に応じて、表現を柔軟に使い分ける意識が求められます。
関連記事【夏の挨拶文例まとめ】6月〜8月に好印象を与える言葉集+使い方
関連記事【7月の挨拶文】上旬・中旬・下旬で迷わない季語と文例の正しい使い方