- 7月らしい時候の挨拶を手紙やメールに入れたいけど、言葉選びに迷う
- ビジネスにもカジュアルにも使える表現をうまく使い分けたい
- 季語の意味や使い方がわかれば、もっと印象に残る文章が書ける気がする
この記事でわかること
- 7月に使える季語(時期別・用途別)
- 関係性に応じた使い分け(ビジネス・私用など)
- メールや手紙の書き出し・結び・暑中見舞いの例文
- 季語の意味やニュアンス、選び方のポイント
- よくある質問と答え(Q&A形式)
7月の挨拶文には「気配りや季節感」を自然に伝える工夫が求められます。
ただ、梅雨明け前と夏本番では雰囲気が異なり、どんな言葉がふさわしいか迷うものです。
本記事では「7月挨拶の季語」を軸に、初旬から下旬までの季語を時期や用途別に整理しました。
フォーマルとカジュアルの使い分けや、すぐ使える例文・注意点も紹介しています。
季語の意味や選び方が分かれば、言葉に自信が持て、相手との関係も深まります。
7月に使える季語一覧

7月の季語には、梅雨の余韻と夏本番の兆しが同居しています。
手紙やメール、挨拶文に季語を取り入れることで、相手に自然な季節感が伝わります。
この章では、時期別・用途別に使える季語を紹介し、選び方の参考になるよう解説します。
初旬〜中旬にふさわしい季語
7月初旬から中旬は、まだ梅雨が明けきらない地域も多く、湿気や雨に関連した季語がよく使われます。
また、徐々に暑さが増していくため、夏の始まりを感じさせる言葉も選ばれます。
- 長雨(ながめ)
- 半夏生(はんげしょう)
- 青葉風(あおばかぜ)
- 雲の峰(くものみね)
「長雨」は梅雨の続く様子を端的に表し「青葉風」は木々を渡る初夏の風を思わせます。
季語を挨拶文に添えることで、季節の空気を丁寧に伝えられます。
»【7月初旬の時候の挨拶】おすすめ季語と迷わない言葉+伝わる気遣い
下旬や梅雨明け以降に使える季語
7月下旬になると、全国的に梅雨が明けて本格的な夏が訪れます。
日差しや暑さ、涼を求める気配が増す時期です。
- 炎暑(えんしょ)
- 涼風(りょうふう)
- 夏の雲(なつのくも)
- 金魚(きんぎょ)
「涼風」は夏の中の涼を象徴し、暑中見舞いにもよく使われます。
「金魚」は夏祭りや風鈴と並ぶ季節の風物詩として、親しみやすい表現です。
»【夏祭りの挨拶例文集】開会・閉会・司会の言葉がすぐ整うテンプレ
ビジネス・フォーマル向けの季語
改まった手紙やビジネス文書では、落ち着きと礼節が伝わる季語が好まれます。
相手への配慮が自然に伝わるよう、使われる言葉には慎重さが求められます。
- 小暑(しょうしょ)
- 盛夏(せいか)
- 猛暑(もうしょ)
- 大暑(たいしょ)
たとえば「盛夏の候」は、7月中旬から下旬に多用される時候の挨拶です。
夏の盛りを落ち着いた語調で伝えることで、文章全体の印象も安定します。
»【迷わない7月中旬の時候挨拶】小暑・盛夏の候の使い方+書き出し例
私用・カジュアル向けの季語
親しい人への手紙やSNS投稿では、やわらかく親しみのある季語が適しています。
自然や日常の一場面をやさしく描くことで心地よく感じられます。
- 蝉時雨(せみしぐれ)
- 花火(はなび)
- かき氷(かきごおり)
- 風鈴(ふうりん)
「風鈴の音に涼を感じる毎日です」といった文は、日常と季節が自然につながる表現です。
堅苦しくならずに、季節を共有する気持ちが伝わります。
季語を使った挨拶文例3選
季語を挨拶文に取り入れると、文章に品や季節感が加わります。
かしこまった手紙にも、カジュアルなメールにも、自然なかたちで季語を添えることで、読み手との距離感をちょうどよく保てます。
書き出し・結び・暑中見舞いなどの実用的な文例を紹介しながら、季語の使い方をわかりやすく解説します。
1.メールや手紙の書き出し例
書き出しに季語を添えると、文章全体が柔らかくなり、印象も上品にまとまります。
定型文でも、ひと工夫加えることで自分らしい挨拶に変えられます。
たとえば以下の書き出しが考えられます。
- 青葉風が心地よい季節となりました。
- 長雨の続く日々、いかがお過ごしでしょうか。
- 盛夏の候、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
季語を取り入れると、季節の空気を感じさせる表現になり、形式的になりすぎず自然な印象を与えられます。
2.結びの言葉に使える季語表現
文末に季語を加えると、季節の余韻が残り、丁寧な気配りを感じてもらえます。
とくに相手の健康を気遣う場面では、自然な締めくくりとして効果的です。
- 蝉の声に夏を感じる毎日です。どうぞご自愛ください。
- 炎暑の折、くれぐれもご無理なさいませんように。
- 涼風が待ち遠しいこのごろ、健康にてお過ごしください。
日常にある季節の風景をさりげなく入れることで、心温まる印象を残せます。
3.暑中見舞いでの使い方と注意点
暑中見舞いでは、梅雨明けから立秋前までの期間に季語を交えて夏の挨拶を送ります。
丁寧な言葉とともに、涼やかさや健康を気遣う表現を心がけましょう。
- 盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか。
- 酷暑のみぎり、ご自愛のほどお祈り申し上げます。
- 涼を求める季節、皆さまのご健康を心より願っております。
なお「暑中見舞い」は立秋前まで「残暑見舞い」は立秋以降に出すのが一般的です。
暦に沿った使い分けを意識することで、品のある印象を与えられます。
7月らしさを伝える表現のコツ
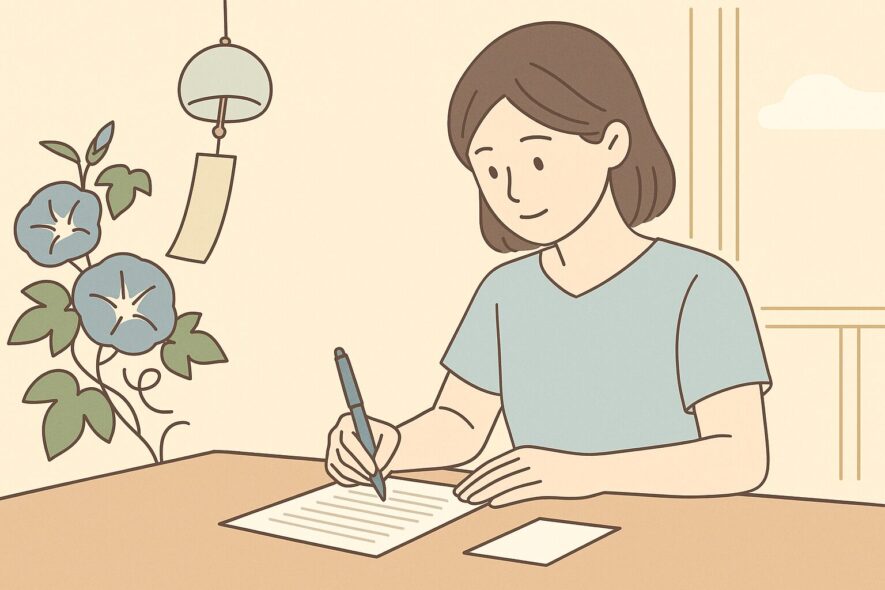
7月は梅雨明けと夏本番のはざまで、気候や雰囲気が日ごとに変化します。
微妙な移ろいを挨拶文にうまく取り入れるには、季語の意味やニュアンスを正しく理解することが大切です。
また、相手や状況に応じた言葉選びが、心のこもった表現につながります。
7月らしい表現をより効果的に伝えるための具体的な工夫を紹介します。
季語の意味とニュアンスの理解
季語には、自然の情景や日本人の感性が込められています。
単なる季節の表現にとどまらず、感情や思い出を呼び起こす力があります。
たとえば「青葉風」は、新緑を揺らす風のさわやかさと、初夏の明るさを連想させます。
- 「涼風」→ 暑さの中に一瞬の涼を感じる風
- 「蝉時雨」→ 連なる蝉の声が降り注ぐように聞こえる様子
- 「夕立」→ 急に訪れる夏の強い雨、情緒や迫力を演出
季語のもつ意味や雰囲気を理解することで、文章がより豊かに感じられます。
季節の移り変わりに配慮する
7月は、地域や年によって季節の進み方が異なることがあります。
天候や気候の状況に合わせて季語を選ぶことが重要です。
たとえば、梅雨明け前に「炎暑の候」と書くと違和感を与えてしまいます。
- 梅雨が続くとき→「長雨」「半夏生」など
- 梅雨明け直後→「涼風」「青葉風」など
- 夏が本格化→「炎暑」「蝉時雨」など
季節のずれを読み取りながら、リアルタイムの空気感を反映させた言葉選びが、相手への気配りになります。
»【7月の季節の挨拶】書き出しと結びの使える例文集【ビジネス・私信】
相手に合わせた言葉選びの工夫
挨拶文は、相手との関係性や文脈に応じて表現を調整することで、より伝わりやすくなります。
たとえば、改まった相手には格式ある言葉を、親しい相手にはやさしい季語を使うと、文章が自然に響きます。
- 取引先や上司→「盛夏の候」「大暑の折」など
- 家族や友人→「花火」「風鈴」「かき氷」など
- 目上でも少し親しみを込めたい→「涼風」「青葉風」など
相手に合わせた言葉を選ぶことで、文章に「あなたを思って書きました」という想いが伝わります。
7月の挨拶季語で、よくある質問8つ
1.7月の時候挨拶の例文にはどんなものがありますか?
7月の時候の挨拶例文としては「盛夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」や「青葉風の吹く季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか」などが一般的です。
書き出しの季語は、梅雨明けや夏の到来を意識して使い分けましょう。
» 7月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
2.7月の挨拶をカジュアルに表現するには?
カジュアルな7月の挨拶には「暑くなってきましたね。体調は崩されていませんか」や「風鈴の音が心地よい季節ですね」といった言い回しが適しています。
気取らずに、季節の風景をやさしく描くのがポイントです。
»【7月のカジュアルな挨拶】書き出しのおすすめフレーズ+メール短文例
3.7月の時候挨拶で使える花の名前はありますか?
7月の挨拶に使える花には「朝顔」「蓮」「桔梗」「百日紅(さるすべり)」などがあります。
暑さのなかでも凛と咲く姿が季節感を引き立て、挨拶文の冒頭や結びに彩りを添えてくれます。
»【7月の時候挨拶】花を組み合わせた好印象な例文+使い方のポイント
4.7月上旬にふさわしい時候の挨拶はありますか?
7月上旬はまだ梅雨明け前の地域もあるため「長雨が続いておりますが」「半夏生を迎え」など、しっとりとした季節感を表す挨拶がよいでしょう。
湿度や雨をテーマにすると自然です。
»【7月上旬の時候の挨拶】ビジネス・プライベートで好印象を残す例文
5.7月下旬に使える時候の挨拶の文例はありますか?
7月下旬は夏本番を迎える時期なので「炎暑の候」や「盛夏の候」といった挨拶が適しています。
また「蝉しぐれが響く毎日です」なども、情景が伝わりやすく印象に残ります。
»【7月下旬の時候の挨拶】酷暑・大暑の候で印象アップする例文まとめ
6.時候の挨拶一覧はどこで確認できますか?
時候の挨拶一覧は、ビジネスマナー本や手紙の書き方サイト、または国語辞典などで確認できます。
月ごとに整理された形式のものが多く、7月にふさわしい季語や例文も掲載されています。
7.8月にも使える時候の挨拶はありますか?
8月に使える時候の挨拶には「立秋の候」「残暑の折」などがあります。
立秋を境に「暑中見舞い」から「残暑見舞い」に切り替えるのが慣例で、季節の移ろいを意識した挨拶が好まれます。
8.ビジネスで使える7月の時候の挨拶とは?
「盛夏の候」「小暑の候」などがあります。
形式的になりすぎないよう、季語のあとに「ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」と添えると丁寧で品があります。
»【7月のビジネスの時候挨拶】上旬〜下旬の例文+使い分け完全ガイド
まとめ:7月の季語で印象に残る挨拶を

7月の挨拶に季語を添えることで「季節感と温かみ」が加わります。
本記事では、時期や相手に応じた季語の選び方や使い方をわかりやすく解説しました。
手紙やメール、ビジネス文書など、あらゆるシーンで役立つ表現が身につきます。
重要ポイントまとめ
- 7月は「梅雨明け」と「夏本番」の間にあり、季語の使い分けが重要(天気や時期に注意)
- 季語には気候だけでなく、感情や風景のニュアンスが込められている(背景理解が大切)
- 書き出し・結び・暑中見舞いなどでの使用例を押さえると実用的(すぐに使える)
- 相手や場面に応じて、フォーマル/カジュアルな表現を使い分ける(伝わり方が変わる)
- 地域の天候に配慮し、自然な印象を与える言葉を選ぶ(思いやりが伝わる)
季語は、日本語ならではの美しさを持ち、心に寄り添う力があります。
7月の気配を感じながら、相手を思う気持ちをひとことに込めてみてください。
印象に残るやさしい挨拶になります。
以上です。
P.S. 工夫で、印象が変わり、思いが伝わります。
関連記事【7月時候の挨拶例文】ビジネス・私信で信頼と季節感を伝える言葉
関連記事【7月の挨拶文】上旬・中旬・下旬で迷わない季語と文例の正しい使い方
