- 8月にふさわしい時候の挨拶を知りたい
- ビジネスや手紙で使える例文を探している
- 暦の知識や結びの言葉まで気が回らず、不安
この記事でわかること
- 8月上旬・中旬・下旬にふさわしい時候の挨拶文例(漢語調/口語調)
- ビジネス用・プライベート用での使い分けポイント
- 挨拶の結び表現と、健康や繁栄を願う言い回しのパターン
- 立秋・処暑の暦の意味と時期
- よくある質問+回答
8月の時候の挨拶は、上旬・中旬・下旬の季節感や暦(立秋・処暑)をふまえて、相手や場面にふさわしい表現を選ぶことが大切です。
漢語調と口語調を使い分け、以下で文章に「品と好印象」を与えられます。
- ビジネスで:敬語や定型
- プライベート:柔らかく親しみやすい語り口
本記事では、8月上旬・中旬・下旬の時候挨拶を、漢語調・口語調の両面から紹介します。
立秋や処暑といった暦の意味だけでなく、文章に深みをくわえるポイントも整理しました。
定型に頼らずとも、相手や場面に応じた書き出し・結びが選べます。
※手書きもいいけれど、印刷なら「きれい・早い・失敗なし」
暑中見舞いや残暑見舞いを送るなら、デザイン豊富で仕上がりが美しい「日本最大級の挨拶状印刷専門店」がおすすめです。パソコンやスマホから簡単に注文でき、最短翌日発送で間に合います。
この記事の目次
8月上旬の時候の挨拶(漢語調・口語調)

8月上旬は、真夏の厳しい暑さが続く時期です。
暑中見舞いや手紙の冒頭で使う「時候の挨拶」も、季節感を意識した表現が好まれます。
ビジネス文書ではかたい印象の漢語調、親しい間柄ではやわらかな口語調など、相手との関係性に応じて使い分けるのが基本です。
8月上旬にふさわしい漢語調と口語調の時候の挨拶を紹介します。
漢語調:「盛夏の候」「猛暑のみぎり」など
8月上旬に使われる代表的な漢語調の時候の挨拶には「盛夏の候」や「猛暑のみぎり」があります。
フォーマルな文書やビジネスレターなどで使われる定型的な挨拶表現です。
「盛夏」は夏の最盛期を意味し「みぎり」は「ころ」「時期」という意味をもつ言葉です。
つまり「盛夏の候」は「夏真っ盛りの時期にあたり」という意味になり、文章の書き出しとして季節感を端的に伝えられます。
実際の使用例としては、以下のような文が一般的です。
- 盛夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
- 猛暑のみぎり、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
漢語調を使うことで、礼節を大切にする気持ちが伝わり、信頼感につながります。
口語調:「蝉時雨の降りそそぐ夏…」など
口語調の時候の挨拶では、日常の情景や体感をそのまま文章に取り入れる表現がよく使われます。
たとえば「蝉時雨の降りそそぐ夏」という表現は、夏の風物詩である蝉の声を詩的に描写し、季節の移ろいをやわらかく伝えています。
口語調は、親しい相手やカジュアルな手紙、メールでのやりとりに適しています。
堅すぎない印象を与えたいときに役立ちます。
使用例としては、以下のような一文が挙げられます。
- 蝉時雨の降りそそぐ夏となりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
- うだるような暑さが続いておりますが、みなさま変わりありませんか。
情景を交えた言葉選びによって、季節感と親しみが伝わります。
8月中旬(立秋以降)の適切な挨拶表現
8月中旬は、暦のうえでは秋の始まりとされる「立秋」を迎えた後の時期です。
とはいえ、実際には猛暑が続いており、夏の終わりというよりも暑さのピークとも言える時期です。
時候の挨拶では「暦の上では秋だが、暑さは続いている」というニュアンスをうまく伝える必要があります。
立秋を過ぎた時期にふさわしい漢語調と口語調の表現を紹介します。
漢語調:「立秋の候」「残暑の候」「残炎の候」
8月中旬に使える漢語調の時候の挨拶には「立秋の候」「残暑の候」「残炎の候」などがあります。
「立秋の候」は、暦のうえで秋を迎えたことを端的に伝える表現です。
「残暑の候」「残炎の候」は、引き続き厳しい暑さが続いていることに配慮し、相手の体調を気づかう意味を込めた言い回しです。
使用例は以下のとおりです。
- 立秋の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
- 残暑の候、みなさまにおかれましてはご健勝のことと存じます。
- 残炎の候、日々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
礼儀を大切にしながら、相手を気づかう姿勢を伝えられます。
口語調:「暦の上では秋となりましたが…」など
立秋を過ぎても厳しい暑さが続く8月中旬では、口語調の挨拶が温かみを持たせます。
たとえば「暦の上では秋となりましたが、暑さはなお厳しく感じられます」など、暦と体感のずれをやわらかく表現する言い回しが好まれます。
暑さが続くなかでの思いやりや気づかいが自然に伝わります。
たとえば、以下の表現が使えます。
- 暦の上では秋となりましたが、暑さはなお厳しく感じられます。
- 立秋を過ぎても真夏のような陽気が続いています。
口語調は相手との距離を縮め、やさしい印象を与えたい場面で役立ちます。
8月下旬(処暑・初秋の頃)の挨拶文例

8月下旬は、二十四節気の「処暑」を迎え、暦の上でも秋が少しずつ近づいてくる時期です。
日差しは強くても、朝夕の風や虫の声に秋の気配が感じられることもあります。
季節の変わり目にふさわしい時候の挨拶では、暑さをねぎらいながらも、秋の訪れをほのかに伝える表現が好まれます。
8月下旬に適した漢語調と口語調の挨拶文例を紹介します。
漢語調:「処暑の候」「初秋の折」など
8月23日頃の「処暑」は、暑さが少し和らぎ始める節目として知られています。漢語調の時候の挨拶には「処暑の候」や「初秋の折」などがあります。
「処暑の候」は「暑さが収まりつつある時期にあたり」という意味をもつ表現で、相手の健康を気づかう文脈に自然になじみます。
「初秋の折」は、秋の入り口を意識した上品な言い回しで、落ち着いた印象の文面に適しています。
使用例としては、以下の文があります。
- 処暑の候、皆様にはいよいよご清祥のことと拝察いたします。
- 初秋の折、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。
丁寧さと季節感をあわせ持つため、ビジネス文書でも使いやすい言い回しです。
口語調:「虫の声に秋の気配を感じ…」など
夜になると聞こえてくる虫の音に、秋の気配を感じ始めるのが8月下旬です。
自然の移ろいを描いた口語調の挨拶は、心にやさしく届きます。
「虫の声に秋の気配を感じるようになりましたね」といった表現は、季節と心の距離を近づけてくれます。
使用例としては、以下の文があります。
- 虫の声に秋の気配を感じるようになりましたが、まだまだ日中は暑さが残ります。
- 朝夕の風に涼しさを覚えるようになりました。お変わりありませんか。
口語調は、季節の情景をまじえながら自然体で気づかいを伝えたいときに重宝されます。
文例を選んだら、そのまま印刷で仕上げられます
住所録取り込みや宛名印刷にも対応の「挨拶状ドットコム」なら、仕上がりが安定します。自宅プリンターのトラブルが不安な方にも便利です。
ビジネス向けとプライベート向けの使い分けポイント
時候の挨拶は、文章の冒頭に季節感を添えるだけでなく、相手との関係性に応じた言葉選びが求められます。
ビジネスとプライベートでは、表現のトーンや文体に違いがあります。
敬意や親しみが適切に伝わるように、それぞれの文調の特徴を理解して使い分けることが大切です。
ビジネス文とプライベート文の使い分けポイントを見ていきます。
ビジネス文:敬語・定型表現中心
ビジネス文における時候の挨拶では、定型的な表現と丁寧な敬語が基本となります。
相手の立場や関係性を踏まえて、堅実で礼儀正しい印象を与える文面を意識します。
たとえば「猛暑の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます」などは、慣用句として広く使われています。
以下のポイントが重要です。
- 漢語調の定型表現を使う(例:「〜の候」「〜のみぎり」など)
- 相手の繁栄・健康を気づかう文言を入れる
- 敬語や謙譲語を適切に使う
礼儀を重んじた文章は、信頼関係の維持にもつながります。
プライベート文:季節感・口語表現を活かす
プライベート向けの挨拶では、より自然な表現で季節感を伝えることが重視されます。
かたい言い回しよりも、気持ちや情景が伝わるような口語表現が好まれます。たとえば「毎日暑い日が続いていますが、元気に過ごしていますか?」といった文がよく使われます。
使い分けのポイントは、以下のとおり。
- 情景描写を取り入れた口語表現を使う
- 相手の近況や体調への気づかいを自然に書く
- メールやLINEなどカジュアルな文面に対応できる
自然体で書かれた挨拶は、相手との関係をよりあたたかく保つ助けになります。
結びの挨拶の例文集
時候の挨拶は、書き出しだけでなく結びの言葉も大切です。
8月のような暑さの厳しい季節には、健康への気づかいや繁栄を願う表現が文章の印象を左右します。
最後のひと言で、相手への思いやりや配慮が伝わるようなフレーズを選びましょう。
健康と繁栄を祈る定型文、自愛をうながすやさしい結び文を紹介します。
健康と繁栄を祈る文(例:「ご健康を祈念」など)
ビジネス文や改まった手紙では、相手の健康や会社の発展を願う結び文がよく使われます。
形式的でありながらも、敬意や配慮を感じさせます。
「ご健勝とご発展をお祈り申し上げます」「ご自愛とご多幸をお祈りいたします」などが代表的なフレーズです。
内容に応じて使い分けると、文章の印象が豊かになります。
よく使われる例は以下のとおりです。
- 皆様のますますのご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。
- 貴社のご発展と皆様のご健勝をお祈りいたします。
- 今後のご繁栄とご健康を祈念いたします。
結びに入れることで、内容に関わらず、誠実な印象を残せます。
自愛を促す結び(例:「どうかご自愛ください」など)
親しい人への手紙やカジュアルなメールでは、相手の体調をいたわるひと言で結ぶと自然です。
「くれぐれもご自愛ください」「体調を崩されませんように」など、やさしく心のこもった表現が多く用いられます。
書き手の気づかいが感じられる言葉は、印象にも残りやすいです。
以下の文がよく使われます。
- 厳しい暑さが続きますので、どうかご自愛ください。
- ご多忙のことと存じますが、どうぞご無理なさいませんように。
- 夏の疲れが出やすい時期ですので、お身体にはお気をつけください。
やわらかな結び文は、無理をさせない気づかいが伝わります。
暦(立秋・処暑)とは?時期の目安ガイド
時候の挨拶では、暦の節目を正しく理解して使うことが重要です。
たとえば「立秋」や「処暑」といった言葉は、8月の手紙やメールで頻繁に使われますが、具体的にどの時期を指すのか曖昧なまま使っている人も少なくありません。
立秋と処暑の意味や時期、使いどころの目安をわかりやすく解説します。
立秋(8月7日頃)とは
立秋は、二十四節気のひとつで、毎年8月7日頃にあたります。
この日を境に、暦のうえでは夏が終わり秋が始まるとされています。
ただし、実際には猛暑が続くことも多く「立秋の候」などの挨拶文を使う際には体感とのギャップに配慮が必要です。
たとえば、立秋の前までは「暑中見舞い」、立秋以降は「残暑見舞い」に切り替えるといったマナーがあります。
以下の場面で使われます。
- 8月7日以降のビジネス文書で「立秋の候」を使う
- 時候の挨拶を「盛夏」から「残暑」へ変える
- 暑中見舞いの送付は立秋までを目安にする
季節の区切りを大切にする日本人の感覚が「立秋」という言葉に込められています。
処暑(8月23日頃)とは
処暑は、立秋の約2週間後、8月23日頃に訪れる二十四節気です。
「暑さがおさまる」という意味があり、暦のうえでは夏の終わりにあたる節目です。
ただし、近年の気候ではまだ真夏のような日も多く「処暑の候」といった表現には実際の気温をふまえた配慮が求められます。
使い方の目安は以下のとおりです。
- 8月23日以降の挨拶文で「処暑の候」を使う
- 「残暑の候」と併用する際は気候や相手に応じて調整する
- 秋の訪れを感じさせる内容とあわせて使う
暑さの中でも秋を感じさせる表現を届けたいときに「処暑」は効果的な言葉です。
8月の時候挨拶の例文で、よくある質問8つ
1.8月上旬の時候の挨拶にはどんな例文がありますか?
8月上旬の時候の挨拶には「盛夏の候」や「猛暑のみぎり」などがよく使われます。
暑さの厳しさに触れつつ、相手の体調を気づかう表現が適しています。
»【8月上旬の時候の挨拶】相手別の使える文例集+好印象を残す書き方
2.おたよりで使える8月の時候の挨拶にはどんな表現がありますか?
「蝉しぐれの降りそそぐ毎日です」「夏空がまぶしく感じられるこのごろ」といった自然描写を含む挨拶が、おたよりでは親しみやすく好まれます。
» 8月時候の挨拶とおたより例文集【園・学級・ビジネス別のテンプレ】
3.ビジネス文書で使える8月の時候の挨拶はありますか?
ビジネスでは「盛夏の候」「残暑の候」「立秋の候」などの漢語調が適しています。
形式的ながらも礼儀正しい印象を与えるため、安心して使えます。
»【8月時候の挨拶ビジネス】上旬・中旬・下旬の正しい例文+NG回避法
4.8月下旬の時候の挨拶ではどのような表現がよいですか?
8月下旬は「処暑の候」「初秋の折」などが適しています。暑さをねぎらいながらも、秋の気配をほのかに伝える表現が自然で好印象です。
5.カジュアルな8月の挨拶にはどんな書き方がありますか?
「毎日暑いね、元気にしてる?」など、会話に近い表現がカジュアルな挨拶には向いています。
体感温度や日常の様子を織り交ぜると自然です。
»【8月のカジュアル挨拶】上旬・中旬・下旬に合わせた書き方+例文集
6.8月上旬の時候挨拶の例文を教えてください。
「盛夏の候、皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます」という文は、8月上旬のビジネスシーンでよく使われる定型例です。
7.8月中旬の時候の挨拶にはどんな言葉を選べばいいですか?
8月中旬は立秋を過ぎるため「残暑の候」「立秋の候」などが適切です。
暑さが続いている点に配慮した文にすると好印象を与えられます。
»【8月中旬の時候の挨拶完全ガイド】残暑・立秋に迷わない例文まとめ
8.9月にも8月の時候の挨拶を使ってもよいですか?
9月に入っても初旬であれば「残暑の候」などは使えます。
ただし、秋の訪れを意識した表現に切り替える方が季節感に合って自然です。
まとめ
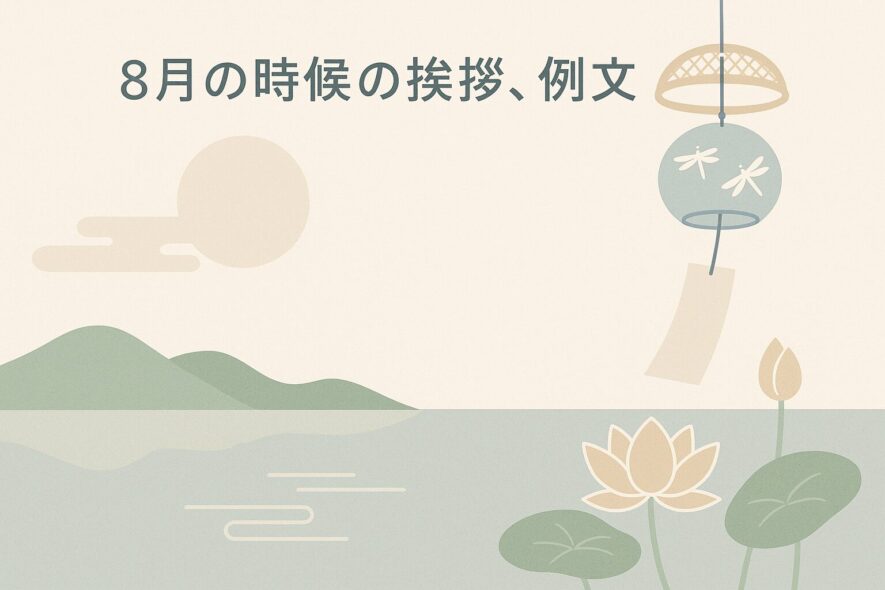
本記事では、8月の時期ごとにふさわしい時候の挨拶表現や、ビジネス・プライベートでの使い分けを解説しました。
8月の時候の挨拶は、季節感だけでなく相手との関係性に応じた言葉選びが重要です。
以下に、押さえておきたい要点を整理します。
- 8月上旬は「盛夏の候」「猛暑のみぎり」など、暑さの最盛期を意識した表現が適切
- 8月中旬は「立秋の候」「残暑の候」など、暦と実際の気候の差に配慮した言い回しが必要
- 8月下旬は「処暑の候」「初秋の折」など、秋の気配を伝える挨拶が好ましい
- ビジネス文では漢語調と敬語を使い、格式ある印象を大切にする
- プライベート文では口語調や情景描写を活かし、自然体で親しみを込める
- 結びの言葉も、健康や繁栄への願い・体調を気づかう表現を使い分ける
- 「立秋」「処暑」など暦の節目を理解することで、表現選びの精度が上がる
今のうちに自分なりの言葉を整理しておくことで、メールや手紙で好印象を与えられます。
季節の挨拶は、信頼や心遣いを伝える第一歩です。
言葉が整ったら、仕上げはプロ品質の印刷で
季節限定デザインも選べる「挨拶状ドットコム」で、好印象の一枚を用意できます。
いま作成して、相手に届くタイミングを整えられます。
以上です。
P.S. 必要な場面ですぐに使えるよう、文例をストックしておくのもおすすめです。
関連記事【8月の季節の挨拶】暑さに気遣う言葉とシーン別の例文集+マナー
関連記事【8月の時期ごとの時候挨拶の基本】ビジネス・プライベート向け文例
