- 8月にふさわしい挨拶文の書き出しや例文、候語・口語の選び方を知りたい
- ビジネスとカジュアルで印象を損なわずに使える文章を短時間で作成したい
- 季節や敬語の不整合を避け、相手に安心感と好印象を与えたい
この記事でわかること
- 上旬・中旬・下旬別の適切な候語や口語の選び方
- ビジネス用とカジュアル用での語調・構成の違い
- 冒頭と末尾の統一感を保つためのルール
- 立秋後や処暑後に避けるべきNG表現と置換方法
- メール・はがき・掲示など媒体別の文調調整方法
- 季節語・情景語を使った印象的な締め方
- 即使える用途別テンプレや例文の活用法
8月の挨拶文は、暦の節目に沿って書き出しと結びをそろえることで、短くても印象的で失礼のない文章になります。
上旬・中旬・下旬ごとの候語や口語の選び方、ビジネスとカジュアルの語調の違い、避けたいNG表現や置換方法を押さえれば、相手や場面に合った文を迷わず作れます。
本記事ではメール・はがき・社内掲示など用途別のテンプレや例文も掲載しているため、読むだけで即実践が可能です。
暦に沿った言葉選びと整った構成は、受け取る相手に安心感と好印象を与えます。
この記事の目次
基本ルール:8月の挨拶文作成の要点
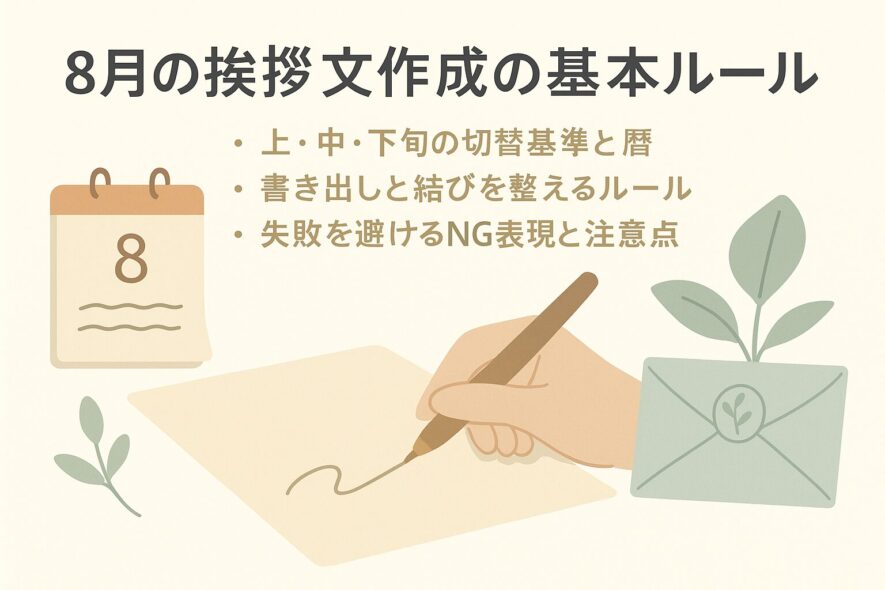
8月の挨拶文は、暦の節目を手がかりに語調を選ぶと安定します。
上旬は盛夏を示し、中旬は立秋、下旬は処暑へ移る流れを押さえます。
相手が取引先なら敬意を厚めに、親しい相手なら口語で温度感を整えます。
書き出しと結びの語感をそろえると、短文でも印象が引き締まります。
迷ったら季節語を口語に置換し、体調への配慮を添えて仕上げます。
- 手順:用途を決める→暦の段階を確認→語調を選ぶ→結びを合わせる。
上・中・下旬の切替基準と暦
切替は上旬の盛夏、中旬の立秋、下旬の処暑を軸に据えます。
暦を基準にすれば、地域差や気温差があっても表現がぶれにくいです。
上旬は「盛夏の候」、中旬は「残暑の候」、下旬は「初秋の候」を選びます。
季語が硬い場合は「暑さが続く折」「朝夕に涼しさが出る頃」へ置換します。
判断に迷う場面では、暦の移ろいを優先して決めます。
- 上旬例:暑さが続く折、みなさまのご健勝をお祈りします。
- 中旬例:残暑が続く折、みなさまのご健康を願っています。
- 下旬例:朝夕の涼しさが芽生える頃、変わらぬご厚誼に感謝します。
ビジネス/カジュアル文体の違い
ビジネスは要点先行で敬語を通し、信頼と読みやすさを両立させます。
カジュアルは近況への共感を先に置き、語尾を柔らかく整えます。
社外や年長者には「お祈りします」などを用い、落ち着いた余韻を残します。
友人や同僚には「ご自愛ください」などで親しみを添えます。
段落内で語調を混在させず、統一します。
- ビジネス例:残暑の折、みなさまのご健勝をお祈りします。
- カジュアル例:暑さが続きますので、どうぞご自愛ください。
- 避けたい例:敬語とタメ口の交互使用。
書き出しと結びを整えるルール
冒頭と末尾の温度感を合わせると、短い挨拶にも芯が通ります。
残暑を述べるなら体調配慮で締め、初秋なら再始動を励ます結びにします。
口語へ置換しても、方向性をそろえれば印象は安定します。
不整合は読み手の解釈を散らし、内容の記憶を弱めます。
下の組合せ例を叩き台にして選びます。
- 残暑の候 ⇄ みなさまのご健勝をお祈りします。
- 初秋の候 ⇄ 新たな季節の実りを願っています。
- 避けたい例:涼感の書き出しと酷暑の結びの併用。
8月上旬の挨拶(例文付き)
8月上旬は盛夏の実感が強く、落ち着いた書き出しが合います。
候語は「盛夏の候」「炎暑のみぎり」、口語は「暑さ厳しき折」が基軸です。
社外や年長者には礼節を厚めに、親しい相手には口語で温度感を添えます。
短文テンプレを基に、用件と結びの整合を意識して仕上げます。
体調配慮の一言を添えると、読み手の行動に寄り添えます。
- 手順:用途を決める→候語か口語を選ぶ→用件を一文→体調配慮で締める
- 置換例:盛夏の候⇄暑さ厳しき折/炎暑のみぎり⇄強い日差しが続く頃
ビジネス用の短文テンプレ
礼節ある冒頭と体調配慮の結びを一対にすると、印象が安定します。
候語が硬い場面は「暑さ厳しき折」へ置換し、要点を先に置きます。
社名や部署の直後に用件を簡潔に添えると、読み手の負担が減ります。
語尾は「お祈りします」「お過ごしください」で統一します。
- 平素よりお世話になっております。盛夏の折、みなさまのご健勝をお祈りします
- ご高配に御礼申し上げます。酷暑の折、どうかご自愛ください
- 日頃のご厚情に感謝いたします。暑さ厳しき折、皆様のご発展をお祈りします
- ご支援に御礼申し上げます。炎暑の折、変わらぬご健勝をお祈りします
親しい相手用カジュアル例
季節の景色と短い気づかいで、負担なく受け取れる挨拶に整えます。
候語は使わず、口語で実感を共有し、柔らかな依頼形で締めます。
同じ段落で敬語とタメ口を混在させず、語調をそろえます。
一文で完結させ、読み終わりの余韻を残します。
- 暑い日が続きます。みなさまがおだやかに過ごせますように
- 日差しが強い頃です。休めるときに休んでください
- セミの声がにぎやかです。水分を忘れずに過ごしてください
- 夏の空がまぶしい時期です。おからだをいたわってください
上旬の体調気遣い結び文
暑さを前提に、無理を避ける選択を静かに促す結びが要点です。
盛夏の書き出しには、休息と補給を自然に薦める表現がなじみます。
相手の予定を縛らない言い回しで、広く届く配慮を心がけます。
命令形は避け、願いの形でやわらかく締めます。
- 暑さ厳しき折、みなさまのご健勝をお祈りします
- 炎暑のみぎり、おからだを大切にお過ごしください。
- 強い日差しが続きます。どうかご無理のないよう願っています
- 暑気が募る頃です。水分を意識して、健やかな日々をお祈りします
8月中旬(立秋以降)の挨拶文

8月中旬は立秋後の残暑期で、体感と暦がずれやすい時期です。
書き出しは「残暑の候」や「残暑が続く折」を起点に整えます。
社外や年長者は端正に、親しい相手は口語で温度感を添えます。
お盆や夏休みは負担を想定し、短い共有と配慮にとどめます。
結びは体調と移動を気づかい、再始動を静かに支えます。
- 手順:用途を決める→候語か口語を選ぶ→近況一文→体調配慮で締める。
「残暑の候」等の置き換え例
候語は端正、口語は体感寄りです。
相手の慣れと場面で硬さを調整します。
迷ったら下の置換表から選びます。
- 残暑の候 ⇄ 残暑が続く折
- 晩夏の候 ⇄ 夏の名残を感じる頃
- 初秋の候 ⇄ 朝夕に涼しさが出る頃
- 立秋の候 ⇄ 秋の気配を感じる頃
お盆・夏休み話題の挿入方法
近況は一文で共有し、返信や移動の負担に配慮します。
業務案内は別段落に分け、読み手の集中を保ちます。
言い切り過ぎず、選択の余地を残します。
- お盆期はご多忙と存じます。みなさまのご健勝をお祈りします
- 夏休みの折、移動が続く方も多いかと思います。どうぞご自愛ください
- 暑さが厳しい時期です。休める折に休んでいただけますと幸いです
- 再開後のご連絡で差しつかえありません。無理のない範囲でお願いいたします
»【お盆の挨拶言葉の完全ガイド】静かなお盆と初盆の例文・マナー集
中旬の結びテンプレ
残暑を前提に、健康と再始動に寄り添う言葉で締めます。
候語で始めた場合は、端正な語尾で落ち着かせます。
口語で始めた場合は、柔らかな願いの形でまとめます。
- 残暑厳しき折、みなさまのご健勝をお祈りします
- 暑さの続く頃です。おからだを大切にお過ごしください
- 移動が重なる時期です。道中のご安全を心より願っています
- 再始動の折、無理なく進められる日々でありますように
8月下旬(処暑以降)の挨拶文
処暑を過ぎると、日中は暑くても朝夕に軽い涼しさが混じります。
書き出しは初秋寄りへ移し、語感を軽やかに整えると安定します。
社外や年長者は端正な語尾、身近な相手は口語でやわらかく締めます。
業務は別段落で簡潔に分け、結びで体調と再始動を支えます。
- 手順:候語か口語を選ぶ→用件の密度を決める→結びで体調配慮。
「初秋・早涼」などの使い分け
涼感の段階で語を選ぶと、読み手の肌感覚に寄り添えます。
初秋は移ろい、早涼は朝夕の軽い涼しさ、新涼は澄んだ空気感を示します。
晩夏は名残の雰囲気を保ちたい場面に向きます。
- 初秋の候 ⇄ 朝夕に涼しさが出る頃
- 早涼の候 ⇄ 日中は暑いが、朝夕にやわらぐ頃
- 新涼の候 ⇄ 空気が澄み、涼しさが際立つ頃
- 晩夏の候 ⇄ 夏の名残を感じる頃
メール/はがき別の文調調整
媒体の性格に合わせ、密度と余韻を設計します。
メールは要点先行、はがきは景色先行で、読み手の負担を軽くします。
語尾は関係性で統一し、段落内のトーンを崩さないようにします。
- メール手順:候語または口語→感謝→用件→体調配慮
- はがき手順:季節の景色→近況ひとこと→消息→体調配慮
- 例(メール):初秋の候、平素より感謝いたします。確認のみお願いします
- 例(はがき):早涼の候、夕風が心地よく感じられる頃です
下旬向け結び文テンプレ
残暑と初秋の間を見据え、健康と歩調を守る言葉で締めます。
休息や補給、安全な移動、緩やかな進行を短く添えます。
冒頭の涼感と方向をそろえ、読み終わりの余韻を落ち着かせます。
- 朝夕の涼しさが出る頃です。みなさまのご健勝をお祈りします
- 残暑の名残が続きます。おからだを大切にお過ごしください
- 移動の機会が増える時期です。道中のご安全を願っています
- 再始動が続く折です。無理のない歩調で進められますように
失敗を避ける:NG表現と注意点
季節や敬語の不整合は、短文でも違和感を生みます。
立秋以降は残暑や初秋の語感に合わせ、書き出しと結びをそろえます。
敬語は尊敬・謙譲・丁寧の役割を分け、重ねを避けます。
コピペ前に、季節語と語尾の統一を点検します。
たとえば「残暑の候」で始めたら、体調配慮で穏やかに締めます。
下の要点を順に確認すると、安全に仕上げられます。
立秋後に「猛暑の候」はNG
立秋後は「猛暑の候」を避け、残暑や初秋の語へ切り替えます。
暦に合わせると、相手の季節感とずれにくくなります。
立秋後は「残暑の候」「残暑が続く折」を軸にします。
処暑以降は「初秋の候」「朝夕に涼しさが出る頃」も選べます。
判断は気温ではなく、暦の段階を基準にします。
- NG:立秋後の「猛暑の候」
- OK:立秋後の「残暑の候」「残暑が続く折」
- OK:処暑以降の「初秋の候」「朝夕に涼しさが出る頃」
重複や敬語の調整ポイント
敬語は混在を避け、冗長な語尾を減らします。
尊敬と謙譲の同時使用は控え、依頼表現は一本化します。
同趣旨の語を重ねず、段落ごとに語調を固定します。
- 二重敬語:「お越しになられる」→「お越しになる」
- 依頼の一本化:「ご連絡いただけますか」または「ご連絡ください」
- 冗長削除:「お願い申し上げますの件」→「お願いします」
- 語尾統一:です・ます調を段落内で統一
コピペ前に確認すべきこと
最初に、季節・敬語・固有名の3点を点検します。
次に、媒体差と差出情報を整え、読後感をそろえます。
最後に、候語と口語の切替で温度感を合わせます。
- 季節語:立秋以降は残暑・初秋系へ切替。結びと対応
- 敬語:尊敬・謙譲の混在回避。二重敬語を除去
- 媒体:メールは要点先行。はがきは景色一言
- 固有名:人名・社名・日付・部署を確認
- 差出情報:肩書・連絡先を最新に
- 読後感:体調配慮で穏やかに締める
即使える:用途別テンプレ集
挨拶文は媒体と相手に合わせ、密度と語調を変えると伝わりやすいです。
社外メールは要点先行、社内掲示は安全配慮、はがきは情景の一言が軸です。
20〜40字と60字の目安で文例をそろえ、短時間で活用できる形にします。
書き出しの季節感と結びの温度感をそろえると、印象が安定します。
社外メール用20~40字例文
礼節ある冒頭と体調配慮の結びを一対にすると、印象が安定します。
社外は信頼と可読性が重要で、短い文が負担を減らします。
残暑や初秋の語感で端正にまとめ、用件は別段落で示します。
- 残暑の折、みなさまのご健勝をお祈りします
- 立秋の頃、平素のご厚情に御礼申し上げます
- 朝夕に涼しさが出る頃です。どうぞご自愛ください
- 初秋の候、変わらぬご高配に感謝いたします
- 残暑が続く折です。無理のない歩調でお過ごしください
社内掲示用ショート文
情報と配慮を短く並べ、誰にでも届く語を選びます。
暑さ対策と業務の連絡は分けて示し、語尾はやわらかく統一します。
- 暑さが続きます。水分と休憩をこまめに確保してください
- 移動が多い時期です。道中の安全にご留意ください
- 冷房の設定は共有の目安に合わせてください
- 体調に不安がある場合は、早めに担当へお知らせください
はがき向け60字例文
季節の景色と相手への気づかいを一息で届けます。
残暑と初秋の間を意識し、穏やかな結びでまとめます。
- 残暑が続く折、みなさまが健やかに過ごせますよう願っています
- 朝夕に涼しさが出る頃となりました。どうぞおからだを大切に
- 初秋の気配をおぼえる頃です。無理のない歩調でお過ごしください
- 夏の名残を感じる日々です。みなさまのご多幸をお祈りします
8月の挨拶文の書き出しで、よくある質問
1.8月の時候挨拶の例文は、どんな書き出しが基本ですか?
基本は季語+配慮の一文です。
「盛夏の候」「炎暑のみぎり」などを冒頭に置き、続けて「皆さまのご健勝をお祈りします」と結ぶと端正に整います。
口語なら「暑さが続く折」も自然です。
2.8月上旬の時候の挨拶は何を使えば自然ですか?
8月上旬は夏の盛りを前提にします。
「盛夏の候」「炎暑のみぎり」が無難で、口語は「暑さ厳しき折」が使えます。
業務メールでは挨拶→感謝→用件→体調配慮の順に短く示します。
»【8月上旬の時候の挨拶】相手別の使える文例集+好印象を残す書き方
3.8月の挨拶をカジュアルにする場合、どの程度砕いてもよいですか?
カジュアルは季節の実感を一言添えると程よい距離感になります。
「暑い日が続きます。水分を忘れずに」などの口語で十分です。
相手との関係が近ければ、近況を一文足してもよいでしょう。
»【8月のカジュアル挨拶】上旬・中旬・下旬に合わせた書き方+例文集
4.8月の時候の挨拶(ビジネス)では、どんな書き出しが無難ですか?
ビジネスでは端正さを優先します。「残暑の候」「立秋の候」など暦に沿う語が安心です。
硬さを和らげたい時は「残暑が続く折」を用い、結びで体調を気づかうと好印象ですね。
»【8月時候の挨拶ビジネス】上旬・中旬・下旬の正しい例文+NG回避法
5.8月上旬の時候の挨拶の例文をいくつか教えてください。
例文は「平素よりお世話になっております。盛夏の候、皆さまのご健勝をお祈りします」の型が使えます。口語なら「暑さ厳しき折」へ置換すると親しみが増すかもしれません。
6.8月下旬の時候の挨拶は、何を選ぶと季節感が合いますか?
下旬は残暑と初秋が交差します。「初秋の候」「早涼の候」が合い、口語は「朝夕に涼しさが出る頃」です。書き出しが涼感なら、結びも穏やかな配慮語で合わせると自然です。
7.8月中旬の時候の挨拶のコツはありますか?
中旬は立秋後の残暑期です。「残暑の候」「立秋の候」を軸にし、口語は「残暑が続く折」が使いやすいです。
お盆や夏休みの多忙にふれつつ、無理のない対応を願うと届きます。
»【8月中旬の時候の挨拶完全ガイド】残暑・立秋に迷わない例文まとめ
8.8月上旬の時候の挨拶(ビジネス)の書き出しを教えてください。
上旬のビジネスは簡潔が鍵です。「盛夏の候」や「炎暑のみぎり」で始め、感謝→用件→体調配慮の順に一文ずつ。長文化を避け、敬語を一本化すると読みやすいでしょう。
参考:季節語一覧とリンク集

季節語は暦と体感の差をつなぐ道具です。
候語は端正に、口語は肌感覚に寄せて調整します。
置換の軸を持ち、同じ温度感で結びまでそろえます。
公式情報を定点観測し、年ごとに更新します。
下の早見表と話題語、参照先で短時間に整えられます。
候語と口語の早見表
候語⇄口語の対で持つと、相手や媒体に合わせて選べます。
季節の段階に応じて、硬さと温度感を微調整します。
下の置換表から近い温度感を選びます。
- 盛夏の候 ⇄ 暑さが続く折。
- 炎暑のみぎり ⇄ 強い日差しが続く頃。
- 残暑の候 ⇄ 残暑が続く折。
- 晩夏の候 ⇄ 夏の名残を感じる頃。
- 初秋の候 ⇄ 朝夕に涼しさが出る頃。
- 早涼の候 ⇄ 日中は暑いが朝夕にやわらぐ頃。
- 新涼の候 ⇄ 空気が澄み涼しさが際立つ頃。
- 立秋の候 ⇄ 秋の気配を感じる頃。
季節トピック語(花火・赤とんぼ)
情景語を一言添えると、短文でも印象が残ります。
花火や赤とんぼなど、地域差が少ない語を選びます。
業務連絡は別段落に分け、余韻を保ちます。
- 花火:夜空の明かりが続く頃です。みなさまのご健勝をお祈りします。
- 赤とんぼ:夕暮れに赤とんぼを見かける時期です。どうぞご自愛ください。
- ひぐらし:ひぐらしの声が涼しさを連れてくる頃です。穏やかにお過ごしください。
- 入道雲:入道雲の背が高い頃です。水分を忘れずにお過ごしください。
- 夕風:夕風が心地よく感じられる頃です。無理のない歩調でお過ごしください。
参照用リンク集(毎年更新)
公式窓口を起点にすると、判断が安定します。
年度更新や構成変更に備え、定期点検します。
下に定点として便利な窓口を並べます。
- 国立天文台 暦計算室:https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/
- 気象庁:https://www.jma.go.jp/
- 文化庁:https://www.bunka.go.jp/
- 国立国語研究所:https://www.ninjal.ac.jp/
- 日本郵便:https://www.japanpost.jp/
- NHK:https://www.nhk.or.jp/
以上です。
