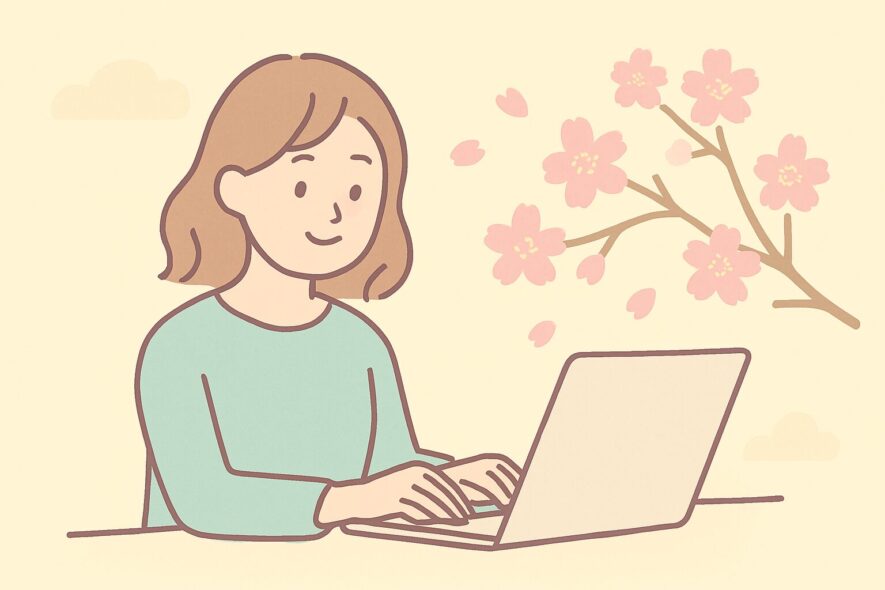- 「4月下旬って、どんな時候の挨拶を使えばいいんだろう?」
- 「ビジネスでも失礼にならない表現が知りたい」
- 「できればかたい印象じゃなくて、自然でやさしい文章にしたい」
この記事でわかること
- 4月下旬の気候や季節感に合った「晩春」「惜春」などの季語
- ビジネス・学校・親しい人向けなど、シーン別の例文と使い分け
- 時候の挨拶に続く文章のつなぎ方、トーンの使い分け、避けたい表現
- よくある疑問(句読点、文末表現、使える時期など)と回答
4月下旬の時候の挨拶は、季節感や相手への気づかいを込めることで、定型文以上の印象を与えられます。
本記事では、4月下旬にふさわしい季語や表現、ビジネス・学校・カジュアルといったシーン別の例文、文章のつなぎ方や注意点まで紹介します。
シーンや相手に合わせた自然な表現を選べば、心のこもった挨拶が書けます。
Contents
4月下旬の時候の挨拶とは?

「もう春も終わりか…」そんな空気を感じるのが4月下旬です。
この時期の挨拶は、ただ形式として書くだけでなく、季節の移ろいを感じ取るやさしさがにじむと印象が変わります。
手紙やメールに季節の言葉をひとこと添えるだけで、文章に温度が生まれます。
難しそうに感じるかもしれませんが、自然の変化に目を向けると表現のヒントは意外と身近にあります。
心を軽くほぐすような、あたたかな一文を意識してみましょう。
4月下旬の季節感と気候の特徴
あなたのまわりでも、桜の花びらが消え、緑の風景が広がっていませんか。
4月下旬は、春から初夏への切り替わりを感じるちょうど境目です。
日中は薄着でも過ごせるようになり、朝晩はまだ少しひんやりしています。
その寒暖差が、なんだか春の名残を惜しんでいるようにも感じられます。
こんな時期だからこそ、自然の変化を表現に取り入れると、相手に伝わりやすい挨拶になります。
時候の挨拶に使える季語・言葉
「晩春」「惜春」などの季語は、春の終わりの静けさや余韻を感じさせます。
一方で「新緑」「若葉」は、これから訪れる初夏のいきいきとした景色を想像させます。
たとえば「春風に若葉がそよぐ季節となりました」という表現には、やさしい時間の流れが感じられます。
言葉は不思議で、たった一行でも季節や気持ちを伝える力があります。
「心に浮かぶ風景」を言葉にすると、共感を得やすくなります。
»【4月の季語で挨拶が変わる】自然に伝わる例文+やさしい言葉の選び方
ビジネス・手紙など使用シーンの違い
同じ「時候の挨拶」でも、誰にどう伝えるかで選ぶ言葉は変わります。
ビジネスの相手には、安心感のある定型文が喜ばれます。
一方で、親しい人には、自然な会話に近いあいさつの方が気持ちが伝わりやすいです。
「最近の気候、気持ちよくなってきましたね」でも、季節を感じてもらえます。
相手の顔を思い浮かべながら綴るだけで、文章の温度が自然と変わってきます。
4月下旬に使える時候挨拶の例文3選
春の名残と初夏の気配が入り混じる4月下旬は、どこか物思いにふけるような季節です。
そんな時期の時候の挨拶は、決まり文句にとどまらず、感じた空気を一言に込めるだけで印象が変わります。
「きれいな言葉を使う」以上に「気持ちが伝わる」を意識してみましょう。
ビジネス・プライベート・学校向けの例文を紹介しながら、使い方のコツをお伝えします。
フォーマルなビジネスメール例文
ビジネスの文章に季節感を添えると、無機質な印象がやわらぎます。
特に春の終わりには「次の季節もよろしく」という前向きな気配をそっと忍ばせるのが効果的です。
- 晩春の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます
- 惜春の折、みなさまにおかれましてはご健勝のことと拝察いたします
- 新緑がまぶしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか
たとえば「晩春の候」には、静かな落ち着きと、長く続く信頼関係を想起させる力があります。
形式に沿いながらも、その季節らしい「空気感」を意識すると、心に残る一文になります。
親しい相手へのカジュアル文例
「そろそろ半袖でも平気かな」
ささやかな季節の変化を共有できるのが、カジュアルなあいさつの良さです。
- 最近は日中も暖かくなってきましたね。春ももうすぐ終わりですね
- 新緑のまぶしい季節になりました。そろそろ半袖が気持ちよく感じられる日もあります
- 桜もすっかり散って、次はどこへ出かけようかと楽しみにしています
かしこまりすぎず、でも相手のことを考えていると伝わる「微妙なバランス」が心地良さです。
挨拶文に悩んだら、自分が感じている季節の変化を素直に書き出すのもひとつの手です。
学校・保護者あての手紙文例
先生からの手紙やおたよりの冒頭には、たった一行の季節のあいさつが安心感をもたらします。
慌ただしい日々のなかで「季節を感じる一文」に心が緩むこともあります。
- 春も深まり、新緑の美しい季節となりました。保護者のみなさまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか
- 桜の花が散り、若葉が目にまぶしい時期となりました。新年度もどうぞよろしくお願いいたします
- 春風の心地よい季節となりました。日々のお力添えに、心より感謝申し上げます
こうした文の中には、単なる時候の挨拶以上に、先生の心配りやあたたかなまなざしが感じられます。
読み手が「読んでよかった」と思える手紙には、ちいさな共感が必ずあります。
時候の挨拶のあとに続ける文の工夫

季節の挨拶をきれいに書けたのに、そのあとの文章で手が止まった経験はありませんか。
言葉のつなぎ方ひとつで、文章全体の雰囲気や読みやすさは変わります。
相手に合わせた語調、自然な話の流れ、使うべきでない言葉への配慮。
3つを意識するだけで、挨拶文は印象深くなります。
相手に合わせたトーンの使い分け
同じ内容でも、語調によって伝わり方はまったく変わります。
たとえば、堅い印象を避けたいときに「ご無沙汰しております」より「お久しぶりです」の方がやわらかく感じられます。
反対に、失礼のないやりとりを求められる場面では、定型的でも丁寧な言葉が安心感につながります。
相手にとって心地よい言葉選びをするには「この文を自分が受け取ったらどう感じるか」と考えるのがコツです。
少し視点を変えるだけで、言葉にやさしさや品が加わります。
違和感のない自然な文章構成
「さて、話題を切り替えよう」と思ったとき、文章がぎこちなくなることがあります。
意識したいのは“間”をつくること。
たとえば「桜もすっかり散りましたね。さて、本題に入りますが〜」のように、季節の話題と本題の間に空気を含ませると、読者も構えずに読めます。
手紙やメールも、会話のようなリズムがあると読みやすくなります。
「言葉をつなぐ」だけでなく「場をつくる」つもりで一文を考えてみましょう。
避けたい表現・注意点
一見丁寧でも、読み手によっては冷たく感じる言葉もあります。
「お元気そうでなによりです」や「ご多忙とは存じますが」は、典型です。
意図せず相手の状況を前提にしてしまうことで、距離を感じさせる原因になります。
挨拶文は、相手の体調や忙しさを気づかうより「季節を一緒に感じる」ような言葉にすると、受け手にやわらかく伝わります。
思いやりは、言葉の内容よりも、選び方に表れます。
よくある質問とその回答(Q&A)
「これで合ってるかな?」
時候の挨拶を書いていると、ふと手が止まることはありませんか。
意味は知っていても、使い方や言葉選びに迷うのは自然なことです。
ここでは、4月下旬の時候の挨拶にまつわる“よくある疑問”にやさしく答えていきます。
つまずきやすいポイントを確認しておくと、自信をもって文章を整えられます。
4月下旬は「晩春」でいいの?
「4月も下旬だけど、“春”って言っていいのかな?」
結論からいうと「晩春」で大丈夫です。
暦のうえでは、春は立春から立夏の前日までとされていて、4月下旬はその終盤にあたります。
俳句や手紙でも「晩春」「惜春」といった言葉が使われ、この時期を丁寧に表現する言葉として定着しています。
ただ、地域によっては初夏の陽気を感じることもあるため「新緑」「若葉」などに言い換えるのも自然です。
景色に合わせて、言葉を選んでみましょう。
ビジネスメールでも使える?
「ビジネスメールに時候の挨拶って、ちょっと固い気がする…」
実は効果的です。
メールの冒頭にひとこと添えるだけで、やわらかな印象を与えられます。
たとえば「晩春の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、格式ある定型文としてよく使われます。
親しい取引先には「新緑が気持ちよくなってきましたね」のように、少しカジュアルな表現もおすすめです。
関係性や文面のトーンに合わせて、ちょうどよい挨拶を選ぶと自然に馴染みます。
句読点や文末表現はどうする?
「この文、最後に“。”をつけるべき? それともつけないのが正しいの?」
こんな細かい疑問が気になって、手が止まることもあります。
ビジネス文書では、時候の挨拶の末尾に句点を打たないのが慣例です。
少し堅めの印象を与えることで、文全体が引き締まって見えるためです。
ただし、メールや社内向けのやわらかい文章なら、句点をつけても問題ありません。
文末の言葉は「ご自愛ください」「お喜び申し上げます」など、丁寧で穏やかなものを選ぶと印象が良いです。
迷ったときは「自分が読み手だったらどう感じるか」で考えてみると答えが見つかります。
4月下旬の時候挨拶で、よくある質問
4月時候の挨拶にはやわらかい表現を使ってもいいですか?
はい、やわらかい表現は親しみやすさを演出するうえで効果的です。
ビジネス以外の場面では「春風が心地よい季節になりましたね」など、自然体な言い回しもおすすめです。
相手との関係性を意識して選ぶと、好印象につながるでしょう。
» 4月のやわらかい時候挨拶の例文まとめ【好印象を与える3つのコツ】
4月の時候挨拶はビジネスでも使えますか?
もちろん使えます。
「晩春の候」「新緑の候」などは、ビジネスメールの冒頭にも適しています。
相手や業種によって堅さを調整すれば、丁寧かつ自然な印象を与えられます。
»【4月のビジネス挨拶文】社内外で信頼を得る言葉選び+書き方テンプレ
4月の挨拶はカジュアルでも大丈夫ですか?
カジュアルな挨拶も、相手との関係性に応じて選べば問題ありません。
たとえば「暖かい日が増えてきましたね」など、やわらかい言葉を選ぶと自然な印象になります。
形式にこだわりすぎず、気持ちを込めて伝えることが大切です。
» 4月のカジュアルな挨拶文例集3つ【丁寧すぎない自然な挨拶のコツ】
4月の時候の挨拶は学校向けでも使えますか?
学校や保護者あてのおたよりなどにも使われます。
「春も深まり、新学期の慌ただしさも少し落ち着いた頃かと存じます」などが好例です。
丁寧で親しみのある文体を心がけるとよいです。
»【4月の時候挨拶】学校ですぐ使える例文3選+伝わる先生になるコツ
4月の初めにはどんな言い方が合いますか?
4月初めは「春暖の候」や「陽春の候」という表現が適しています。
桜の開花や新年度の始まりに触れた表現も自然です。
相手に春の雰囲気が伝わるような言葉を選びましょう。
»【4月上旬の時候の挨拶】手紙・メールですぐに使える表現+例文集
春の挨拶は3月に使うのが正しいですか?
3月も春の挨拶が使える時期です。
「早春の候」「春寒の候」など、季節の始まりを表す言葉が向いています。
気候や地域に合わせた表現を選ぶのがポイントです。
»【春の挨拶文の書き方】ビジネス・手紙・メール例文集+NGフレーズ
4月中旬に使える時候の挨拶には何がありますか?
4月中旬には「春爛漫の候」「花冷えの候」などがよく使われます。
桜や春の花に触れた表現も多く、柔らかく華やかな印象になります。
相手に季節の美しさを届けるような言葉がおすすめです。
»【4月中旬の時候の挨拶】3つの例文で迷わず書ける【やさしい印象】
3月に使える時候の挨拶でやわらかい表現はありますか?
はい「日差しがやわらかくなってきましたね」「春の足音が近づいてきました」などが自然です。
ビジネス以外のやりとりには、季節感のあるカジュアルな言い回しがよく合います。
気軽な挨拶に季節の情緒を添えると印象がやわらぎます。
»【3月の時候の挨拶】やわらかい表現のコツ+シーン別の例文3選
まとめ:季節感のある挨拶で印象アップ

4月下旬の時候の挨拶は、春から初夏への季節感を言葉で伝える大切な表現です。
相手や場面に応じた語調や言い回しを工夫することで、印象は変わります。
本記事では、下記を解説しました。
- 4月下旬は「晩春」「惜春」といった季語が自然に使える時期
- ビジネス・学校・親しい相手など、使用シーン別の例文を紹介
- 時候の挨拶のあとに続く自然なつなぎ方と表現のコツを解説
- 「やわらかい表現」や「句読点・文末のマナー」などもQ&A形式で解決
- 季節の空気感をのせるだけで、文章の印象がやさしくなる
4月下旬は、春の終わりと初夏の入り口が重なる、微妙で美しい時期です。
季節の変わり目だからこそ、丁寧に言葉を選ぶことで、心にやさしく届く一文になります。
たった一文でも、季節を感じる言葉が添えられているだけで、文章全体にぬくもりが生まれます。
以上です。
P.S. 空気を逃さず、心のこもった一文を届けてみましょう。
関連記事【4月の挨拶文の書き出し】ビジネス・プライベートで使える例文
関連記事4月の時候挨拶の結びで使える例文【言葉選びのポイント+NG表現】