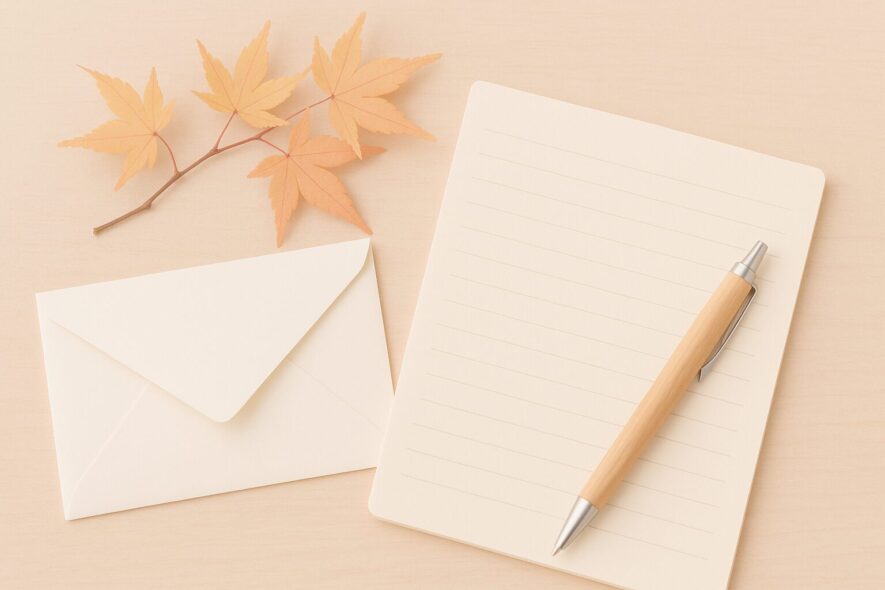広告 11月
【11月初旬の時候挨拶】時候句リスト+そのまま使える3行テンプレ
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
2.11月の時候挨拶をビジネスで使うときの注意点は?
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
2.11月の時候挨拶をビジネスで使うときの注意点は?
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
2.11月の時候挨拶をビジネスで使うときの注意点は?
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
2.11月の時候挨拶をビジネスで使うときの注意点は?
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
- 11月初旬の時候の挨拶、晩秋と初冬のどちらを使えばいいのか迷う
- 立冬前後の表現が難しく、相手に違和感を与えない言葉を選びたい
- ビジネスでも私的でも、自然で丁寧な文章に整えたい
この記事でわかること
- 11月初旬に使うべき「晩秋語」「初冬語」の選び方と切り替え時期
- ビジネス・学校・私的文など、媒体別の文調と使い分け
- 立冬前後や地域差による季節ズレの対処法
- 三行テンプレやカジュアルな結び表現など、すぐ使える実例
- 時候の挨拶を体系的に整える具体的な判断手順
- よくある質問+回答
11月初旬の時候の挨拶は、季節の変わり目ゆえに判断が難しい時期です。
暦の上では秋が終わりを迎える一方で、地域や天候によってはまだ暖かさが残ります。
本記事では、そんな曖昧な季節にも迷わず整う「時期判定→語句選定→媒体→結び」の3ステップを解説します。
二十四節気を基準にしつつ、届く時期の気温や地域差を反映することで、自然で心のこもった挨拶文が書けるようになります。
ビジネス・学校・私的など、どの場面でも印象よく使える表現が身につきます。
11月初旬の基礎知識と時期判定

結論は、時期判定→語の選定→媒体の型の3ステップで決めると迷いが減ります。
境目の時期は判断が割れやすく、順序を決めるほどぶれが小さくなるからです。
例として、配達日と地域を先に確定し、晩秋語と初冬語を候補に並べ、最後に冒頭と結びの温度感を合わせます。
読み手の体感と文章の温度がそろい、自然な印象で受け取られます。
- Step1: 配達日と地域を確定
- Step2: 晩秋語と初冬語を2〜3語ずつ選定
- Step3: 冒頭と結びの温度感を一致
11/1〜6は晩秋系 11/7〜は立冬系
届く日が11/1〜6なら晩秋語、11/7以降なら初冬語を基本線にします。
受け取る日の体感に語を合わせると、自然に読めるからです。
例では、前半は「晩秋の候」「暮秋の候」、後半は「向寒の候」「初冬の候」を軸にします。
配達日が境目をまたぐ場合は、本文で温度を補い、結びで健康気遣いを丁寧に入れます。
- 前半: 晩秋の候 / 暮秋の候
- 後半: 向寒の候 / 初冬の候
- 境目は配達日を優先して微調整
二十四節気の考え方と注意点
節気は土台、仕上げは直近の気温と生活実感です。
数字の目安だけでは、地域の差や寒暖の波に追いつけないからです。
例として、立冬週でも日中が暖かい地域は、急な寒さ表現より「朝夕が冷える」を置くと自然です。
逆に冷え込みが強い地域では、初冬語を少し早めても整います。
- 節気は「目安」、年や地域で前後
- 最高気温と朝晩の冷えで補正
- 生活実感に寄せて語を選ぶ
初旬と上旬の言い換えと運用
語感で選び、規程や慣例がある場面は表記に合わせます。
表記の統一が読み違いを防ぎ、やりとりを円滑にするからです。
例では、事務文は「上旬」、私的文は「初旬」を選び、本文では季節語を主役に据えます。
日付は括弧で補助に回すと、受け手が全体像をつかみやすくなります。
- 事務は上旬、私的は初旬が無難
- 季節語を主役、日付は補助
- 既存の書式があればそれに合わせる
使える時候句リスト(意味と目安)
11月初旬は、晩秋から冬への移り変わりを感じる時期です。
前半は秋の余韻を表す語、後半は寒さを意識する語が合います。
時候句を使い分けることで、相手に季節感と心配りを伝えられます。
この章では「晩秋」「暮秋」「残菊」「立冬」「向寒」「深秋」の6語を中心に、意味と使いどころを整理します。
- 11月初旬=秋と冬の境目
- 前半は秋語、後半は冬語を使う
- 印象でフォーマル・カジュアルを切り替える
晩秋・暮秋・残菊の候の使いどころ
11月初旬の前半は「晩秋」「暮秋」「残菊」の候が自然です。
「晩秋」は語感が中庸で、相手を問わず使える万能表現です。
「暮秋」はやや改まり、社外文書や案内状に向いています。
「残菊」は花の余韻を感じさせ、趣味の便りや年配の方への手紙に適します。
- 晩秋の候:万能で使いやすい
- 暮秋の候:改まった文書向け
- 残菊の候:親しい相手・趣味文に好適
立冬・向寒・深秋の候の使い分け
11月上旬の後半は「立冬」「向寒」「深秋」の候がふさわしいです。
「立冬」は暦上の冬入りを伝える語で、公式文書に向きます。
「向寒」は寒さに向かう様子をやわらかく表し、日常のビジネス文に自然です。
「深秋」は秋の終盤をしっとりと描く語で、私信や挨拶状におすすめです。
- 立冬の候:節目を伝える公式向け
- 向寒の候:柔らかく冬支度を示す
- 深秋の候:静かで文学的な印象
避けたい語と季節ズレの回避
11月初旬に使う語は、季節感のズレを避けることが大切です。
「初春」「新緑」「新涼」などは時期が合わず不自然に響きます。
立冬前でも冷え込む年は「向寒の候」を早めに使って問題ありません。
逆に暖かい場合は「晩秋」や「深秋」を残すと自然です。
- 避ける語:初春、新緑、新涼など
- 判断基準:届く頃の気温や天気
- 微調整:立冬前後で1段階ずらすと安全
媒体別テンプレ(冒頭〜結び)

媒体に合わせて文調を変えると、自然な印象で伝わります。
ビジネスでは簡潔さ、学校連絡では思いやり、カジュアルでは柔らかさが大切です。
冒頭と結びの温度感をそろえると、誠実な印象を与えられます。
- 媒体別にトーンを変える
- 冒頭と結びの温度感を一致させる
- 目的と関係性に合う表現を選ぶ
ビジネスメール/送付状の型と例文
ビジネスでは、簡潔で誠実な文調が基本です。
冒頭は「晩秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」
本文では用件を一文で伝え、詳細は続けて補足します。
結びは「貴社のご発展をお祈り申し上げます」でまとめます。
- 冒頭:晩秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
- 本文:目的を明確に伝える(例:書類送付の件)
- 結び:貴社のご発展をお祈り申し上げます
»【11月の挨拶文】上旬・中旬・下旬の書き出し+用途別テンプレ集
私的手紙/学校連絡の丁寧表現
私的な文書では、温かみを持たせると親近感が生まれます。
冒頭は「晩秋の候、みなさまお元気でお過ごしでしょうか」
本文では「朝晩の冷え込みが増してきましたね」など、季節の話題を添えます。
結びは「どうぞお体を大切にお過ごしください」で締めるとやわらかい印象です。
- 冒頭:晩秋の候、みなさまお元気でお過ごしでしょうか
- 本文:季節の変化や健康への気遣いを添える
- 結び:体調をいたわる一文で締める
»【11月の手紙挨拶】迷わず書ける季節表現+相手別文例集
カジュアル結びの安全フレーズ集
カジュアルな結びは、軽くなりすぎないバランスが重要です。
「お体に気をつけてお過ごしください」は汎用性が高く安心です。
「季節の変わり目ですので、ご自愛ください」も丁寧な印象を与えます。
親しい相手には「風邪などひかないように、あたたかくしてお過ごしください」と添えると自然です。
- 万能型:お体に気をつけてお過ごしください
- 丁寧型:季節の変わり目ですので、ご自愛ください
- 親しみ型:風邪などひかないように、あたたかくしてお過ごしください
»【11月の結びの言葉】シーン別の文例集+気遣う一言の書き方のコツ
そのまま使える三行テンプレ
3行構成の挨拶は、短くても誠意が伝わる便利な形式です。
どの場面でも「季節+気づかい+結び」を意識すれば整った印象になります。
社外・社内・私的の3タイプに分けて紹介します。
- 1行目:季節の挨拶
- 2行目:感謝や近況
- 3行目:前向きな結び
社外宛(取引先)
社外文は、礼節を重んじる表現が基本です。
「晩秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」から始めると季節感と敬意が伝わります。
中間の一文では感謝を述べ、結びで関係維持を願うと自然です。
- 1行目:晩秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
- 2行目:平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます
- 3行目:今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
社内宛(同僚/上司)
社内向けでは、感謝と気づかいを柔らかく伝えるのがコツです。
冒頭で季節を触れ、日常のねぎらいを加えると好印象です。
- 1行目:朝晩の冷え込みが増してまいりました
- 2行目:いつもご尽力いただきありがとうございます
- 3行目:お体に気をつけてお過ごしください
私的(保護者/友人)
親しい相手には、形式よりも自然な優しさが大切です。
天気や体調に寄り添う言葉を添えると温かく伝わります。
- 1行目:朝夕の空気に冬の気配を感じるようになりました
- 2行目:お変わりなくお過ごしでしょうか
- 3行目:どうぞあたたかくしてお過ごしください
よくある失敗Q&A
時候の挨拶で迷いやすいのは「暦と気温のズレ」「地域差」「投函日」です。
二十四節気(1年を24の季節に分けた暦)に基づくため、実際の天候と異なることがあります。
立冬前後や気温差が大きい年に起こりやすい3つのケースをQ&A形式で紹介します。
- 投函や送信のタイミングによるズレ
- 地域ごとの気候差への対応
- 季語と体感のずれ対処
立冬当日をまたぐ投函はどうする?
立冬(11月7日ごろ)をまたぐ場合は、「6日まで秋語」「7日以降冬語」が基本です。
暦上の切り替えを意識して使い分けると、印象が自然になります。
ただし、暖かい年は立冬当日でも秋語を使って問題ありません。
- 6日まで:晩秋・暮秋など
- 7日以降:立冬・向寒など
- 判断基準:相手が受け取る時期の季節感
地域差・寒暖差が大きい年の表現
地域差が大きい年は、どちらにも通じる中間表現を使うと安全です。
たとえば「向寒の候」や「深秋の候」は全国に通じる語です。
北海道や東北では早めの冬語、九州では秋語を残すなど柔軟に調整します。
- 全国宛て:向寒・深秋など
- 地域限定:晩秋・初冬に調整
- 補足文:寒暖差に気づかう一文を添える
季語と実天候のズレ対処
天候と季語がずれる年は、暦より体感を優先します。
気温が高い年は「晩秋」「深秋」、冷え込みが早い年は「立冬」「初冬」に切り替えると自然です。
形式よりも「受け取る空気感」を意識するのがコツです。
- 暖かい年:晩秋・深秋を残す
- 寒い年:立冬・初冬に変える
- 優先:形式より体感
11月初旬の時候挨拶で、よくある質問8つ
2.11月の時候挨拶をビジネスで使うときの注意点は?
4.11月の挨拶をカジュアルにするにはどうすればいい?
5.11月の時候挨拶は学校向けにどう書くのがよい?
6.12月の時候の挨拶はどう切り替えればいい?
12月は本格的な冬の始まりなので、「初冬の候」から「師走の候」「寒冷の候」などに変えましょう。
時期の変化を意識して語句を更新すると、自然な季節感が出ます。
7.11月下旬から12月上旬にかけて使える挨拶は?
11月下旬から12月上旬は季節の境目です。
「初冬の候」「師走の候」がどちらの時期にも使えます。
寒さを気遣う文を添えると柔らかくまとまります。
まとめ

11月初旬の挨拶は「時期判定→媒体→結び」の3ステップで整います。
この順番を意識するだけで、迷いなく自然な文章を組み立てられます。
挨拶文づくりの流れと次の展開を紹介します。
- 時期判定:季節の切り替えを意識
- 媒体選定:相手や場面に合わせる
- 結び表現:温度感をそろえる
基本は「時期判定→媒体→結び」
どんな挨拶も「いつ・誰に・どう締めるか」で印象が変わります。
時期は暦を基準に、媒体は関係性に応じて調整し、結びは心配りで整えます。
3点を意識すると、自然で信頼感のある文章になります。
- 時期:暦の変わり目を意識
- 媒体:関係性に応じたトーン
- 結び:思いやりの表現
二十四節気+例文で迷いゼロ
時候の挨拶は、二十四節気(にじゅうしせっき)を軸に例文を照らすと迷いません。
たとえば「立冬=11月7日ごろ」と覚えておくと、時期の切り替えが明確になります。
「立冬の候」「向寒の候」「深秋の候」を状況に応じて使い分けましょう。
- 節気:季節の基準を知る
- 例文:自然な使い方を学ぶ
- 目的:迷わず整った文に仕上げる
次は中旬/下旬版へ展開
初旬の挨拶に慣れたら、中旬・下旬も同じ流れで応用できます。
中旬は「初冬」「向寒」、下旬は「小雪」「初霜」などの語が中心です。
11月全体を通して流れを把握すると、挨拶文が“型”から“感覚”へ変わります。
- 中旬:初冬・向寒など
- 下旬:小雪・初霜など
- 目的:自然な季節の流れを表す
重要なポイント
11月初旬の時候の挨拶は、季節の移ろいを正しくとらえることが鍵です。
本記事では、暦と実際の気候を踏まえた語句選びと使い分けを整理し、迷いをなくす方法を紹介しました。
- 配達日と地域で「晩秋語」「初冬語」を選ぶ
- 媒体ごとに文調と温度感を合わせる
- 二十四節気を基準に自然な表現へ調整
- 避けたい語と季節ズレの回避で印象を整える
- 3行テンプレで短くても誠意を伝える
「正しい時期判定」と「使える例文」を身につけ、状況に応じた挨拶文を自信をもって書けるようになります。
中旬・下旬の挨拶記事も確認し、季節ごとの表現力を体系的に磨いていきましょう。
以上です。
関連記事11月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
関連記事【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ