- 11月の挨拶文を書くたびに、「秋なのか冬なのか」で迷ってしまう
- 定型文を使うと固すぎるし、柔らかく書くと軽く見えてしまう
- 毎年この季節になると、どんな言葉を選べばよいか悩む
この記事でわかること
- 上旬・中旬・下旬で使い分ける時候語(晩秋・向寒・立冬など)とその意味
- ビジネス/お礼状/学校便り/LINEなど、場面別に使える自然な例文
- 書き出しと結びを先に決めて、短時間で整える文章構成法
- ご自愛系・発展祈念系など、相手との距離で選ぶ結び文の型
- 古式過多・敬語重複を避ける、安全で上品な運用ルール
- よくある質問+回答
11月の挨拶文を書くたびに「秋なのか冬なのか」微妙な季節の狭間で、どんな言葉を選べばよいか悩む方は多いです。
迷いを解く鍵は、「秋語」と「冬語」を意識して語の温度をそろえることです。
たった一行でも、季節の空気を正しく届けるだけで、文全体が自然で上品に整います。
本記事では、上旬・中旬・下旬ごとの表現と、ビジネス・お礼状・私信に使える例文を紹介しています。
形式に頼らず、自分の言葉で季節を伝えたい方にとって、挨拶文づくりが迷いから自信に変わります。
地域や気温に合わせて言葉を半歩動かすことで、心に寄り添う手紙やメールを書けるのです。
11月の時候語と使い方の基本
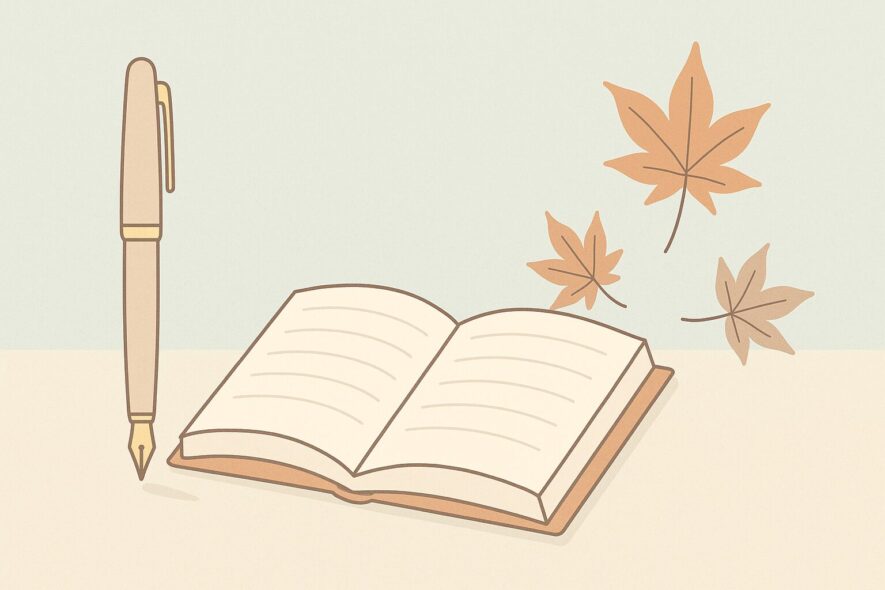
結論は、「秋語」と「冬語」を使い分ける意識を持てば迷いが減ることです。
語の温度をそろえるだけで、読み手の景色がそっと一致するからです。
上旬は「晩秋」「暮秋」で色づきの余韻を伝えます。
中旬は「向寒」で冷えの始まりを知らせ、下旬は「立冬」「深冷」で張りつめた空気を添えます。
迷ったら、最後の1文だけ丁寧度を上げて全体を整えましょう。
- 秋語:晩秋/暮秋。
- 冬語:向寒/立冬/深冷。
- 迷った時:結びを丁寧に寄せる。
二十四節気と体感季節のズレ注意
節気は目安、体感は現場という考え方で選ぶことです。
相手の暮らす場所と天気が、受け取り方を左右するからです。
立冬が早く感じる日は、秋語へ半歩戻して温度差を埋めます。
冷えが続く週は、冬語へ半歩進めて空気の張りを添えます。
語は季節の定規です。
目盛りを少し動かすだけで、文の景色が合います。
- 早い体感 → 秋語で調整。
- 寒い体感 → 冬語で調整。
- 地域差を想像して選ぶ。
ビジネス/カジュアルの語調の選び方
同じ内容でも語調を変えると伝わり方が整うことです。
礼節の度合いと距離感が、読み手の安心につながるからです。
ビジネスなら「向寒の折、貴社のご発展をお祈りします」
カジュアルなら「朝夕が冷えるので、体をあたためてお過ごしください」
どちらも要件は短く、結びで温度をそろえると収まりがよくなります。
- 社外文 → 定番語+端正な結び。
- 友人宛て → 会話調+体調への気遣い。
- 迷い → 結びで丁寧度を調整。
»【11月のカジュアル挨拶】迷わず使える一言テンプレ+好印象の書き方
書き出し→結びの型を先に決める
書き出しと結びを先に固定し、本文は要件に集中することです。
毎回の語選びを減らし、短い時間で仕上げられるからです。
例として、書き出しを「向寒の候」、結びを「ご自愛ください」にします。
上旬は「晩秋の候」、下旬は「立冬の候」へ差し替えます。
要件は箇条書きで入れると、すぐ用件を把握できます。
- 書き出し語+結び語を固定。
- 本文は要件を短く。
- 時期語は差し替えで運用。
»【11月の結びの言葉】シーン別の文例集+気遣う一言の書き方のコツ
上旬に使う表現と例文
朝の白い息がうすく見え、夕方の空が深く色づく頃です。
語は体感に寄せると、読み手の景色とやさしく重なります。
迷ったら、秋寄りの語から始め、寒気が続く日は半歩だけ冬寄りへ寄せます。
運用は「挨拶一行→用件→結び一行」の三段で流すと整います。
晩秋/暮秋/菊花の候の意味と例文
三語は、秋の終わりを異なる質感で映します。
相手と文書の重さに合わせ、響きで選びます。
- 晩秋の候:明るめの終盤。幅広い相手に自然です。
- 暮秋の候:静かな余韻。落ち着いた場に合います。
- 菊花の候:行事と相性がよい、上品な季節語です。
- 晩秋の候、皆さまのご健勝をお祈りいたします。
- 暮秋の候、平安にお過ごしのほどお祈りいたします。
- 菊花の候、季節の折り目につきご自愛ください。
社外メールの短文テンプレ
最初の一文で温度を合わせると、読みやすくなります。
用件は数字と期日を明確にし、段落を短く割ります。
- 晩秋の候、平素のご高配に厚く御礼申し上げます。
- 暮秋の候、引き続きご支援のほどお願い申し上げます。
- 菊花の候、何卒よろしくお願い申し上げます。
結びは「ご自愛ください」「ご発展をお祈りいたします」などで静かに締めます。
学校・おたより向けの言い換え
生活の実感に触れる一言があると、動きやすくなります。
季節の情景と行動の案内を、短い文で並べます。
- 落ち葉が増え、朝の空気がひんやりしてきました。
- 登下校は上着の用意をお願いします。
- 菊の花が見ごろです。体調に気をつけてお過ごしください。
「挨拶→連絡→お願い→結び」の四段で、読みやすい流れを保ちます。
»【11月のおたよりの書き出し】短く伝わる季節の言葉+行事文例集
» 学校で使える11月の時候挨拶フレーズ【目的別の挨拶文テンプレート】
中旬に使う表現と例文

11月中旬は暦のうえで冬へ入りつつも秋の余韻が残る時期です。
日暮れが早まり朝晩の冷えが進むため言葉は寒気を映します。
代表語は「向寒」「小夜時雨」「深秋」です。
礼節か情緒か余韻かという軸で選ぶと文面の温度が整います。
向寒/小夜時雨/深秋の意味と例文
中旬は寒さへ向かう気配を示す語が自然です。
立冬後の空気に沿うため読み手の体感ともずれにくいです。
- 向寒の候:礼儀重視の定番語で公私に広く適合。
- 小夜時雨の候:夜の一時雨を映す情緒語で私信向き。
- 深秋の候:秋の深まりを示す上品な語で式典案内にも合う。
- 向寒の候 皆さまのご健勝をお祈りいたします。
- 小夜時雨の候 ご自愛のうえ穏やかにお過ごしください。
- 深秋の候 日ごとに寒さが増してまいりました。
送付状・請求書の一文サンプル
ビジネスでは挨拶一行ののち要件へ移る構成が読みやすいです。
語は端正で簡潔なものを選ぶと全体が整います。
- 向寒の候 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
- 深秋の候 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
- 小夜時雨の候 今後とも変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。
挨拶の直後に「下記のとおりご送付申し上げます」などで要件へ続けます。
カジュアルLINE・私信の言い換え
私信は形式より体温が届く短文が合います。
季節の一言と相手のからだ遣いへの配慮を添えると伝わります。
- 朝晩が冷えてきたね。温かくして過ごしてね。
- 夜の雨が冷たく感じる季節だね。風邪に気をつけて。
- 秋が深まってきたね。無理せず休んでね。
下旬に使う表現と例文
11月下旬は秋の名残を残しながら冬の気配が深まる時期です。
朝霜や北風が季節の変わり目を知らせます。
言葉選びは冷たさの中に温かみを添えることが鍵です。
代表語は「立冬」「深冷」「初霜」です。
それぞれに静かな余韻が宿ります。
立冬/深冷/初霜の候の意味と例文
三語はいずれも冷えを描きつつ人のぬくもりを映す語です。
- 立冬の候:冬の始まりを告げる節目の語。ビジネス・公用に最適。
- 深冷の候:澄んだ空気の静けさを湛える上品な語。
- 初霜の候:霜の白さにやさしさを感じさせる親しい語。
- 立冬の候 ご健勝をお祈り申し上げます。
- 深冷の候 ご多忙の折 ご自愛のほどお願い申し上げます。
- 初霜の候 あたたかな日々をお過ごしください。
取引先あて丁寧表現の差し替え表
形式美は細部に宿ります。
語を一段やわらげるだけで印象は穏やかになります。
- お忙しい中 → ご多用の折
- お体にお気をつけください → ご自愛のほどお願い申し上げます。
- よろしくお願いします → 何卒よろしくお願い申し上げます。
年末進行の気遣いフレーズ
冷たい風のなかで働く相手へ一言の労りを。
忙しさの合間に読むたった一行が心を休ませます。
- 年末ご多忙の折 ご健康をお祈りいたします。
- 寒気いよいよ募る頃 ご自愛ください。
- 今年も残りわずか。どうぞ穏やかな日々をお過ごしください。
結び文の定番と言い換え

結び文は、用件の余韻を整える一行です。
11月は体調と業務の配慮が要るため、健康と祈念を使い分けると自然です。
場面別の言い換えと季節の一言で、読み手に温度が伝わります。
ご自愛系/発展祈念系の使い分け
個人や社内はご自愛系、取引や社外は発展祈念系が基本です。
距離感と目的に合う視点を選ぶと、結びが落ち着きます。
- ご自愛系
- ご自愛のほどお願い申し上げます。
- 体調にお気をつけてお過ごしください。
- 健やかにお過ごしになれますようお祈りいたします。
- 発展祈念系
- ますますのご発展をお祈り申し上げます。
- 今後のご隆盛を心よりお祈りいたします。
- 変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
季節感を添える一言(紅葉・寒暖)
結びの直前に、季節の情景を短く添えます。
言い過ぎず、一行で整えます。
- 紅葉が見ごろの折、どうぞ穏やかにお過ごしください。
- 朝夕の冷え込みが増す頃、どうかご自愛ください。
- 寒暖差の大きい時節につき、健康にご留意ください。
NG/古式過多の回避ポイント
古式の重ねがけと口語のくだけ過ぎを避けます。
読み手の負担を軽くし、品位と親しみを両立させます。
- くれぐれもお体ご自愛ください → ご自愛のほどお願い申し上げます。
- 取り急ぎご連絡まで → 以上、用件のみ申し上げました。
- まずは書中にて失礼いたします → 取り急ぎ書中にてご挨拶申し上げます。
- 何卒よろしくお願い申し上げたく存じます → 何卒よろしくお願い申し上げます。
11月の実用テンプレ集
冷たい風に冬の気配を感じる11月。
形式文でも、わずかな温度を添えるだけで心が伝わります。
すぐに使える短文テンプレを、媒体別にまとめました。
ビジネス文(メール/送付状)
公的文書は「端正」「簡潔」「整った敬意」が基本です。
次の定型をベースに、要件を続けるだけで形が整います。
- 向寒の候 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
- 深冷の候 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
- 初霜の候 貴社のご発展をお祈り申し上げます。
件名例:「【ご案内】11月のご挨拶」「【請求書送付】11月分のご連絡」
手紙・はがき・一筆箋
手紙やはがきは、言葉に声の温度をのせる媒体です。
短くても、情景を一文入れると記憶に残ります。
- 晩秋の候 お変わりなくお過ごしのことと存じます。
- 紅葉が美しい頃ですね。どうぞお元気でお過ごしください。
- 寒さが増してまいりました。体調にお気をつけください。
- 冷え込む日が増えました。お体をおいといください。
- 年末に向けご多忙かと存じます。ご自愛ください。
件名や書き出しの即時コピペ集
件名と書き出しを整えるだけで、文全体の印象が変わります。
時間のないときは、以下をそのまま使ってください。
- 件名テンプレ
- 【ご挨拶】立冬の候に寄せて
- 【お礼】深冷の候 ご厚情に感謝申し上げます
- 【ご案内】年末業務のスケジュールについて
- 書き出しテンプレ
- 向寒の候 皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。
- 深冷の候 貴社のご隆盛をお祈り申し上げます。
- 晩秋の折 ご健勝にてお過ごしのことと存じます。
»【11月の季節の挨拶】書き出し・結び・時期別のコピペ例文まとめ
11月の時候挨拶の例文で、よくある質問8つ
1.11月の時候挨拶で、やわらかい表現にしたいときはどうすればいい?
形式的な言葉を少し崩すと、やわらかい印象になります。
たとえば「晩秋の候」より「秋の深まりを感じる頃ですね」と言い換えると自然です。
相手が親しい場合は季節の情景を一文添えると温かみが出ます。
2.11月下旬の時候挨拶にはどんな表現が合う?
11月下旬は初冬の冷えを意識した語が合います。
「立冬の候」「深冷の候」「初霜の候」などが定番です。
ビジネス文では「寒さが身にしみる季節となりました」と添えると落ち着いた印象になります
»【11月下旬の時候挨拶】迷わず書ける表現と好印象の結び方
3.11月の挨拶文の書き出しで迷ったときのコツは?
書き出しは「季節+相手の安否」で整います。
「晩秋の候、いかがお過ごしでしょうか」や「木枯らしに冬の気配を感じるこの頃」などが使いやすいです。
ビジネスでも私信でも自然に馴染みます。
»【11月の挨拶文】上旬・中旬・下旬の書き出し+用途別テンプレ集
4.11月の時候挨拶をビジネスメールで使うときの注意点は?
ビジネスでは簡潔さと礼節が重要です。
「向寒の候」「晩秋の候」など季節を示す語を1文だけ入れると上品です。
その後に「平素よりお世話になっております」と続けると自然な流れになります。
»【11月のビジネスの時候挨拶】迷わず書ける例文と使い分け完全ガイド
5.11月下旬から12月上旬の時候挨拶はどう切り替えればいい?
11月下旬は「立冬の候」、12月上旬は「初冬の候」など、どちらも使える語を選ぶと安心です。
季節の境目なので「冬の足音が聞こえる頃」といった柔らかい表現もおすすめです。
6.11月の時候挨拶をお礼状に入れるときのポイントは?
お礼状では季節感を控えめに添えるのがコツです。
「晩秋の候」「紅葉の美しい折」など一文で季節を伝え、その後に「ご厚情に感謝申し上げます」と続けると丁寧にまとまります。
7.11月中旬の時候挨拶で無難な表現を教えて。
11月中旬は「向寒の候」「小夜時雨の候」「深秋の候」が無難です。
日常文なら「朝晩の冷え込みが強くなりましたね」と書くと自然です。
どんな相手にも失礼のない万能表現です。
»【11月中旬の時候挨拶 】迷わず書ける季節の言葉と例文集
8.11月上旬の時候挨拶の例文でおすすめは?
11月上旬はまだ秋の余韻が残るため、「菊花の候」「秋晴れの空が心地よい頃」などが向いています。
ビジネスでは「晩秋の候 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます」が定番です。
まとめ

朝霜が降り、吐く息が白くなる頃。
11月の挨拶は、冷たさの中に思いやりをのせる練習です。
言葉の運び方と安全に使うための確認をまとめました。
- 要点まとめ
- 上旬:晩秋・菊花の候など秋の余韻を残す語を。
- 中旬:向寒・小夜時雨など冬支度を感じさせる語を。
- 下旬:立冬・深冷・初霜の候など冷えを映す語を。
- 結び文:相手に応じてご自愛系・発展祈念系を選ぶ。
- テンプレは相手・媒体・温度感で調整する。
- 安全運用チェック
- 重複・古語の過多は避ける。
- 敬語の強弱を相手の立場で調整。
- 候体の使用は1文までが読みやすい。
- 誤用が心配な語は辞典や信頼ソースで確認。
- テンプレは必ず一度声に出して違和感を確認。
時候の挨拶は、正解よりも「誠実な調整」に価値があります。
心の温度を測るように、言葉を選ぶことが11月のマナーです。
以上です。
関連記事【11月初旬の時候挨拶】時候句リスト+そのまま使える3行テンプレ
関連記事【11月の挨拶】上中下旬と立冬の整った例文集【書き出し+結びの型】
