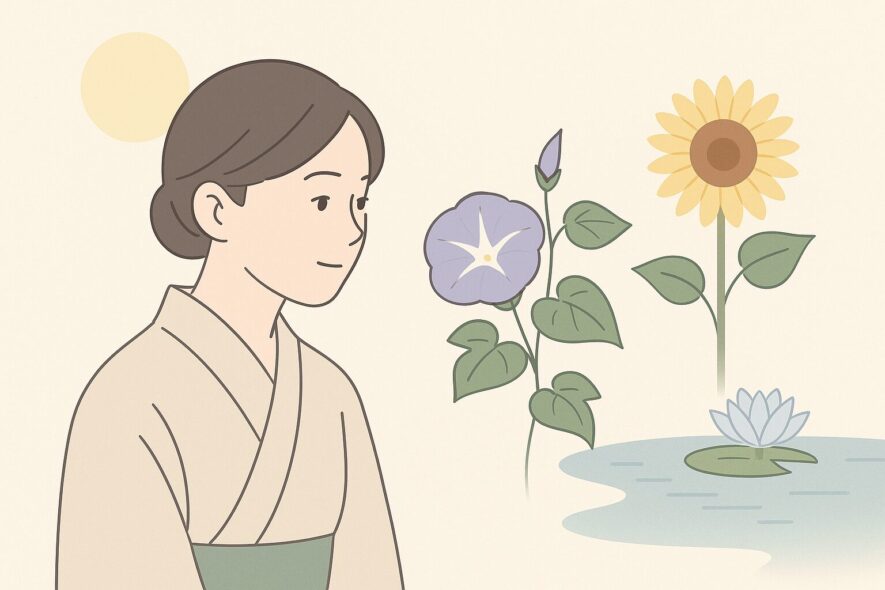- 毎年この季節になると、時候の挨拶や手紙の書き出しに悩む
- 形式だけの文章にならず、自然な季節感も伝えたい
- 7月らしい花の名前も入れたいけれど、どんな言葉を選べばいいのか迷ってしまう
この記事でわかること
- 7月の時候の挨拶に使える「漢語調」「口語調」の使い分け方
- 上旬・中旬・下旬別にふさわしい挨拶の文例
- 朝顔・ひまわり・睡蓮など、7月に合う花を使った表現方法
- ビジネスとプライベートで異なる書き出し・結びの構成の違い
- 花を活かした情景描写や相手に合わせた選び方のポイント
- 季語や挨拶文を使った実践的なテンプレート・応用例
「7月の時候の挨拶」に「ふさわしい言葉や季節の花」を組み合わせることで、印象に残る表現が生まれます。
本記事では、上旬・中旬・下旬それぞれの季節感を活かした挨拶例に加え、朝顔・ひまわり・睡蓮などの花を取り入れた書き方を紹介しています。
文体や関係性に応じて言葉を選び、自分らしい表現で気遣いを伝えられます。
7月の時候の挨拶とは
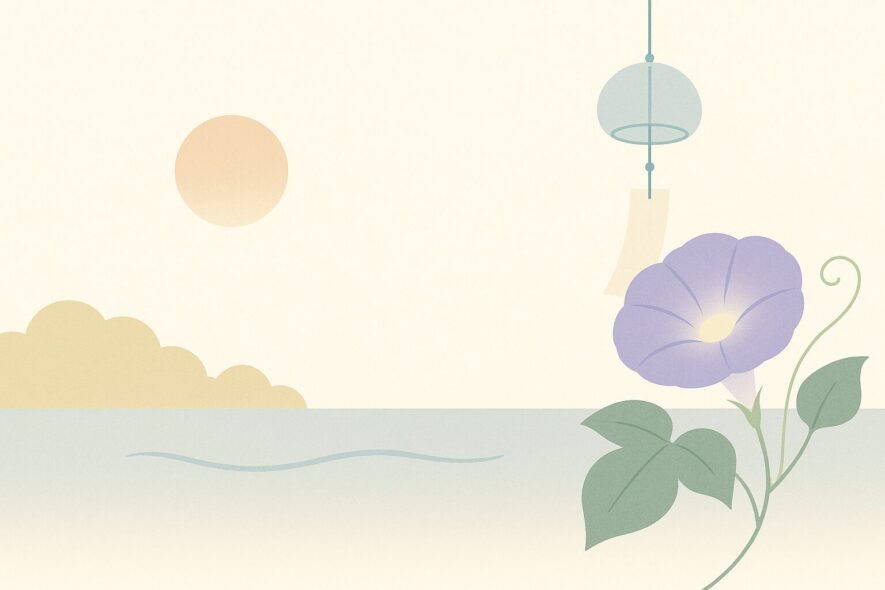
7月の時候の挨拶は、季節感を表す大切な要素です。
日本では昔から「季節のうつろい」を言葉で表現し、相手を気遣う文化があります。
爽やかな印象を届けたいときに効果的です。
たとえば「盛夏の候」「小暑の候」といった言葉は、使う時期や相手に応じて選びます。
文体に合わせて「漢語調」と「口語調」を使い分けることで、挨拶文の印象が変わります。
朝顔やひまわりなどの花を添えると、文章がぐっと夏らしくなります。
漢語調と口語調の違い
時候の挨拶には「漢語調」と「口語調」があります。
表現の形式や相手との関係に応じて選びます。
- 漢語調:格式ばった印象を与える文章
- 口語調:自然で柔らかな印象を与える会話的な表現
たとえば、上司や取引先への手紙では「盛夏の候」「小暑の候」などが適しています。
一方、友人や家族には「暑さが続きますがお元気ですか」といった自然な口調が合います。
相手との関係性に合った文体を使うことで、丁寧さや気遣いが伝わります。
使える季語一覧(朝顔・ひまわりなど)
7月の挨拶文では、花を添えると季節感が際立ちます。
花は季語としても活用され、言葉に彩りを加えてくれます。
- 朝顔:夏の朝に咲く清涼感のある花
- 向日葵:強い日差しを連想させる夏の象徴
- 蓮:水辺に咲く静けさを感じさせる花
- 桔梗:凛とした印象を与える紫の花
- 百日紅:長く咲き続ける夏の終わりの花
たとえば「朝顔が涼やかに咲くころに」と入れると、風景が浮かぶ挨拶になります。
暑さのなかでも咲き誇る花に、相手への励ましや涼感をたくす気持ちを込められます。
たとえば、江戸時代の人びとは朝顔を涼しさの象徴として愛しました。
「朝顔市」は7月の風物詩として親しまれています。
上旬・中旬・下旬別 挨拶フレーズ
7月の時候の挨拶は、上旬・中旬・下旬で使う言葉が変わります。
梅雨明け前の湿気、夏の始まり、そして大暑と、季節の移ろいがはっきりしているからです。
たとえば、上旬は梅雨を意識した表現、中旬は爽やかな夏を感じさせる語句、下旬は体調を気遣う文面が適しています。
時期に応じた言葉選びが、自然で心に残る文章になります。
7月上旬:梅雨明け前後の書き出し
7月上旬は、梅雨の名残と夏の気配が入り交じる時期です。
湿度や雨の多さを意識しつつ、晴れ間の兆しを織り交ぜた表現が合います。
- 長雨が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか
- そろそろ蝉の声が聞こえはじめました
- 梅雨明けが待ち遠しいころとなりました
花を取り入れるなら「紫陽花が色づく季節になりました」などもおすすめです。
自然を通して、季節の情景を伝えるよう意識しましょう。
「蝉の初鳴き」は7月初旬の風物詩として知られています。
静かな梅雨の終わりと、にぎやかな夏の入り口をつなぐ合図とも言えます。
7月中旬:小暑~本格的な夏の表現
7月中旬は「小暑」の頃で、夏らしさが増してきます。
強すぎない暑さと、自然の変化に目を向けた表現がなじみます。
- 小暑の候、夏の訪れを感じる今日このごろです
- 日差しが日に日に強まってまいりました
- 朝顔が元気に咲いています
生活の中で感じる季節の移ろいを添えると、共感が生まれます。
心地よい暑さをイメージできる言葉を選びましょう。
朝顔は、夏の訪れを告げる日本の風物詩です。
涼しげな色合いが、暑さのなかにやさしさを与えてくれます。
7月下旬:大暑・酷暑を見据えた文言
7月下旬は「大暑」を迎え、暑さが厳しくなります。
健康や日常を思いやる表現が求められます。
- 大暑の候、厳しい暑さが続いております
- 連日の猛暑に、どうかご自愛ください
- うだるような暑さが続いておりますが、お元気でしょうか
型通りの言葉でも、相手への気遣いが込もると、印象がやわらぎます。
昔から「暑中見舞い」は、この時期に相手の無事を祈る手紙として親しまれてきました。
心遣いは、季節の挨拶として受け継がれています。
花と季語を組み合わせた例文集

7月の手紙やメールでは、花を使った挨拶文が親しみやすく、季節感も伝わります。
朝顔やひまわりは、見た目にも涼しく、印象に残りやすい夏の花です。
文面の目的に応じて、花と季語を自然に組み合わせることが大切です。
7月にふさわしい花を使った挨拶文を具体的に紹介します。
朝顔を使った書き出し例(プライベート)
朝顔は、夏の朝を象徴する花として親しまれています。
江戸時代の庶民にも愛された夏の風物詩です。
台東区の「朝顔市」は毎年7月初旬に開かれ、風物詩としても有名です。
- 朝顔が元気に咲きはじめ、夏の訪れを感じる季節になりました。
- 涼しげな朝顔の花が、夏の朝を彩ってくれています。
- 朝顔が咲くころとなり、いよいよ夏本番ですね。
親しい相手への手紙では、自然の描写を交えると柔らかく伝わります。
日常の一コマとして花を取り上げると、親近感が増します。
ひまわりを取り入れた例文(ビジネス)
ひまわりは、太陽に向かって咲く姿から、希望や明るさを象徴する花です。
花言葉は「憧れ」「情熱」などで、ビジネス文にも前向きな印象を添えられます。
- 向日葵の花が日差しに映える季節となりました。
- 連日の暑さに、ひまわりのたくましさが印象に残ります。
- 盛夏の候、ひまわりのように元気にお過ごしのことと存じます。
フォーマルな文面でも、花を加えることで柔らかさが生まれます。
信頼や季節感を同時に伝える工夫として有効です。
睡蓮・サルビアなど季節花の文例
睡蓮やサルビアも、7月によく見かける季節の花です。
睡蓮は仏教にもゆかりのある花で、水辺の静けさや涼しさを感じさせます。
サルビアの赤は活力を象徴し、街角を明るく彩ります。
- 池に咲く睡蓮が、心を落ち着かせてくれる季節です。
- サルビアの赤い花が、街角を鮮やかに彩っています。
- 夏の日差しのなか、睡蓮の花に癒されています。
場面に応じて、花の印象や色を取り入れた表現にすると伝わりやすいです。
気温の高さを和らげるような描写が、心をやさしく包みます。
書き出しと結びの文構成ガイド
挨拶文では、書き出しと結びの構成が印象を左右します。
7月の季節感を伝えるとともに、相手を気遣う気持ちを込めることが大切です。
ビジネスでは丁寧な文体、プライベートでは親しみやすい言葉選びが求められます。
それぞれに合った言い回しを使うことで、自然で心のこもった文章になります。
暑中見舞いの文化は江戸時代の「季節の贈り物」から始まったと言われています。
当時はお中元と同時期に手紙を添える風習があり、現在の挨拶文の原型となっています。
ビジネス向け:漢語調+丁寧な結び方
ビジネスの挨拶文では、改まった印象を与える漢語調が基本です。
格式や礼儀を重視した表現で、相手との信頼関係を築くきっかけになります。
- 書き出し例:盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
- 書き出し例:小暑の候、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 結び例:今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
- 結び例:厳しい暑さが続きます折、皆さまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。
ビジネス文の冒頭にある「盛夏の候」などは、四季の移ろいに目を向ける日本特有の挨拶文化です。
結びの「ご健勝をお祈りします」には、相手の健康や仕事の順調を願う気持ちが込められています。
»【ビジネス向けの夏の挨拶】上司や取引先に好印象な例文とマナー集
プライベート向け:口語調+温かみある結び
親しい相手への手紙では、自然な口調で心を込めた表現が好まれます。
やわらかい言葉づかいや、相手への思いやりを込めた結びが印象的です。
- 書き出し例:暑さが増してきましたが、元気にお過ごしですか。
- 書き出し例:朝顔の花が咲きはじめ、夏の訪れを感じています。
- 結び例:暑さに負けず、お体を大切にお過ごしください。
- 結び例:また近いうちにお会いできるのを楽しみにしています。
日常の中で感じたことを素直に書くことで、読み手の心に残ります。
季節の話題を交えながら、相手の暮らしを想像するような言葉を添えると、温かい印象になります。
»【夏の手紙の挨拶文マナー】失礼にならない書き方+時期別の文例集
花を活かす文章のポイント
7月の挨拶文に花を取り入れると、季節感がより豊かになります。
ただ花の名前を出すだけでなく、咲く様子やまわりの情景を描写すると、伝わり方が変わります。
相手に合った花を選ぶことで、より丁寧な印象を与えられます。
花をうまく使った表現のポイントを紹介します。
情景描写で季節感を演出
花を使った表現では、咲いている様子やまわりの風景を描くと、読み手の想像が膨らみます。
色や時間帯、温度、音などを意識すると、臨場感ある文章になります。
- 朝顔が朝露に濡れて、涼しげに咲いています。
- ひまわりがまっすぐに空を仰ぎ、夏の強い日差しを浴びています。
- 池の水面に映る睡蓮の白い花が、風に揺れています。
朝顔の青色には、見る人を落ち着かせる心理効果もあると言われています。
夏の寺院では蓮の花を眺めながら風鈴の音を楽しむ風景もあります。
相手に合わせた花選びのコツ
相手の年代や関係性に応じて、花の選び方にも工夫が必要です。
色や花言葉を意識すると、印象がやわらかくなります。
- 目上の方には、落ち着いた印象の蓮や桔梗がおすすめです。
- 親しい相手には、明るく元気なひまわりや百日紅が向いています。
- 女性には、可憐な印象の朝顔やサルビアが好まれることが多いです。
桔梗には「誠実」「変わらぬ愛」などの花言葉があり、年配の方に好まれる傾向があります。
花には気持ちを託す力があるため、文中にさりげなく添えると、心が伝わります。
たとえば、忙しい人には、元気づけるようなひまわりを添えると、さりげない気遣いになります。
7月の時候挨拶の花で、よくある質問8つ
1.7月の時候の挨拶例文にはどんなパターンがありますか?
7月の時候の挨拶例文には「盛夏の候」「小暑の候」などがよく使われます。
上旬・中旬・下旬によって表現を変えると、季節感がより伝わります。
花や自然の描写を加えるのもおすすめです。
» 7月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
2.7月の時候の挨拶をビジネス文書で使う場合の注意点は?
ビジネスでは、漢語調の「盛夏の候」などが適しています。文頭に置いて礼儀正しく始めると印象が良くなります。
結びの文でも相手の健勝や今後の関係性に触れると丁寧です。
»【7月のビジネスの時候挨拶】上旬〜下旬の例文+使い分け完全ガイド
3.7月上旬の時候の挨拶はどう書けば自然ですか?
7月上旬は梅雨の終わりが近づく時期なので「梅雨明けが待たれる季節となりました」や「長雨が続いておりますが」など、湿度や雨を意識した表現が自然です。
»【7月上旬の時候の挨拶】ビジネス・プライベートで好印象を残す例文
4.カジュアルな7月の挨拶にはどんな表現がありますか?
「毎日暑いけど元気ですか?」「朝顔が咲いて夏らしくなってきましたね」など、口語調で気軽な言葉を使うのがポイントです。
親しい相手には、体調を気遣う一文も添えると丁寧です。
»【7月のカジュアルな挨拶】書き出しのおすすめフレーズ+メール短文例
5.7月下旬の時候の挨拶には何を意識すればよいですか?
7月下旬は「大暑」の時期にあたるため「酷暑が続いておりますが」や「大暑の候」など、暑さを意識した表現が適しています。
体調を気づかう結びも大切です。
»【7月下旬の時候の挨拶】酷暑・大暑の候で印象アップする例文まとめ
6.7月上旬の時候の挨拶例文を一つ教えてください。
「梅雨明けが待たれる季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか」といった例文が自然です。
梅雨と夏の境目を表現することで、時期に合った挨拶になります。
7.「盛夏の候」は7月のどの時期に使うのがよいですか?
「盛夏の候」は7月中旬から下旬にかけて使われます。梅雨が明けてから本格的な暑さが続く時期にふさわしい表現で、ビジネスにもプライベートにも活用できます。
8.7月中旬の時候の挨拶はどんな表現が適していますか?
「小暑の候、夏の訪れを感じるこのごろです」や「日差しが日に日に強まってまいりました」などが適しています。夏の始まりをやさしく伝える表現を選ぶとよいでしょう。
»【迷わない7月中旬の時候挨拶】小暑・盛夏の候の使い方+書き出し例
まとめ

7月の時候の挨拶に、季節の花を添えることで伝わり方が変わります。
本記事では、季節感や気遣いを表現できる文章の工夫や文例を紹介しました。
漢語調・口語調の使い分けや、花ごとの特徴を知ることで、挨拶文に深みが加わります。
ポイント
- 7月の時候の挨拶は、上旬・中旬・下旬で表現を変えるのが基本
- 「盛夏の候」「小暑の候」などの季語は文体と相手に応じて使い分ける
- 朝顔・ひまわり・睡蓮などの花を入れると季節感と印象が向上
- ビジネスでは丁寧な漢語調、親しい相手には温かな口語調が適切
- 書き出しと結びの構成に少し工夫を加えると、文章全体が洗練される
日本には「季節の移ろいを言葉に託す」という伝統があります。
時候の挨拶は、文化を伝える大切な表現のひとつです。
形式表現だけではなく、自分らしい言葉で少しアレンジするのもありです。
以上です。
P.S.季節を言葉で贈る挨拶文を、自分らしく仕上げてみてください。
関連記事【夏の挨拶文例まとめ】6月〜8月に好印象を与える言葉集+使い方
関連記事【7月の挨拶まとめ】失礼なく心を伝える言葉の選び方+テクニック