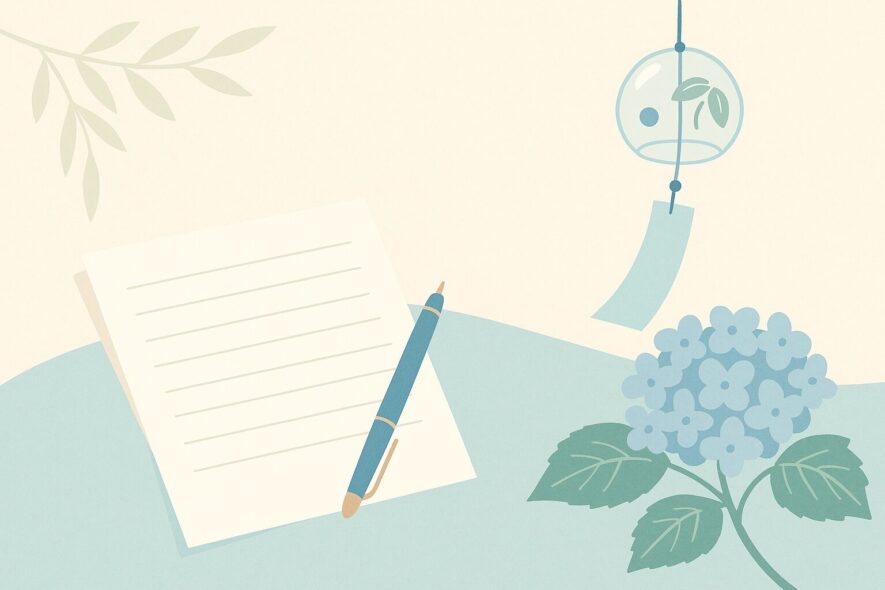- 「7月上旬ってどんな時候の挨拶を使えば失礼じゃないのかな」
- 「ビジネス用とプライベート用、どこまで書き分けるべきか悩む…」
- 「季語や言い回しの使い方が、今の時期に合っているか不安」
この記事でわかること
- 7月上旬の時候挨拶の基本知識と意味
- ビジネス用・プライベート用の書き出し、結びの例文
- 季節や天候に応じた表現の選び方と、誤用の回避方法
- よくある質問と回答(Q&A)
7月上旬は「小暑」や「向暑」など、季節の変わり目にふさわしい表現があります。
一言添えるだけで「気づかいや教養」が伝わるのが「時候の挨拶」の魅力です。
本記事では、フォーマル・カジュアルの例文や、誤用を避けるポイントまで網羅しています。
7月上旬にふさわしい時候の挨拶が書け、丁寧で気づかいのある印象を与えられます。
定型文をベースにしながら、自分らしいひと言を添えるコツもまとめました。
この記事の目次
【基本知識】7月上旬の時候の挨拶とは?

7月上旬に合う時候の挨拶には「小暑」や「向暑」などの表現があります。
文章に季節感と丁寧さを添える日本独自の言葉です。
日本では、自然の移ろいに心を寄せ、相手の体調や暮らしを思いやることが大切とされてきました。
たとえば梅雨が明けるころ「小暑の候」という一言で、季節の変わり目に対する配慮が伝わります。
文章の冒頭に季節のあいさつを添えるだけで、心がほどけることもあります。
「小暑」「向暑」「星祭」の意味と使用時期
7月上旬に使える代表的な季語には以下があります。
- 小暑(しょうしょ):7月7日ごろ。梅雨明けとともに夏の訪れを告げる節気。
- 向暑(こうしょ):暑さが近づく様子。6月末〜7月上旬に適した表現。
- 星祭(ほしまつり):七夕の別名。願い事や星空への思いを込められます。
季節の風景や行事を映し出し、文章に情緒を添えます。
普段のメールにも一言添えるだけで、心の通う文章になります。
»【7月の挨拶と季語一覧】季節感を伝える文例3選+表現のコツ
二十四節気と暦の関係
二十四節気は、古代中国から伝わった季節のカレンダーです。
日本ではこれを生活や文化に取り入れ、手紙文化にも反映しています。
- 「小暑」:7月7日ごろ。夏の始まりとされる節目。
- 「大暑」:7月23日ごろ。一年で最も暑い時期。
たとえば「小暑の候」「大暑の候」といった挨拶文は、節気をもとにしています。
単なる気候ではなく、伝統や暮らしの知恵を感じさせる表現として重宝されています。
»【7月の季節の挨拶】書き出しと結びの使える例文集【ビジネス・私信】
ビジネス向け:書き出し&結びの例文
ビジネス文書では、定型の挨拶文を使うことで礼儀と信頼が伝わります。
「型にはまった表現は味気ない」と思われがちですが、実際には型があるからこそ、安心感を与えられます。
7月上旬は、季節の節目で体調の変化も起こりやすく、気づかいの表現が重視される時期です。
定番の書き出しと結びを押さえておくだけで、文章全体の品格が保たれます。
書き出し:「拝啓 小暑の候…」
定型句「拝啓」に続けて、季節を感じさせる言葉を添えることで、文章の雰囲気が整います。
7月上旬に適した例は以下のとおりです。
- 拝啓 小暑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
- 拝啓 向暑の候、貴社におかれましてはご健勝のことと存じます。
「拝啓〜の候」の構文は古くから使われており、伝統に沿った信頼感ある書き出しになります。
結び:「盛夏の折柄、ご自愛を…」
結びには、相手の健康を願う言葉を置くと、文章が温かく締まります。
暑さの厳しくなる時期だからこそ、体調を気づかう一文は読まれる印象をよくします。
- 盛夏の折柄、くれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます。
- これからますます暑くなりますので、どうぞお身体を大切にお過ごしください。
一文だけ自分の言葉を添えると、定型の中に自分らしさも光ります。
プライベート向け:カジュアル例文集

親しい人へのメッセージでは、気取らない言葉のほうが、心に届きやすいです。
7月上旬は、湿気や気温の高さで体調をくずしやすい時期でもあります。
「元気かな?」「暑くない?」といった日常の問いかけから始まる文章はあたたかみがあります。
そのまま使える例文と、自分の言葉を添えてアレンジできる余白もあるフレーズを紹介します。
口語調の書き出し「梅雨明けが待ち遠しい今日…」
堅苦しくない書き出しは、SNSやLINEにもなじみやすい表現です。
- 梅雨明けが待ち遠しい今日このごろ、そっちはどう?
- 蒸し暑いね、夏バテしてない?
- 最近、夜が寝苦しくなってきたね。
主語や丁寧語を省略することで、会話のような自然な流れが生まれます。
結び「暑さ厳しき折、お互い元気で…」
締めくくりは、思いやりを感じさせる場所です。
短くても、やさしい気持ちが伝わる一言を添えましょう。
- 暑さ厳しき折、お互い元気でいようね。
- 無理せず、ぼちぼち過ごしてね。
- また涼しくなったら、どこか行こう。
定型句にとらわれない自由さが、プライベートなやりとりの魅力です。
誤用を防ぐ:使い分け&注意点
時候の挨拶は、たった一文で与える印象を左右します。
たとえば「盛夏の候」と書くか「猛暑の候」と書くかで、受け取る印象は変わります。
季節の表現には、気づかいと教養が表れるものです。
ありがちな誤用と、季節に合った言葉の選び方を紹介します。
時期と気候に合わせた選択のコツ
言葉の選び方ひとつで、文章の印象が整います。
以下を目安にすると自然で伝わりやすいです。
- 向暑の候:6月末〜7月初旬。梅雨明けがまだの場合に。
- 小暑の候:7月7日ごろ。夏らしい気配が感じられるころ。
- 盛夏の候:7月中旬〜下旬。真夏日が続く時期に。
天気予報や気温の推移を参考にしながら、丁寧に言葉を選びましょう。
「猛暑」「酷暑」との違い
「猛暑」や「酷暑」は、気象報道などで使われるインパクトのある表現です。
しかし、丁寧な手紙の中で使うと過剰に聞こえることもあります。
- 猛暑:35℃以上の猛暑日を指す公式な言葉
- 酷暑:猛暑よりさらに過酷さを表す感覚的な語
たとえば「酷暑の候」と書くと、状況を強く印象づけすぎてしまう場合もあります。
「盛夏」や「向暑」を選ぶことで、やわらかく、気づかう気持ちが伝わります。
7月上旬の時候挨拶で、よくある質問8つ
1.7月の時候挨拶の例文を教えてください。
代表的な例文としては「拝啓 小暑の候、みなさまにはお健やかにお過ごしのことと存じます」があります。
フォーマルな文書でよく使われる表現でしょう。
天候や体調を気づかう文を続けると丁寧な印象になります。
» 7月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬で使える例文集
2.7月上旬の時候挨拶の例文にはどんな表現がありますか?
7月上旬には「向暑の候」「小暑の候」といった挨拶が適しています。
たとえば「向暑の候、みなさまにはますますご清祥のこととお慶び申し上げます」といった書き出しが一般的です。
相手に合わせて使い分けましょう。
»【7月初旬の時候の挨拶】おすすめ季語と迷わない言葉+伝わる気遣い
3.7月の挨拶でカジュアルな言い回しはありますか?
カジュアルな場面では「梅雨明けが待ち遠しいね」や「蒸し暑い日が続くね」といった自然な会話調の言葉がおすすめです。
手紙やメールでも、親しみを込めたいときに使いやすい表現といえるでしょう。
»【7月のカジュアルな挨拶】書き出しのおすすめフレーズ+メール短文例
4.7月の時候挨拶で花を取り入れたいときはどうすればいいですか?
季節の花を添えると、挨拶文がいっそう情緒豊かになります。
7月はアジサイや朝顔、ハスなどが代表的です。「アジサイの彩りが美しい季節となりました」といった形で入れると、自然な印象になるでしょう。
5.7月の時候挨拶をビジネスで使うときの注意点は?
ビジネスでは「拝啓 小暑の候」「向暑の候」など、季節と形式に合った挨拶を使うのが基本です。
結びでは「ご自愛ください」や「ご健勝をお祈りいたします」といった丁寧な言葉を添えると印象が良くなります。
»【7月のビジネスの時候挨拶】上旬〜下旬の例文+使い分け完全ガイド
6.7月下旬の時候挨拶にはどんな言葉が合いますか?
7月下旬には本格的な暑さが続くため「盛夏の候」「暑中お見舞い申し上げます」という表現が適しています。
体調を気づかう文章に仕上げることで、丁寧な印象を与えられます。
»【7月下旬の時候の挨拶】酷暑・大暑の候で印象アップする例文まとめ
7.8月の時候挨拶に変えるタイミングはいつ頃?
8月に入ったら「残暑の候」「立秋の候」など、暦の上では秋を意識した挨拶に切り替えます。
立秋(8月7日頃)を過ぎたら「残暑お見舞い」が適しており、時候に合わせて使い分けることが大切になります。
8.7月中旬の時候挨拶には、どんな表現が自然ですか?
7月中旬は「小暑」から「盛夏」への移行期にあたります。
「盛夏の候」や「暑中の候」という表現が自然で使いやすいです。
暑さが厳しくなる時期なので、体調への気づかいを添えると印象が良くなります。
»【迷わない7月中旬の時候挨拶】小暑・盛夏の候の使い方+書き出し例
まとめ:自分に合う挨拶文の選び方

本記事では、ビジネス・プライベート両方で使える具体的な例文や注意点を紹介しました。
7月上旬の時候の挨拶は、季節に合った言葉を選ぶことで印象が変わります。
丁寧な表現を身につけておけば、手紙やメールでの信頼感が自然と高まります。
ポイント
- 7月上旬は「小暑」「向暑」「星祭」などの季語が使える
- ビジネス文書では「拝啓〜の候」と定型の書き出しが基本
- プライベートでは自然な口語表現が親しみを生む
- 「猛暑」「酷暑」は使う時期と場面に注意が必要
- カジュアルでも一言の気づかいが印象を左右する
挨拶文は、相手との関係や自分の言葉のクセに合わせて変えていいものです。
形式的な文面に「自分の気持ち」をひと言添えるだけで、文章は温かくなります。
自分なりの挨拶文を見つけてみましょう。
- かしこまった印象を与えたいとき:定型文+時候の表現
- やわらかく寄り添いたいとき:自然な口語+日常への気づかい
- 自分らしさを出したいとき:一文だけアレンジを加える
「どんな言葉を使えば伝わるか」を考える時間が思いやりです。
以上です。
P.S. あたたかい挨拶を言葉で届けてみてください。
関連記事【7月時候の挨拶例文】ビジネス・私信で信頼と季節感を伝える言葉
関連記事【7月の挨拶文】上旬・中旬・下旬で迷わない季語と文例の正しい使い方