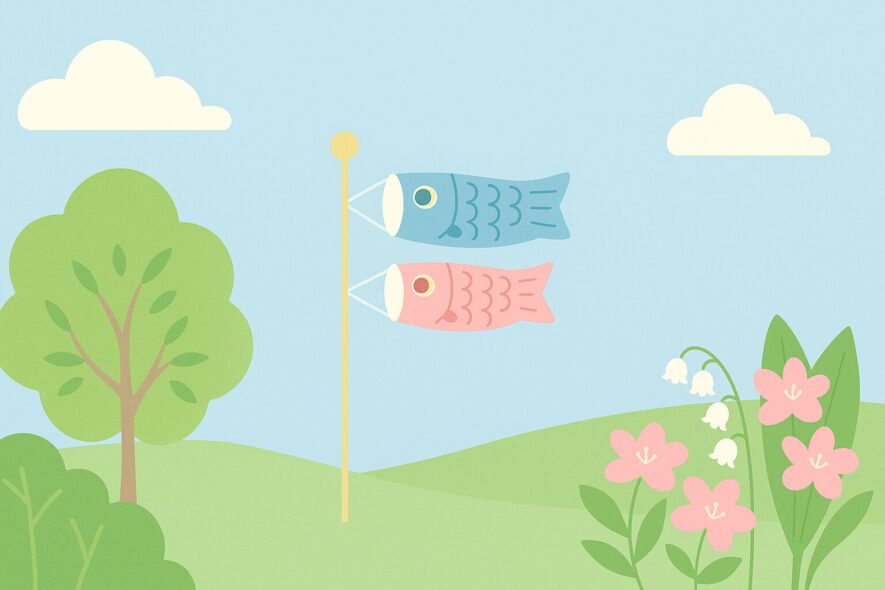- 5月の挨拶文、毎年ネット検索してるけど正解がわからない。
- 堅苦しすぎず、でも失礼のない表現ってどう書けばいいのかな。
- 季語とか書き出しのルールって、どこまで気にすればいいんだろう。
この記事でわかること
- 5月上旬の特徴や季語(新緑、若葉、薫風、立夏など)
- フォーマル・カジュアル・ビジネス文での使い分け
- 適切な書き出しや結びの工夫、避けるべきNG表現
- 相手別に配慮すべきポイント(ビジネス・友人・家族など)
- 5月の他の時期(中旬・下旬)や6月との違い
- Q&A形式で読者の疑問を具体的に解消
5月上旬の時候の挨拶は「季節感と思いやり」で、心の距離を縮める手段となります。
「自然の情景や季語」で、形式にとどまらない温かなやりとりが実現できます。
本記事では、5月上旬の特徴や季節に合った表現、相手別の使い分け、NG表現まで紹介します。
フォーマル・カジュアル・ビジネスのシーンにふさわしい一文が見つかります。
爽やかな初夏を迎える5月は、文章に「季節感や相手への配慮」を自然に込めるチャンスです。
5月上旬の時候の挨拶とは?

5月上旬の時候の挨拶は、新緑が芽吹き、自然の生命力を感じる季節感を伝える役割があります。
春の温もりを名残惜しみながら、初夏へと移ろうこの時期には、爽やかさと躍動感が満ちています。
たとえば、若葉の香りを含んだ風が、街をそっと包み込む情景を思い浮かべてみてください。
そんな自然の一コマを、手紙やメールにそっと忍ばせることで、相手との心の距離が近づきます。
この記事では、5月上旬ならではの季節感や、活用できる季語、シーン別の使い方をやさしく紹介していきます。
5月上旬の特徴と季節感
5月上旬は、春の終わりと初夏の始まりが静かに交差する時期です。
桜が散り、代わって若葉が勢いよく伸び、街中がまるで新しく衣替えしたかのように輝きます。
また、この時期の風はただの風ではありません。
「薫風」と呼ばれる、草木や土の香りを運ぶ柔らかな風が、心までそっと撫でていきます。
自然の息づかいを意識して言葉にのせると、ありきたりな挨拶も奥行きを持つようになります。
上旬に使える代表的な季語
5月上旬に使われる季語には、時代を超えて愛されてきた言葉が並びます。
- 立夏(りっか):夏の始まりを告げる日。5月5日前後にあたります。
- 新緑:初夏の光を浴びて輝く、若い葉の姿。
- 若葉:芽吹きたての、みずみずしい緑。
- 薫風:緑と花の香りを運ぶ、穏やかな初夏の風。
これらの言葉を使うことで、単なる季節感ではなく、その瞬間の情景や空気までも相手に届けられます。
たとえば「新緑の候」と記すだけで、目の前に瑞々しい若葉がそよぐ風景が浮かぶのではないでしょうか。
時候の挨拶が必要なシーンとは
時候の挨拶は、単なるマナーにとどまりません。
たとえば、取引先へのメールで「新緑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」と添えれば、ただの用件通知が、心のこもった便りに変わります。
また、友人や知人への手紙に「若葉が目にまぶしい季節となりましたね」と書けば、共に季節を感じるあたたかい関係性が生まれます。
日本独自のこの文化は、季節を大切にし、人とのつながりをより豊かにするために育まれてきたものです。
相手に合わせた言葉選びを意識し、自然なかたちで取り入れていきましょう。
5月上旬に使える時候の挨拶例文3選
5月上旬は、新緑がまぶしく、自然が静かに初夏の訪れを告げる季節です。
この時期、手紙やメールにひと言添えるだけで、その人らしさが伝わる文章に変わります。
挨拶文は、単なる形式ではなく、相手との距離を縮める小さな工夫です。
ここでは、フォーマル・カジュアル・ビジネスと場面に応じた例文を紹介します。
5月の風景を思い浮かべながら、あなただけの一文を見つけてみてください。
1.手紙・メールに使えるフォーマル例文
たとえば「新緑の候」という表現には、芽吹いたばかりの葉が陽の光を受けて輝く情景が込められています。
また「立夏」は二十四節気のひとつで、昔の人が自然のリズムを大切に暮らしていた証です。
こうした言葉を挨拶に使うだけで、文章全体にやわらかな品が生まれます。
- 新緑の候、みなさまにはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
- 若葉のまぶしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
- 立夏を迎え、日差しの中にも夏の気配を感じる今日この頃でございます。
読み手が季節を感じたくなるような一文を選ぶのが、フォーマル表現の魅力です。
»【5月の手紙挨拶】知らないと損する時候表現+3つのシーン別例文
2.親しい相手向けのカジュアル例文
朝の光がやわらかくなり、風にそよぐ若葉を見て、ふと誰かの顔を思い出すことはありませんか。
少しだけ季節を感じさせる一言を添えて、気持ちを伝えてみるのも素敵です。
たとえば、こんな表現が使えます。
- 若葉が風に揺れる季節になりました。
- 日差しがあたたかくなり、外を歩くのが楽しくなってきましたね。
- ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
自然な言葉に、ふだんの空気や思い出を重ねると、やさしい温度のある挨拶になります。
»【5月のカジュアル挨拶文】堅苦しさゼロで伝わる一言3選+注意点
3.ビジネス文書向けの例文集
ビジネスでの挨拶文は「形式」だけでなく「信頼」の土台になる部分でもあります。
「ご清栄」「ご繁栄」という表現は、相手の成功や健康を願う気持ちを、季節に重ねて伝える日本独自の言葉です。
5月上旬の爽やかさを取り入れることで、堅い文面にもほどよい柔らかさが加わります。
- 新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
- 立夏の候、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
- 若葉の美しい季節を迎え、みなさまにはお健やかにお過ごしのことと存じます。
形式の中にも、季節と気遣いが感じられる一文を選ぶことで、印象は変わります。
»【5月のビジネス挨拶文】信頼が伝わる例文3つ+時候の書き方ガイド
5月上旬の挨拶文を書くときの注意点

5月上旬は、自然の変化が目に見えて感じられる時期です。
そんな季節を言葉で伝える挨拶文には、小さな工夫で大きな印象の違いが生まれます。
形式どおりに整えるだけではなく「その人らしさ」や「気配り」が表れる文章にするにはどうすればよいでしょうか。
ここでは、避けたい表現や書き方のコツを、場面を思い浮かべながら紹介します。
避けたいNG表現とその理由
たとえば「春の訪れを感じる季節となりました」と聞くと、やさしい響きがあるようでいて、実は5月には不自然です。
すでに桜の季節は終わり、若葉が生い茂る初夏に入っているからです。
また「お元気ですか」など、話しかけるような言葉も、手紙の書き出しにはやや唐突に響く場合があります。
- ×「春の訪れを感じる季節となりました」
→ 5月は春から初夏へ移る時期であり、表現が古すぎる印象。 - ×「お変わりありませんか」
→ 丁寧ではあるが、文脈がないと意味が曖昧に感じられる。 - ×「お元気ですか」
→ 親しい間柄以外では、カジュアルすぎて唐突に感じられる。
自然や季節の動きとズレのない言葉選びが、伝わる文章の第一歩になります。
書き出しと結びのコツ
5月の風景を想像しながら、文章の始まりと終わりを整えてみましょう。
たとえば、新緑のまぶしさやそよぐ風をイメージし、その空気感を一文に込めると、心に自然が届きます。
結びの一言は、健康やつながりへの思いをやわらかく伝える役割があります。
- 書き出し:新緑の候、みなさまにおかれましてはお元気でお過ごしのことと存じます。
- 結び:季節の変わり目ですので、どうかご自愛くださいませ。
- 結び:今後とも変わらぬご交誼のほど、よろしくお願い申し上げます。
書き出しと結びを整えるだけで、全体の印象が丁寧で洗練されたものになります。
相手別に気をつけたいポイント
相手が誰かによって、言葉の感じ方は変わります。
同じ「新緑」という言葉でも、ビジネス文書では格式ある響きに、家族宛の手紙では季節の喜びを共有するやさしさになります。
相手を思い浮かべながら文面を整えることで、その人との関係性まで言葉ににじみ出ます。
- ビジネス相手:立夏の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
- 友人:日差しがやわらかく、散歩が気持ちいい季節になりましたね。
- 家族:新緑がきれいなこの時期、みんな元気に過ごしているかな?
その文面を受け取った人が「自分らしい」と感じてくれる挨拶が、一番心に残るのかもしれません。
5月上旬の時候挨拶で、よくある質問
5月のおたよりで使える時候の挨拶はありますか?
はい「新緑の候」や「若葉の季節を迎え」などが使いやすいです。
爽やかで落ち着いた季語を選ぶと、5月上旬のおたよりにふさわしい印象になります。
» 5月のおたよりに使える時候の挨拶3選【自然に気持ちが伝わる書き方】
カジュアルに5月の挨拶を伝えるにはどう書けばいいですか?
たとえば「若葉がまぶしい季節になりましたね」など、やわらかい語り口が自然です。
会話調に近づけると親しみが伝わりやすいです。
»【迷わず使える】5月のカジュアルな挨拶例文3選【気持ちが伝わる】
ビジネスで使える5月の時候の挨拶には何がありますか?
「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」が定番です。
立夏の候なども5月上旬にはふさわしいフォーマルな表現です。
»【5月の時候挨拶(ビジネス)】相手別に使える3つの好印象フレーズ
5月の挨拶文の書き出しで気をつけることは何ですか?
季節感に合った言葉を選び、相手への配慮を込めることが大切です。
「新緑の候、みなさまいかがお過ごしでしょうか」などが自然で丁寧です。
»【5月の時候挨拶】手紙・ビジネスにも使える例文+好印象な書き出し
5月下旬にふさわしい時候の挨拶はありますか?
「薫風の候」「若葉青葉の折」などが5月下旬らしい表現です。
春から初夏への移り変わりを意識した言葉を選ぶと自然な印象になります。
»【5月下旬の時候挨拶】ビジネス・カジュアル例文で季節感を伝える方法
5月の面白い挨拶ってどんなのがありますか?
「若葉の季節に草木と一緒に成長中です」など、ユーモアを交えた表現も使えます。
ただし、相手や場面を見極めて使うのがポイントです。
»【5月の面白い挨拶】笑顔が生まれる一言3選×2+失敗しないコツ
5月中旬の時候の挨拶でおすすめはありますか?
「新緑の色が深まる季節となりました」などが中旬に適しています。
立夏の候などの二十四節気を用いるのも上品な印象になります。
» 5月中旬に使える時候挨拶の例文2種【自分らしい気持ちが伝わる表現】
6月の時候挨拶は、5月とどう違いますか?
6月は梅雨の始まりが多く「入梅の候」や「長雨の折」などが使われます。
爽やかな5月とは異なり、湿り気や季節の変わり目を意識した挨拶が合います。
まとめ:5月上旬にふさわしい挨拶を自然に取り入れよう

5月上旬は、自然の移ろいとともに挨拶文にも季節感が求められます。
やさしい言葉選びを意識することで、手紙やメールに彩りを添えられます。
本記事の要点
- 5月上旬は「新緑」や「若葉」など、自然の力強さが感じられる季節
- 季語には「立夏」「新緑」「薫風」などがあり、時期に合った選び方が大切
- 挨拶を使う場面は、ビジネス、カジュアル、親しい相手など幅広い
- 目的別に使えるフォーマル例文・カジュアル例文・ビジネス例文を紹介
- 書き出しと結びには季節の空気を感じさせる言葉を意識すると好印象
- 相手や状況に合わせた言葉遣いが、挨拶の印象を左右する
5月上旬は、新緑がまぶしく、木々の葉がやさしく揺れる季節です。
風景を言葉に映して届ける時候の挨拶には、単なる形式を超えた意味があります。
たったひと言でも、心に残るあたたかいやりとりになることがあるからです。
大切なのは、文章の正しさだけでなく「相手を思い浮かべながら書く」こと。
気持ちが、言葉に自然なやさしさを与えてくれます。
忙しい日々のなかで、手紙やメールに一瞬の静けさや季節の気配を添えることです。
以上です。
P.S. 小さな心づかいが、相手との関係を深めるきっかけにもなります。
関連記事【5月の挨拶文】仕事・私用で使える例文3選+やさしく伝わる季語
関連記事【5月の季語挨拶】シーン別の例文3選【季節感を簡単に伝える方法】