- できるだけ簡単な読書ノートの書き方を知りたい
- 本を読むたびに読書ノートを書くのはめんどくさい
- 読書ノートの効果に疑問。書かなくても良いのでは
この記事はそんな方へ向けて書いています。
この記事でわかること
- 読書ノートの書き方
- 読書ノートのテンプレート:本のタイトルを1行
本記事の信頼性
- 読書歴:1996年4月より読書
- 読書日記歴:1999年より記録
- 読書数:一般書籍4,982冊+漫画1,439冊
浪人生時代に読書習慣を得ました。
会社員時代の年間390冊ほど読みました。
本記事では、読書日記の書き方を解説します。
この記事を読むことで「読書日記の書き方やテンプレート」がわかります。
Contents
読書ノートの書き方は簡単【目的別の書き方】
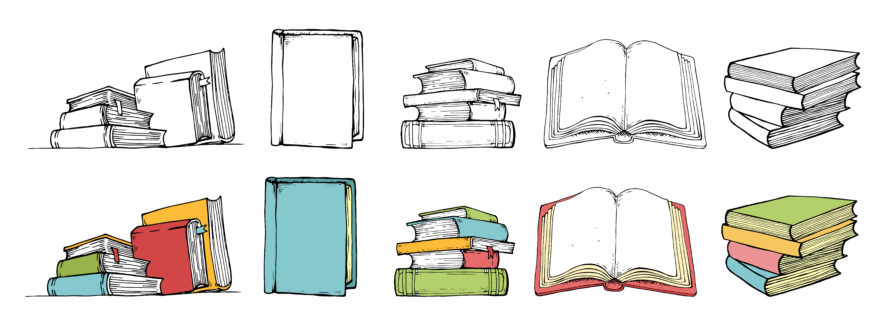
読書ノートの書き方は「読んだ本のタイトルを1行書く」だけです。
「読書ノート、読書日記、読書感想文、書評」の違い
- 読書ノート:読んだ記録
- 読書日記:気づきのメモ
- 読書感想文:感想(主観)
- 書評:本の紹介(客観)
読書ノート:読んだ記録
あとで見返したときに何を読んだかわかればOKです。
読書日記:気づきのメモ
読書ノートより数行多くなります。
「ビフォー、気づき、To Do」などです。
読書感想文:感想(主観)
「自分のため」に書くのが読書感想文です。
本を読んで「自分が何を思ったか、考えたか」です。
書評:本の紹介(客観)
「人のため」に書くのが書評です。
未読の人に向けて、本の内容を紹介しつつ批評します。
読書感想文より客観的なイメージです。
読書ノートの書き方:タイトルの1行だけ
「本のタイトル」を書くだけなので簡単です。
タイトルだけなら、どんなに忙しくても書けます。
1999年から23年間続いています(2023年9月時点)。
身体を壊すくらいの激務の時期もありましたが、習慣化できています。
読書ノートは簡単だからいいのです。
誰にでも継続できます。
読書日記の書き方:ビフォー、気づき、To Do
「タイトルだけでは物足りない。読んだ内容も記録したい」と思う方もいるかもしれません。
「アウトプット大全」から受け売りですが、下記3つを加えることで重みのある「読書日記」に変化します。
- ビフォー
- 気づき
- To Do
1.ビフォー
読む前の状況です。
言い換えれば「問題提起」です。
たとえば「読んだ理由、知りたかったこと、本で解決したかったこと」などです。
2.気づき
読んでどうなったか「結果の明示」です。
たとえば「考えたこと、気づいたこと、学んだこと、印象に残った3つと理由、体験談、ちょっと関係ない話」などです。
3.To Do
読んだあとの「行動設計」です。
読んだ内容を身につけるための「To Do:やることリスト」です。
以上の3つで「タイトルだけの読書ノートから立派な読書日記」に変わります。
3つを意識しながら読むことで、本から得るものも増えるはずです。
読書感想文の書き方:気づき、考え、変化
たとえば、以下を盛り込みます。
- 本のタイトル、著者
- あらすじ
- 読んだきっかけ
- 考えたこと(深堀り)
- 気づいたこと(深堀り)
- 変化したこと(深堀り)
- 読む価値はあるのか
- 誰におすすめか
「もっと文量を増やしたい」と思うなら「2.気づき」を増やします。
- 気づいたこと
- 考えたこと
- 変わったこと
1.気づいたこと
言い換えれば、学んだことです。
- 本から何を学んだのか
- 本から何を気づいたのか
知らないことを知ることが読書の喜びです。
わからないことがわかるのが、成長です。
2.考えたこと
本の内容紹介は不要です。
読めば、わかるからです。
大事なのは「読んだときに自分が考えたこと」です。
考えたことは「その時かぎり」のものだからです。
オリジナルな自分だけの記録なのです。
3.変わったこと
言葉は人を変える力を持っています。
本を「読む前と、読んだ後」では変わったことがあるはずです。
たとえば、料理の本であれば「新しいレシピと野菜の名前を知った。作る過程で包丁の持ち方を習得した」など。
読書は自分を変化させます。
読書の記録は「成長記録」でもあるのです。
読書ノートのテンプレート:具体例と継続のコツ
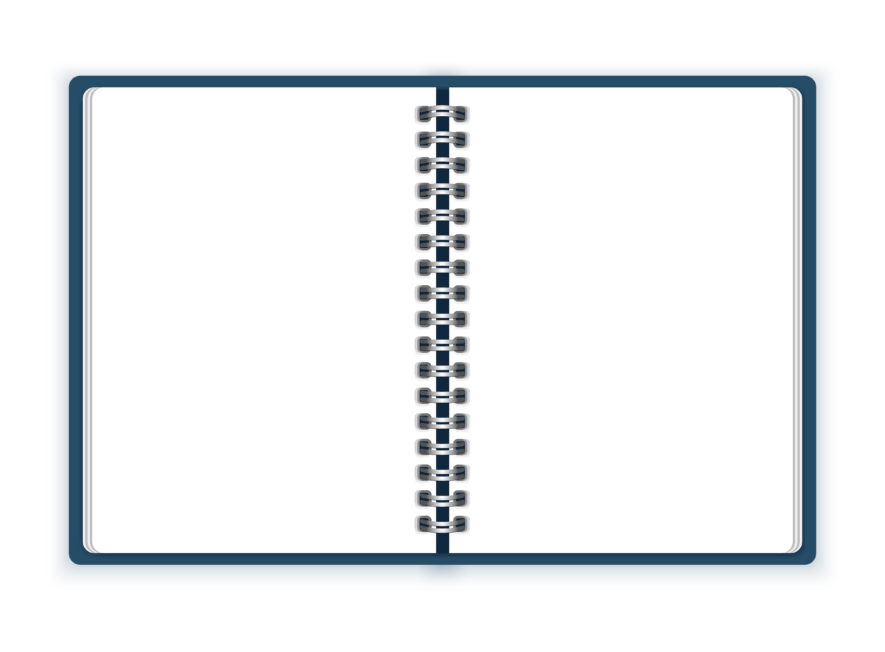
読書日記のテンプレートは「タイトルを書く」だけです。
感想を1行でも追記すれば立派な読書日記です。
タイトルの1行だけ書けばいい
1999年から読書日記を「Campusノート(100枚)」につけています。
書くのは、本のタイトル1行だけです。
正確には次の3つを1行に書いています。
- タイトル
- 今月の累計冊数
- 今までの累計冊数
ノートの写真
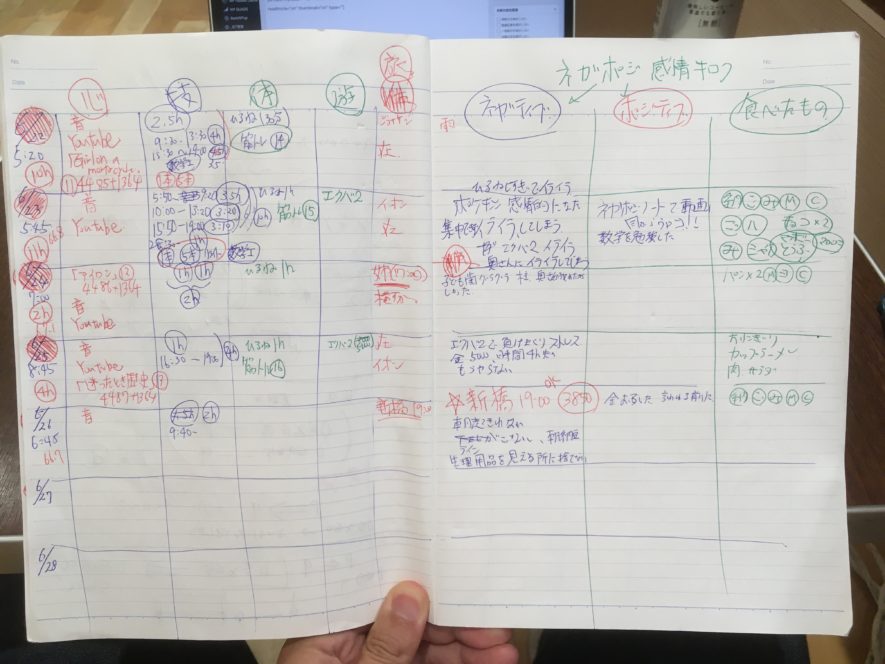
1番左の列が、本のタイトルです。
たとえば、6月25日は「迷ったとき歴史、13、4,487+1,364」です。
- 本のタイトル:迷ったとき歴史
- 6月の累計冊数:13
- 累計冊数:本4,487+マンガ1,364
これだけです。
他の項目(ブログの時間、ランニング距離など)もあるので、これ以上は必要ないのです。
感想を書きたければ、ブログやTwitter、インスタ、YouTubeにアウトプットしたほうがメリットがあります。
継続のコツ:ハードルを下げる
読書日記に「本のタイトル、著者名、出版社、ページ数、書かれていること、気づき、感想」などたくさん書く人がいます。
素晴らしいです。
私には真似できません。
特に「感想を書く」はハードルが高いです。
ハードルの高さは「継続の壁」です。
おすすめしません。
感想をムリに書こうすると、しんどくなります。
しんどいものは続きません。
経験的に3ヶ月が限度です。
ハードルは歩いてまたげる高さでOK
「読書日記で本のタイトルだけ書く」は低いハードルです。
1行で終わるので続けられます。
1999年から読書日記を継続できています。
ムリしないことです。
感想文は書きたくなったら書けばいいのです。
読書日記の本質は「継続」です。
歯を磨くように継続できれば、1行でもいいのです。
ムリをする必要は一切なし
ムリなプランをつくらないほうがいいです。
理想は自分のキャパシティよりちょっと上くらい。
読書日記のテンプレートも「タイトル以外にも書ける」という人は試してみるのもあり。
ただ上を目指したら継続できません。
たとえば、私は会社員時代、毎日3時間の英語学習を義務づけました。
会社から帰宅後、辛い思いをしながら勉強するのです。
続くわけがありません。
見事に挫折しました。
できる範囲で楽しくやるから、継続できるのです。
決意が続かないのは、ムリなスケジュールだからです。
いかにハードルを下げられるか。
いかに読書を楽しめるか。
タイトル1行は「読書日記を楽しむテンプレート」なのです。
読書ノートの効果:自分の世界が構築される
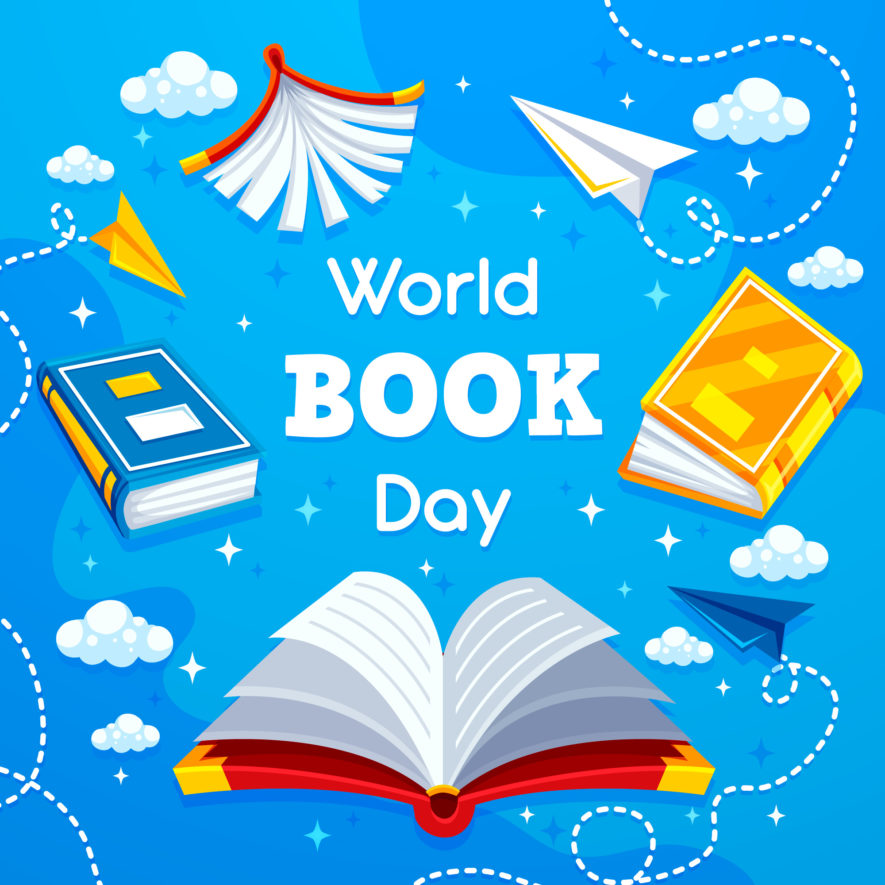
読書日記の心は「世界をつくりたい」です。
読書の記録で、人生を充実させたいのです。
世界がつくられていくのは楽しい
ノートにコツコツと本のタイトルが積み重なると、世界がつくられていく喜びがあります。
ノートには他にもブログを書いた時間、ランニングの距離などの行動記録や、嬉しかったこと、ネガティブなことなど感情の記録もしていいます。
振り返れば、気づきが生まれます。
- 「あ、この時期はこんな本を読んでいたんだ」
- 「ランニングに集中しながら、この本を読んだな」
- 「ブログで成果が出ないから、ブログ関連の本ばかりだ」
読書以外のことが、読んだ本を思い出すきっかけです。
読書日記を振り返ることは、まさ人生日記を読むことなのです。
生まれるインスピレーション
読書日記の「本のタイトル」を眺めると、ひらめきが生まれることがあります。
愛着のある本をどう読んだかが、思い出されるからです。
たとえば、音楽を聴くと、当時の思い出が蘇ることがあります。
本も同じです。
- 何を学んだのか
- どこで読んだのか
- どんな思いで読んだのか
ネットで情報収集するだけでは得られないメリットです。
1冊の本を読むことは、人生の貴重な時間を使うことです。
影響を与える本は、それだけ思い入れのあるものなのです。
読書日記で思考の幅が広がる
「本のタイトル」が並んでいくと、思考のベースとなる本棚になっていきます。
10冊、20冊と増えていくにつれ、思考の幅の広がりを感じます。
世界を広げたくなり、もっと本を読みたくなるはずです。
大事なことは「本のタイトル」がはっきり見えるように書くこと。
「本のタイトル」が読めないと、なんの本を読んだのかわかりません。
読んだことが思い出せないのは、もったいないです。
「本のタイトル」がわかれば、なんとなくタイトルを見るだけでも、内容を思い出せます。
読書日記を開くたびに、読んだこと、学んだことが自分に刷り込まれていくメリットがあるのです。
読書ノートを23年続けた感想3つ

読書日記を23年続けた感想は「インプットとアウトプットはセット」です。
理由は3つです。
- インプットだけでは身につかない
- 読んで行動しないと、意味がない
- アウトプットだけでは、足りない
順番に解説します。
1.インプットだけでは身につかない
4,623冊の本を読んできました。
本の内容はほとんど覚えていません。
アウトプットしていないからです。
- インプットだけの本 → ほとんど内容を忘れている
- アウトプットした本 → インプットだけより覚えている
ゆえにアウトプットしないと忘れてしまうものなのです。
読んだら、書く
本の内容を身につけるには「読んだら早めにアウトプット」です。
- ブログに書く
- 人に話す
- Twitterで呟く
- インスタを投稿する
- YouTubeで解説する
2回、3回と繰り返すうちに、本の内容が確実に消化される感覚です。
どんな形でもいいので早めにアウトプットなのです。
読めば、書けます。
読まないと、書けません。
たくさん読めば、たくさん書けます。
膨大なアウトプットをしたければ、膨大なインプットをするだけです。
読むことで思考の幅が広がります。
書くことで思考が、整理されます。
「読む、書く」の両輪を回すことが、読書の醍醐味です。
「思考をまとめる」という軽い気持ちで書くのもありですね。
2.知識をスキルに変えないと意味がない
本を読んで知識を蓄えても、行動しないと意味がありません。
頭の中にある「ただの情報」で終わってしまいます。
知識をスキルに変換する必要があります。
- 知識:知ってるだけの状態
- スキル:知識を活用できる状態
本を読んでも、スキル変換しないと結果に繋がらないのです。
どうやって知識をスキルに変換するのか?
実際に活用してみるだけです。
たとえば、以下です。
- Webマーケティングの知識を得た → ブログに活用する
- ライティングの知識を得た → 知識を活用して文章を書く
- セールスライティングの知識を得た → 商標記事で活用する
本で得た知識を活用することです。
インプットだけでは、何の役にも立ちません。
時間が経つにつれ、記憶から消えていきます。
読書習慣は身につきますが、読んだ内容は消滅するのです。
3.アウトプットだけでは、足りない
アウトプットだけでは、その他大勢になるからです。
解決策は2つです。
- 大量にインプットする
- 自分のフィルターを通す
1.大量にインプットする
人と同じインプットをしていたら、人と同じアウトプットしかできません。
本を読むだけで差別化できますが、差別化する方法は「量」です。
人よりたくさん読むことです。
シンプルですが、これに尽きます。
2.自分のフィルターを通す
インプット内容を、右から左にアウトプットするだけでは意味がありません。
誰でもできる作業だからです。
- 自分なりに情報を加工する
- 自分の経験を交えて発信する
- 持っている情報を組み合わせる
知識の差別化のためには「勉強×体験」です。
できていないことだらけですが、以上の3つが読書日記を23年続けた感想です。
読書が10年後の自分をつくる
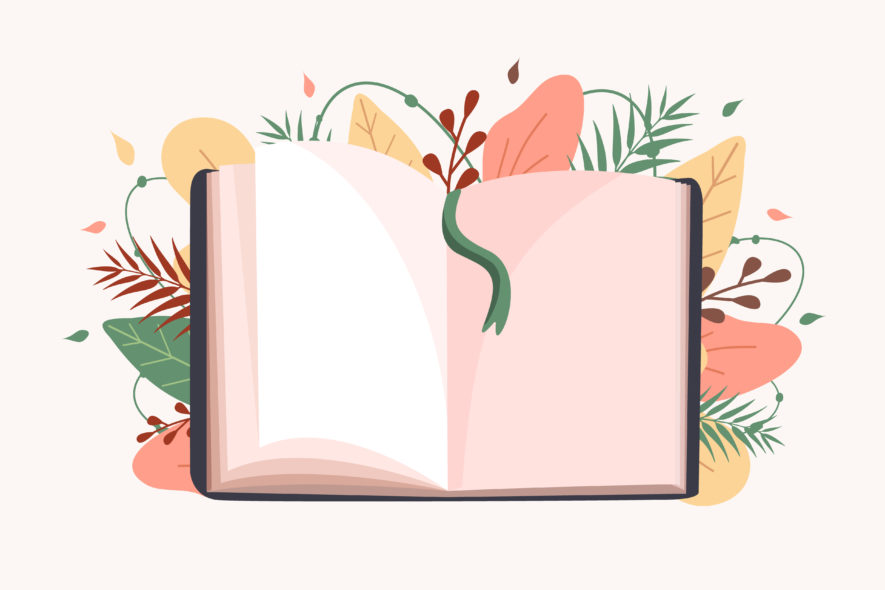
今読んでいる本が10年後の自分をつくります。
手に取った本は興味そのもの
人間は1%も興味のない行動は起こせません。
たとえば、就職活動の会社説明会です。
希望していない会社でも、少しでも興味があれば受けていました。
逆に、興味ゼロの会社説明会は行きません。
正確には、行けませんでした(申し込んでも当日に面倒になる)。
読書も同じです。
興味のない本は書店に行っても、触れることさえありません。
興味があるから手にしたのです。
- 個人事業主の本を読んだ
- ブログ運営の本を読んだ
- 文章の書き方の本を読んだ
上記の人は、10年後にブログで生計を立てている可能性があります。
「たかが読書じゃないか」という意見もあるかもしれません。
たしかに、本を読むだけで10年後の自分がつくれれば苦労はしません。
ただ自分の思考をつくるのは読書です。
経験から言えます。
「頭の中で言葉を並べて、考える行為は読書によるものである」と。
「体系的、網羅的、専門的な知識を得るには、やはり読書である」と。
ゆえに以下の2つの質問を考えてみるのもありです。
- 10年後どうなっていたいか
- 今の自分は何を読んでいるか
難しい本じゃなくてもいい
読書といっても「難しい本を読んで自分をつくろう」じゃないです。
エッセンスを凝縮した時間帯効果の良い本があります。
- 初心者向けの本
- マンガでわかるシリーズ
本から何を吸収できるかが、大事です。
吸収のない読書は時間のムダです。
とはいえ学びがない読書はありません。
どんな本でもキラリと光る1行はあるからです。
たった1行で自分にテコ入れできます。
難しい本が正義ではないのです。
最初から最後まで読まなくてもいい
「身銭を切って買った本だから、最初から最後まで一字一句読まないともったいない」
過去の自分はそう思っていました。
「買って失敗した。ちょっとおもしろくない。難しい」と思った本でも、もったいないから一字一句読んでしまうのです。
意味がありません。
- 何も理解できない
- 何も記憶に残らない
- ちっとも読書が楽しくない
良いことが1つもありません。
読書のモチベーションを下げるだけです。
- 価値のある本:いまの自分に役立つ
- 価値のない本:いまの自分に役立たない
価値ない本は、いったん閉じて放置してもOKです。
成長した1年後に、また読みたくなるかもしれません。
1年後の自分に「価値ある本」に変わっている可能性もあります。
読書を楽しむコツ3つ
- 面白くないところは飛ばす
- 興味のあるところだけ読む
- 全ページ一字一句読まない
何か吸収できればいいのです。
極端な話、目次だけ見て吸収できるものがなければ捨ててもいいのです。
自分を変える1行が見つければいいのですね。
読んだらアウトプットする
本は読み終ったら、アウトプットするのがコスパの良い行動です。
本の内容をアウトプットすると、吸収・理解が深まるからです。
たとえば、以下です。
- 誰かに話す
- ブログに書く
- ツイートする
アウトプットで記憶に定着します。
読みっぱなしで何もしないのはもったいないです。
簡単にツイートするだけでも効果はあります。
» 読書の質を上げるTwitterの書き方【本の感想をツイートする】
まとめ:「インプット→行動→アウトプット」のサイクルを回す
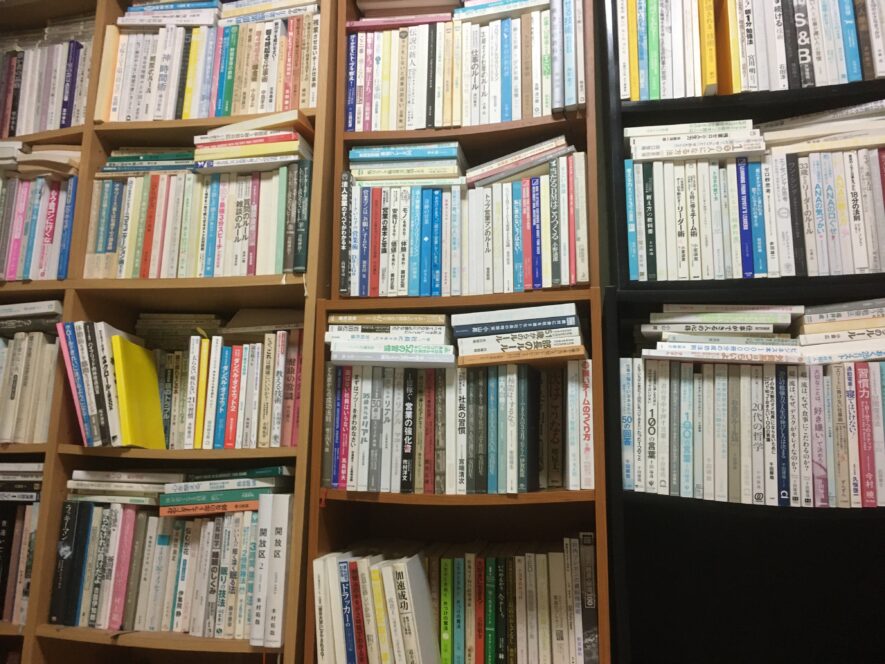
読書内容を財産にするコツ
3つのサイクル「インプット→行動→アウトプット」を回すことです。
どれか1つでも欠けては意味がありません。
ただ読書するだけではもったいないです。
右から左へ流すだけでは意味がないのです。
読書をより良い時間にするために、読んだあとが大事です。
本は買ったほうが身につく
理由は3つです。
- 身銭を切ると真剣になる
- 本の背表紙を眺められる
- リアルの本棚が、できる
読書日記でノートに本棚を作るのも有効。
本を購入してリアルの本棚を作るのも有効。
どちらも価値はあります。
ゆえに両方すればいいのです。
自分だけの本棚ができあがり、知識や知恵、考えがつながったとき、新しいものが生み出されます。
本棚を眺めて、手に取った本には、その時の自分に必要は解決策が書いてあります。
読書日記の書き方を知り、実際に書いてみる
読書日記の書き方は人それぞれです。
私の書き方は「読み終えたら追記していくスタイル」で、1ヶ月ごとに書いています。
ほとんどは「Kindle Unlimited」で無料で読んだ本です。
読みたい本が次々に見つかります。
多読する方は十分にもとが取れます。
まずは読み放題の対象本を見るのもありです。
読書日記には本のタイトルを1行だけ書く
読書の習慣化ができたら、感想を1行でもアウトプットしてみる。
感想を1行アウトプットできるようになったら、3行にしてみる。
3行書けるようになったら、Twitterで140字の感想を書いてみる。
140字の感想が書けるようになったら、800字、1,500字、3,000字とレベルアップしてみる。
徐々に書けるようになるのは、楽しいことです。
読書はコスパの良い最高の自己投資です。
血肉になった本は誰にも奪えません。
本は投資価値のあるものです。
読書で「思考の骨格」が強化されます。
以上です。
P.S. 読書日記への記録で、確かな世界がつくられていくのです。
関連記事アウトプット術がわかるおすすめ本ランキング10選【人生を変える】
関連記事日記の書き方がわかる『日記の魔力』【人生の記録が道しるべになる】
